
県立高等技術専門校における職業訓練についての質問
目次
県立高等技術専門校における職業訓練について

私は、県立高等技術専門校における職業訓練について質問します。
今では、どの分野においても人手不足ということが言われています。
若い人たちが県外に流出してしまう。
仕事がないとか、人材の流出ということがある中で、県立高等技術専門校、県内には、青森高等技術専門校、弘前高等技術専門校、八戸工科学院、むつ高等技術専門校がありますけれども、これらの高等技術専門校がもっと周知されていくべきと思います。
もっと入学する人が増えてほしいと思います。
【質問①】各校の入校率の推移を伺いたい。
現状などを確認しながらご質問していきたいと思います。
はじめに、県立高等技術専門校の各校の入校率の推移を伺います。
回答:原産業イノベーション推進課長
- 県では、青森、弘前、八戸及びむつの県内4市に県立高等技術専門校を設置し、新規学卒者や離転職者、さらには企業で働いている方を対象に、多様化・高度化する人材ニーズを踏まえて、即戦力となる産業人材を育成しています。
- このうち、新規学卒者や離転職者を対象とした訓練科の過去3か年の入校率の推移は、
- 青森校が定員40名に対して、令和5年度60%、令和6年度20%、令和7年度35%。
- 弘前校が定員75名に対して、令和5年度86.7%、令和6年度76%、令和7年度58.7%。
- 八戸校が定員95名に対して、令和5年度61.1%、令和6年度32.6%、令和7年度44.2%。
- むつ校が定員35名に対して、令和5年度60%、令和6年度48.6%、令和7年度40%となっています。
年によっては、非常に低かった年もあることが分かりました。
5割に届かない年もありますが、青森、弘前、八戸、むつの高等技術専門校には、いろいろな学科がある中でやはり特定の学科に人気が集中してしまう。
申込みが多いところ、逆に、少ないところというのがあると思いますけれども、入校率の高い訓練科と低い訓練科の内容について伺います。
回答:原産業イノベーション推進課長
- 4つの県立高等技術専門校に設置している計13の訓練科のうち、弘前高等技術専門校と八戸工科学院に設置している自動車整備科の入校率が比較的高くなっており、令和7年度においても、ともに100%となっています。
- 一方、それ以外の訓練科の入校率は50%を下回ることが多くなっています。
自動車整備科の入校率は100%ということで人気があることが分かりました。
ほかの訓練科は50%を下回るところが多いということでした。
高等技術専門校に入校する男性または女性、その比率、割合というのは、どういった状況でしょうか。
回答:原産業イノベーション推進課長
- 4つの県立高等技術専門校の令和7年度入校生114名のうち、女性は8名で、割合は7%となっています。
- 内訳は、弘前高等技術専門校の自動車整備科に1名、総合建築科に2名、造園科に3名、ライフライン設備科に1名、八戸工科学院の自動車整備科に1名となっております。
7%ということで、理工系科目は女性の進学が少ないということを今でも言われていますが、男性、女性というのはそもそも関係ないものと思っていますし、より周知していく、魅力をもっと発信していくことも必要と思います。
私も調べてみたところ、例えば、学費に関しても、年間で入校費、諸経費を含めて20万円から30万円という学科があり、一方で、造園科、ライフライン設備科は入校料、授業料が無料というところもあるので、もっと周知されていくべきと思いますし、入校生をより確保していく必要があると思います。
県立高等技術専門校の入校生を確保するための取組について伺います。
回答:原産業イノベーション推進課長
- 県立高等技術専門校の入校生を確保するため、各校において、県内の高等学校等を訪問し、進路指導の教員等にPRしているほか、教員を対象とした学校見学会や生徒及び保護者を対象としたオープンキャンパスの開催、SNSを活用したPR等を実施しています。
- また、高等学校が実施する進路ガイダンスや出前授業への出席、イベントへの参加など、積極的なPR活動を行っています。
今後とも、関係機関と連携し、県立高等技術専門校の認知度向上に努めてまいります。
【質問②】校全体の就職率の推移を伺いたい。
頑張って粘り強く続けていただきたいと思います。
次に、県内4校全体の就職率の推移について伺います。
回答:原産業イノベーション推進課長
- 県内4校全体の過去3年の就職率は、令和4年度は100%、令和5年度は93.5%、令和6年度は令和7年4月末現在で96.2%となっています。
就職率が非常に高い。4校全体で100%のときもあるということです。
これは非常に高いと思います。
だからこそ、入学者が増えると就職率が変わってくるかもしれないですけれども、高等技術専門校で専門的な技術を学んで、そして生かしていってほしい、就職につなげていってほしいという思いがあります。
ちなみにですが、就職に関して、県内の企業への就職、県外の企業の就職の割合についてはどういった状況でしょうか。
回答:原産業イノベーション推進課長
- 県内就職の割合でございますが、令和6年度修了生の校全体の県内就職率は、令和7年4月末現在、84.8%となっております。
県内就職の割合もやはり高いということで、県外に流出することを防ぐためにも、高等技術専門校がもっと周知されていってほしいと思います。
そして、要項も確認したところ、基本的に2年コースと1年コースがあるということで、1年コースは高卒者だけではなく、離職者、社会人も入れるというのに対して、2年コースは高校卒業した方だけが対象になっています。
2年コースも、1年コースと同様に離職者も入れるといった間口が広げられると良いと思います。
これは国で定められているからできないというものでしょうか。
それとも、あえて2年コースは高卒者を対象にしているのでしょうか。
離職者を対象にしない、学び直しということもあると思います。
2年コースに関しては高卒者だけを対象にしている理由について伺いたいと思います。
回答:原産業イノベーション推進課長
- 2年課程につきましては、新規学卒者を基本としておりますけれども、離転職者、ハローワークで求職をされている方についても入校可能でございます。
- その場合は、まず初めにハローワークのほうに御相談をしていただいて、保険等の手続をしていただくということになります。
離職者も2年コースに入校可能ということでした。
2年コースには、電気設備、土木、自動車整備、総合建築など、本当に魅力的なコースがあります。どの分野も人手不足と思いますが、建設や建築も本当に人手不足と言われていますし、間口がより広がっていくように、そして、離職者の方もより積極的に活用できるように、周知を頑張っていただきたいと思います。
【質問③】在職者訓練に関する企業ニーズについて、県はどのように対応しているか伺いたい。
そして、高等技術専門校において、今、在職者訓練も行われていると思います。
在職中の人を対象にして、高度な技能の習得を図るため、より充実させることを目的として、講習を各校で行っていると思います。
ある企業の方から、電験三種という科目に関して、県で講習を行うのかと聞かれました。
電験三種の取得のために従業員が頑張って勉強しているけれども、独学ではなかなか難しいということで、例えば、県で講師のあっせんとか、そういった講習を開いているかという御相談が寄せられました。
在職者訓練に関して、メニューはそろえていると思いますけれども、企業のいろいろなニーズがあると思います。在職者訓練に関する企業ニーズについて、県はどのように対応しているのか伺います。
回答:原産業イノベーション推進課長
- ものづくり企業等で働いている方の職業能力の向上を図っていくため、県では、4つの県立高等技術専門校において在職者訓練を実施し、各種資格の取得や新技術・技能の習得を支援しております。
- 訓練の実施に当たっては、企業のニーズにしっかりと対応していく必要があることから、企業や業界団体への調査、さらには訓練生へのアンケートなどによって訓練ニーズの把握に努めています。
令和7年度は、職業能力の多様化、高度化が進む中、前年度と比較して、コース数で19コース多い計60コース、訓練定員で200名多い計905名の訓練を計画しているところです。 - 委員のお話にありました電験3種につきましては、技術専門校で訓練している内容から比較しますと少し高度な技術ということですので、現在は行っておりませんけれども、今後検討していき、企業で働いている方に対する実効性のある訓練を通じて、地域が求める人材の育成に取り組んでまいります。
資格によって難易度は違うので、すぐに対応するというのも難しいと思いますけれども。
今、人手不足の中で頑張っている企業のうち、従業者にもっとスキルアップしてほしいけれどもなかなか進まないというところには、こういった在職者訓練なども活用して、いろいろな現場で活躍してほしいです。
繰り返しになりますけれども、県立高等技術専門校、就職率がすごく高いのに、全体的な入校率が低いという状況です。
学費も決して高いわけでもないので、特に高校生に周知、認知してもらうよう、私も高校生に御紹介できる機会があればと思いますけれども、周知を引き続き頑張っていただきたいと思います。

ご意見・ご感想など
あなたの声を聞かせてください。





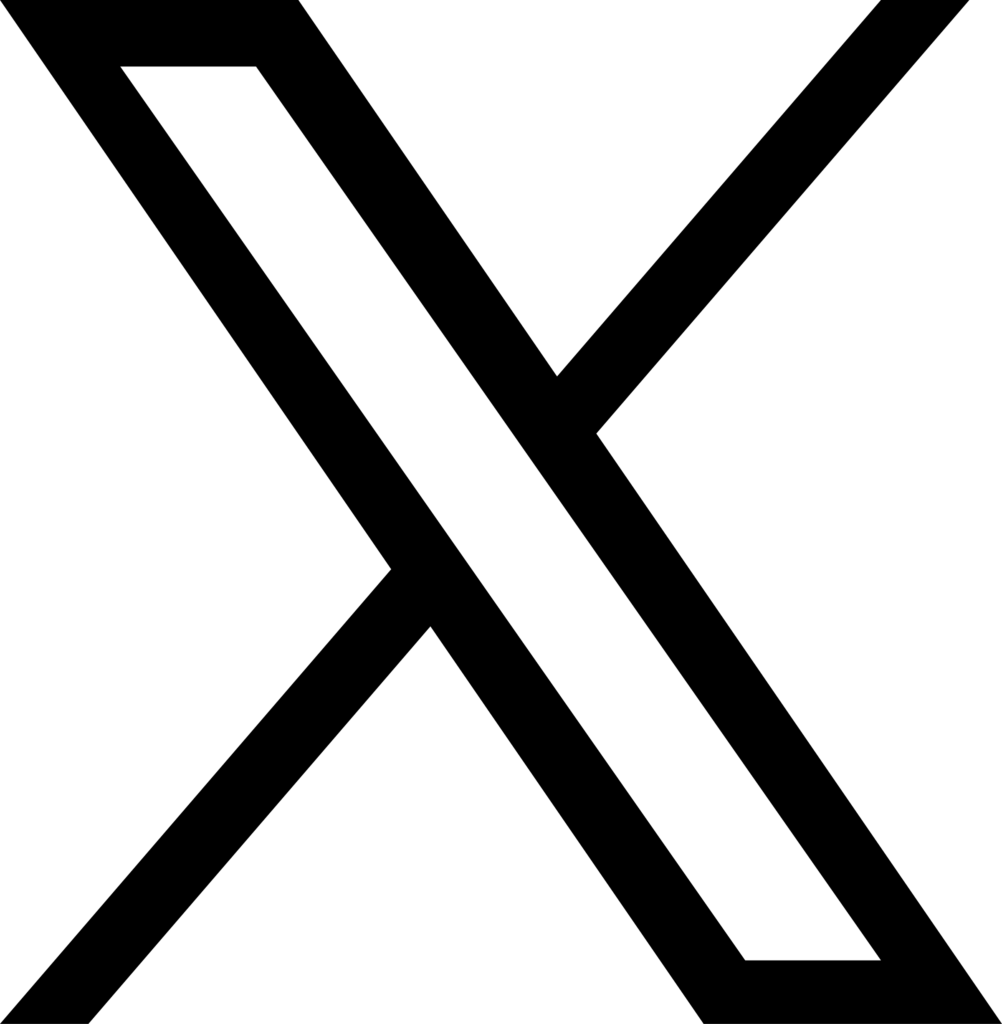
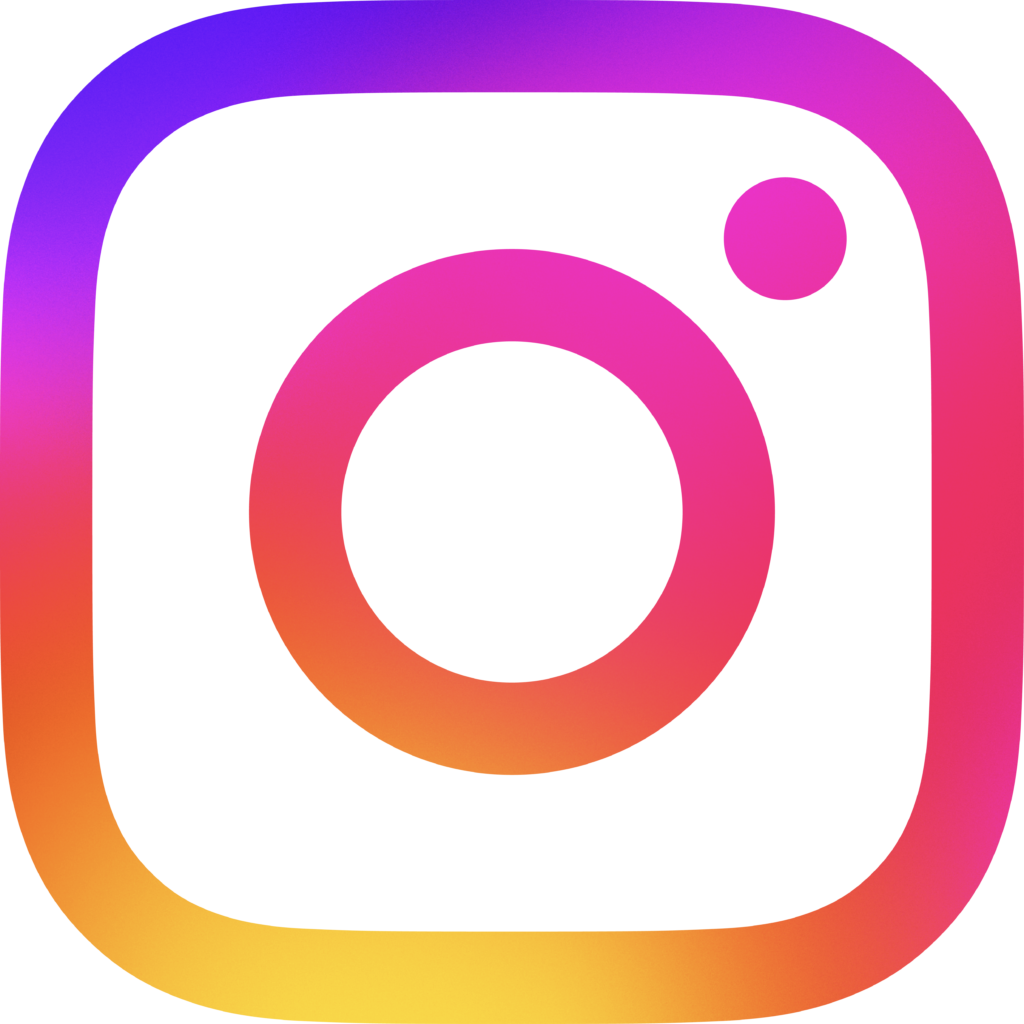

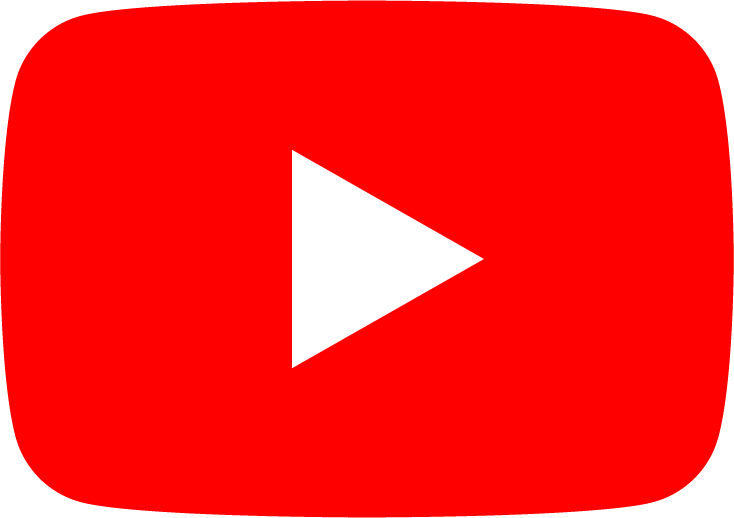

 青森県庁ホームページ
青森県庁ホームページ 青森市ホームページ
青森市ホームページ