
移住促進の取組についての質問
目次
移住促進の取組について

今日12月5日はモーツァルトの命日なんだそうです。
モーツァルトは生涯に13回ぐらい引っ越ししたらしいんですね。
というわけでということではないんですけれども、移住促進の取組について質問したいと思います。
議会でも移住の話、本当によくいろんな議員の方々から、この委員会とかでもよく出ていたかなと思うんですけれども、もう少し具体的な取組とか中身を聞いていきたいと思います。
【質問①】青森暮らしサポートセンターにおける相談体制と主な相談内容について伺いたい。
移住を促進するために、相談される方にきちんと対応していかないといけない。
相談体制がどうなっているのか、相談された内容に関して相談員がきちんと対応できているのか、そういったことなども含めて確認したいんですけれども。
まず、青森暮らしサポートセンターにおける相談体制と主な相談内容についてお聞きします。
回答:野田若者定着還流促進課長
- 青森暮らしサポートセンターでは、移住相談員1名、就職相談員1名の計2名が仕事や暮らしなど移住に関する相談に対応しております。
- 同センターにおける令和5年度の相談件数は2,392件となっており、主な相談内容としては、就職や起業など仕事に関する相談が最も多く1,840件で、これに次いで、住まいなど暮らしに関する相談が552件となっております。
【質問②】移住を促進するためには、仕事に関する情報提供が重要と考えるが、県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」における移住支援金の対象求人件数について伺いたい。
令和5年に県の取組を介して移住が決まった方が確か109人だったと思うんですけれども。
相談件数が2,400件ぐらいだということで、結構な相談件数だなと思います。
さらにここからつながっていけばいいなと思います。
そして、相談内容では就職だったり起業に関することが1,800件ぐらいだと。
中身としては仕事に関する相談が多い傾向ということで、仕事に関する情報提供というのが重要になってくると思います。
結局、青森県に移住するとなったときに、青森県で暮らしていくために、そこで何の仕事をするのか、そこはやっぱりきちんと考えないといけない。
移住支援金などもあるわけですけれども、こちらも十分に活用されているのかというのもあるわけです。
そこで、移住を促進するために仕事に関する情報提供は重要ですが、県の公式就職情報サイト「あおもりジョブ」における移住支援金の対象求人件数をお聞きします。
回答:野田若者定着還流促進課長
- 県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」に登録されている求人件数は、11月末現在で841件で、このうち移住支援金の対象求人件数は386件となっております。
【質問③】移住支援金の利用を促進するためには、移住支援金の対象求人を増やす必要があると考えるが、その登録手続きと登録の促進に向けた県の取組について伺いたい。
登録の求人数ももっともっと増えていってもいいのかなと思います。
県のホームページでは、商業の事業所1万2,646、工業関係の事業所1,500、全部で1万4,000ぐらいあるわけで、この全てが登録するというのはもちろん難しいと思いますけれども、そもそもの求人の母体数が増えていかないといけないかなと思います。
このあおもりジョブに登録するのは難しい手続だったりするんですか、そちらを確認したいと思います。
回答:野田若者定着還流促進課長
- 県公式就職情報サイト「あおもりジョブ」において、企業が求人登録をする際には、求人を登録する企業が県から割り当てられたIDでログインすることによりまして、求人情報や企業情報をオンラインで入力できるような方法となっております。
IDさえもらえば、あとは自分たちで入力できるということで、そこまで煩雑なものでもないと思うんです。
だから、より企業に登録してもらうことも重要だと思いますし、その中で移住支援金の対象になる企業も増やしていかないといけない。
現時点では400件弱ですか。
やっぱりいろんな業種があって、そして企業数もあって、その中で選んでいけたほうがいいので。
そこで、移住支援金の利用を促進していくために、移住支援金の対象企業を増やす必要があると思います。
その登録手続と登録の促進に向けた県の取組をお聞きします。
回答:野田若者定着還流促進課長
- 移住支援金の対象となる求人を登録するためには、中小企業であることなど国が定める要件を満たしていることについて記載した登録申請書と求人票を県に提出し、確認を受ける必要があります。
- 移住支援金の対象求人を増やすことにつきましては、県内企業の人材確保にもつながることから、
- 県では、ハローワークなどの求人情報から未登録企業をリストアップして個別に登録を働きかけるとともに、
- 市町村商工担当課長及び商工団体事務局長会議で県内企業への周知を呼びかけるなど、市町村や関係機関と連携しながら、移住支援金の対象となる求人登録の促進に引き続き積極的に取り組んでいきたいと考えております。
私がとある人から聞いた話だと、移住が決まって、青森県内の企業に就職すると。
その企業が移住支援金の対象企業に登録されていなかったみたいなんですね。
この企業に就職するという話が決まった後に、登録されてないとなって、それから移住支援金に関する申請をして、支援金をもらう形になった、そういった方もいたらしいんですよ。
これはこれで適用されたからよかったんですけれども、もともと適用される企業の条件というのも週20時間以上で無期雇用ということで。
今現在、移住支援金の対象として登録していない企業でも、対象になる企業は結構あると思うんですね。
引き続き粘り強く登録促進を進めていっていただきたいと思います。
【質問④】移住を促進するためには、住まいに関する情報提供も重要と考えるが、Uターン者に限らず、Iターン者など青森県に土地勘がない相談者に対して、どのように対応しているのか伺いたい。
そして、最初に質問した相談件数、内容の中で、住まいなど暮らしに関する相談も500件ほどあるということで。
移住するに当たって、仕事のほかに住まいというのも重要になってくるわけです。
資料を頂きましたけれども、移住件数が109件あったうち、青森市、弘前市、八戸市で69人。
これは人数として結構多いという中で、ほかの地域もいたりするわけですけれども。
青森県内いろんな地域の特性があるわけです。
気候であったり、環境であったり、文化的なものであったり。
Uターンとかならまだともかく、Iターンされる方ももちろんいるわけです。
こちらも資料を見ると、完全に何も青森県とゆかりのない方のIターンというのが2割ぐらいいると。
そういった中で、土地勘とかそういうのも分からない、そうなると、住まいというのもどこがいいんだろうと。
青森市と八戸市だけをみても、八戸市は雪がない、青森市は雪がある。
交通の部分とかでも青森市と下北で差があります。
移住を考えている方はそういったことを十分知らないといけない、相談員の方が伝えていかないといけない。
移住を促進するために、住まいに関する情報提供も重要と考えますが、Uターン者に限らず、Iターン者など青森県に土地勘がない相談者に対して、どのように対応しているのか伺いたいと思います。
回答:野田若者定着還流促進課長
- Iターン者など青森県に土地勘がない相談者につきましては、青森県から遠い地域に住んでいるため、何度も下見に来ることが難しい方もいらっしゃることから、より丁寧な対応が必要になります。
- このため、青森暮らしサポートセンターにおきましては、相談者の希望を踏まえた上で、
- 住まいにつきましては、周辺環境をはじめ、職場までの通勤方法や買物の利便性など幅広い情報を提供するとともに、
- 相談者が子育て世帯の場合には、保育園や学校などの立地環境も併せて提供するなど、きめ細かく対応しているところです。
- 県といたしましては、引き続き相談者の目線に立った対応を行うことで、一人でも多くの移住につなげていきます。
今の時代ですと、ネットとかで物件の情報も写真とかもついていて、いろいろ見れたりするわけです。
どういった物件なのかなというのが何となく分かったりするんですけれども、やっぱり周辺の場所というか地域、条件であったり、環境というのはなかなか分からないですから。
相談員の方が今2名ということで、ここももう少しいてもいいんじゃないのかなと思いますけれども、きちんと相談者に対して親身になって対応してもらえればと思います。
それと、こども・子育て「青森モデル」のほうにもありますけれども、市町村に期待する県と連携した主な取組「若者定住促進住宅等の提供」など、今、青森県内の各市町村でいろんな取組を独自でやられていると思うんです。
この委員会でも大鰐町に行って取組を見たりもしましたけれども、各市町村の取組も実はいろいろやっているのに、なかなか知られていないというのもあったりすると思います。
青森県内の各市町村では移住に関するこういった取組をさらにしているんだよというのを、例えば県のホームページなどにもきちんとまとめる形でアクセスしやすいようにしていけばいかがでしょうか。
移住を考えていくときに、具体的に青森県内のどこかの市町村に住むわけですから、移住する方の参考になると思います。
そういった部分も含めまして、引き続き移住促進に向けて取り組んでいただければと思います。
以上で質問を終わります。

ご意見・ご感想など
あなたの声を聞かせてください。










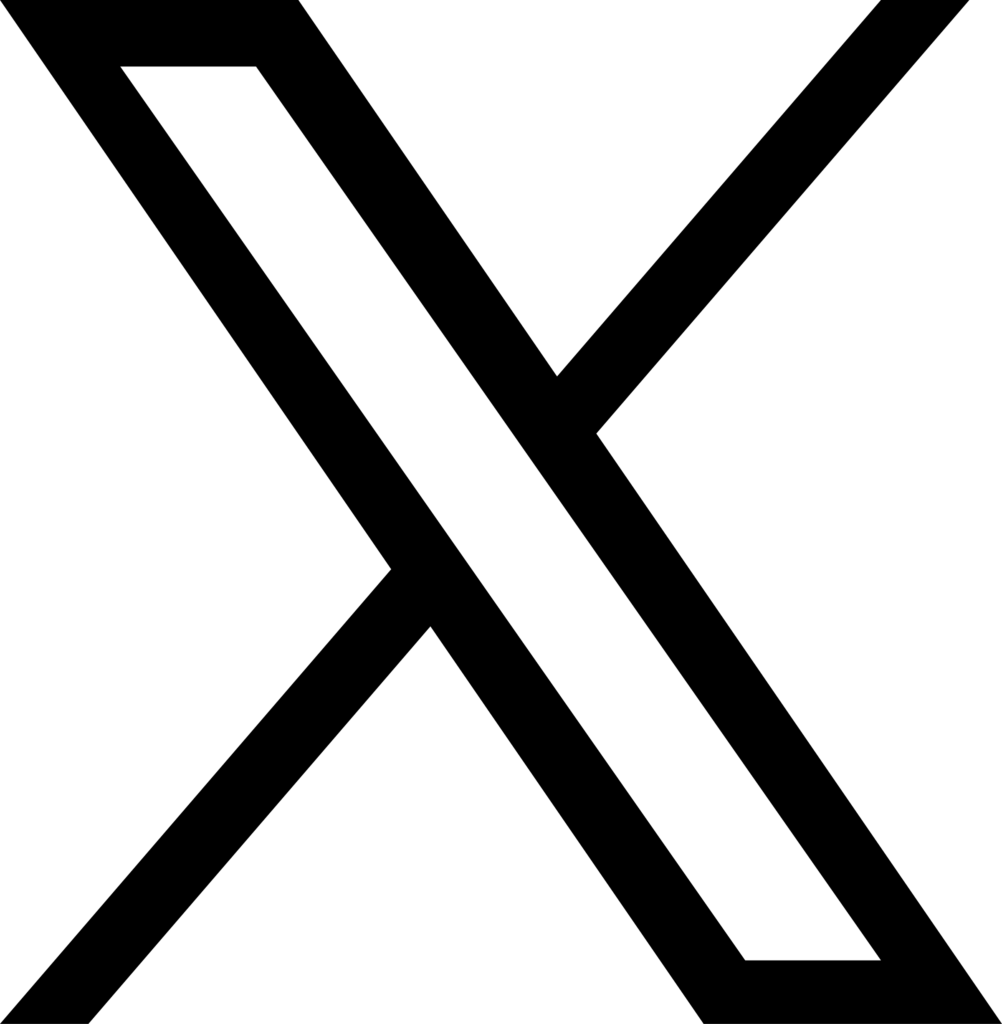
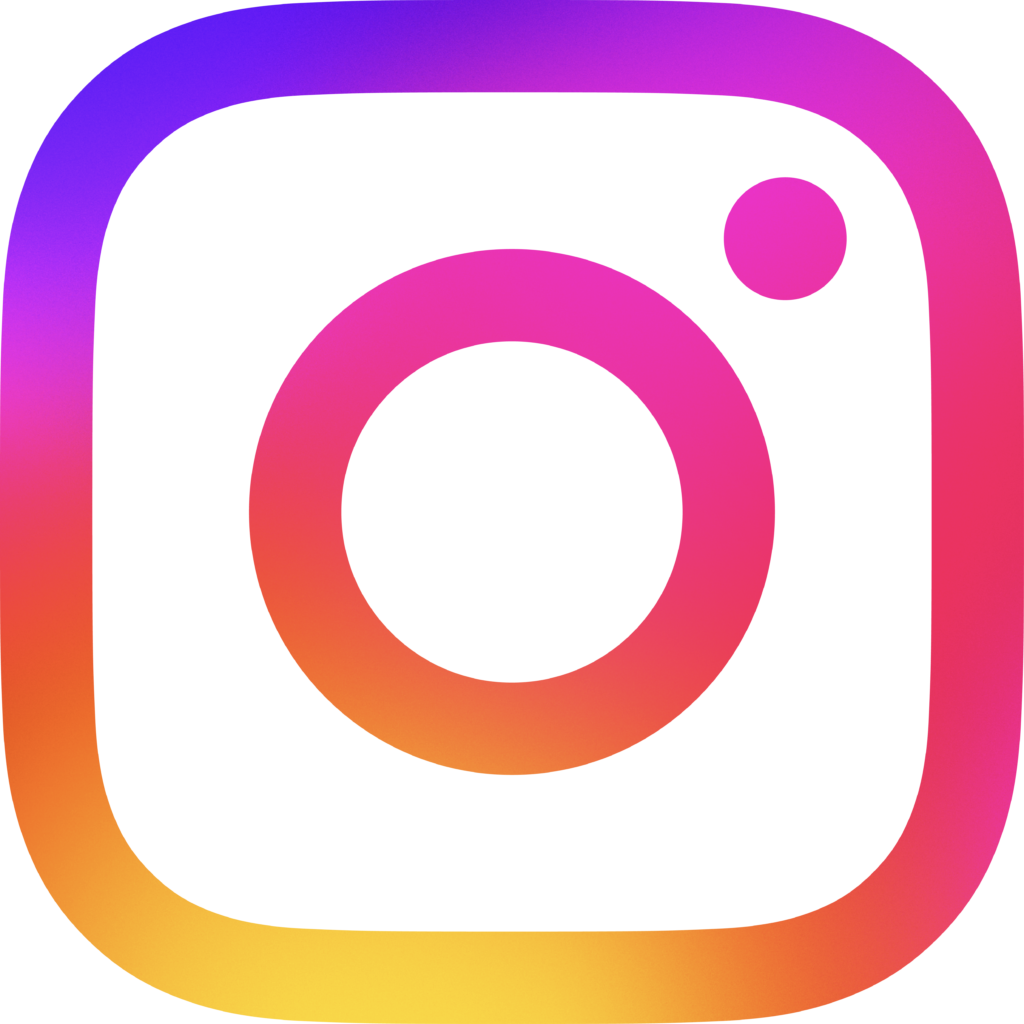

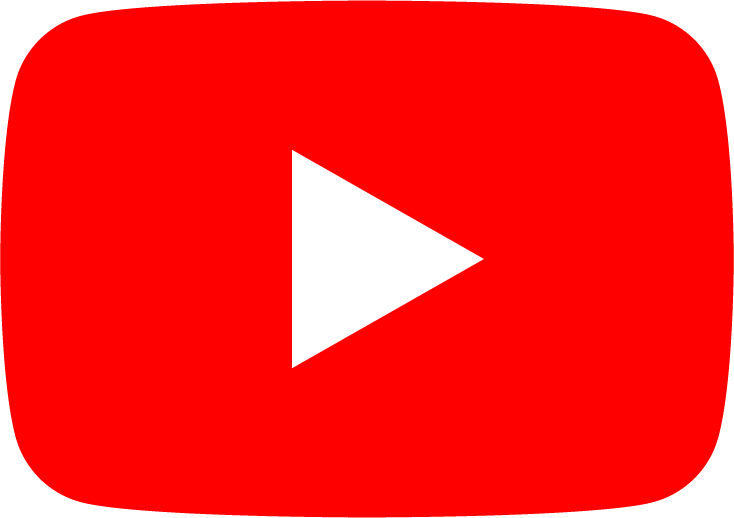

 青森県庁ホームページ
青森県庁ホームページ 青森市ホームページ
青森市ホームページ