
こどもの生活・学習支援事業についての質問
目次
こどもの生活・学習支援事業について

私は子供の学習支援に関して質問していきたいと思います。
先週、自主夜間中学が青森市に開設されました。
今まで東北のほうでもなかなか夜間中学というのは、特に北東北では公立も自主夜間中学も含めてずっとなかったんです。
それが自主夜間中学ということで先週設立されて、昨日、早速、生徒さんが1人来たんです。
私もちょっと関わらせていただいて、吉俣委員も一緒にやっているんですけれども、まずはたった1人だったんです。
分数が分からない。
年配の方なんですけれども、2分の1足す3分の1はみたいなところから始まっていきながら、何でこうなるのかみたいなこととかをやったりしながら。
終わってみんなでけんちん汁を作って食べました。
スタッフの人とか、講師の方であったりとか、受講された生徒さんと一緒に和気あいあい食べながらやったんですけれども。
教える場でありながら、和気あいあいとしながら、みんながつながっていく、そういった場でもあって。
【質問①】こどもの学習支援に関する県の取組について伺いたい。
今は自主夜間中学の話をしましたが、学習支援というのは行政的な定義というのはもちろんあるんでしょうけれども、学習以上の意味を持つ、ただ教える場だけではなくて、みんながつながっていけるような、それがコミュニティーになったり、社会的排除にも対応していけるような、そういった場でもあると思うんです。
そうした中で、県でも学習支援の場というのを取り組んでいらっしゃると思うんですけれども、県では子供の学習支援に関してどういうふうに取り組んでいるのか確認したいと思います。
回答:和田こどもみらい課長
- 県では、町村部の生活困窮世帯の小学4年生から中学3年生を対象に、6月から2月までの期間、月2回または3回、公民館などの施設において無料の学習講習会を開催しています。
- 令和6年度の開催状況は、令和6年10月末現在、27町村において133人の子供から申込みがあり、講習会を275回開催し、延べ877人が参加しています。
- また、ひとり親家庭等の子供への学習支援を実施する市に対し、事業費の一部を補助しており、令和6年度は十和田市が補助を活用して、月3回程度、学習支援を実施しています。
- なお、このほか、市町村においては、国や県の補助に関わらず、独自に学習支援の取組を行っているところです。
【質問②】こどもの学習支援の実施場所を増やしていくべきと考えるが県の見解について伺いたい。
延べ877名と、本当に多くの子供たちが参加されています。
学習会の参加者は子供に限らずということであると思うんですけれども、これからもどんどんそういった場が必要とされていくと思うんです。
先ほども話しましたけれども、学習支援というのがいわゆる学習塾みたいな形で教えるだけではない、そこで悩みを相談することもあるでしょうし、勉強に限らず様々な話ができる。
空間を共有しながら、何か困ったときに相談する、踏ん張れる、そういった場につながっていくと思うんです。
そういった学習支援の場というのがいわゆる居場所であったり、居場所って本当にいろんな概念があるんですけれども、たまり場って言ったほうがいいのかな、そういった場というのを増やしていく。
学習支援というのが学ぶというところとも密接につながって、そこから広がっていくということが多いので、それは増やしていくべきで。
学習としての意味もそうですし、つながりの場、たまり場というところでも学習支援というのが重要になってくると思います。
県でも増やしていくような施策をしていくべきだと考えますけれども、今、県ではどのように考えていますでしょうか。
回答:和田こどもみらい課長
- 子供の学習支援は、子供たちの学習の機会を確保し、学習する習慣の定着を図るとともに、子供たちが安心して過ごせる居場所として重要な役割を担っていることから、学習支援の実施場所を増やしていくことが重要であると認識しています。
- 県としては、引き続き市町村に対して、県や国の補助事業を活用した取組のほか、独自の取組を含めた学習支援の実施を促していきたいと考えています。
【質問③】県として、こどもの学習支援に更に取り組むべきと考えるが、県の見解について伺いたい。
先ほど、ひとり親家庭等の生活向上事業に関しては十和田市に1つということでした。
もちろん、市のほうで独自にやっていらっしゃるということもあると思いますけれども、ぜひこちらを広げていけるように、県でもより周知であったり、市町村に対してバックアップしていただきたいんです。
社会的に排除されてしまうというのが結構深刻な問題です。
例えばシングルマザーの家庭があったとして、日中も夜もアルバイトを掛け持ちしている。
仕事で疲れてしまい、子供をなかなか見ることもできなくて、勉強とかもなかなか見てあげられない。
朝も起こしてあげられず、子供の遅刻が増えてしまう。
勉強についていけなくなったりして、不登校になってしまう。
結構、典型的なケースだと思うんです。
このように親がなかなか見てあげられないときもケアの場になっていく。
そういった意味で、学習支援の場というのは本当に重要になってくると思います。
一例なんですけれども、沖縄県のほうで、高校生であったり、小学生、中学生に対する無料塾に対して支援しているそうなんです。
学習塾に通う子に対して支援をしていくみたいな、補助を出したりしていくというのがあるんですけれども、学力の問題というのが本当に大きくある。
生活に困窮されている家庭というのが学力的な部分で上がっていかないということもありますし、そういったバックアップにもなっていく。
沖縄県としての一例ですけれども、いろんな市区町村でも無料塾みたいなものも広がっているんですね。
この無料塾というのは、ただ勉強する場ではなくて、いろんな相談ができるような場ということで、やっぱりそういった広がりというのが出てきていると思うんですけれども。
場所の提供もそうですし、中身に関しても、県に、より取り組んでいただきたいんです。
県として、子供の学習支援にさらに取り組んでいっていただきたいんですけれども、県ではどのように考えているのか伺いたいと思います。
回答:和田こどもみらい課長
- こども家庭庁の「こどもの居場所づくりに関する指針」においては、
- 市町村には管内の状況把握等を行いつつ、関係者と連携してこどもの居場所づくりを推進すること、
- 都道府県には市町村の取組を支えるとともに、管内の市町村間や都道府県間の連携を図りつつ、広域的なこどもの居場所づくりの環境整備を行うことが求められています。
- こうした中、県内の各市町村では、学習支援について、ひとり親家庭の子供向け、生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子供向け及びこれらを含む全世帯の子供向けなど、それぞれの家庭の事情等に応じた事業を実施しているところです。
- 県としては、こうした学習支援を含めたこどもの居場所づくりを支援するため、広域的なネットワーク会議の開催による関係者の連携体制の構築等に引き続き取り組んでいきます。
学習支援は、こどもの居場所の話なんです。
どうしても行政などで学習支援の話となると、生活困窮とか、そういった話が多くなってしまうんですけれども、それだけでもない。
いろいろな経済事情がある中で、指導してくれる方や関係者の方が集まって、つながりが増えて、ネットワークになっていくと思うんです。
一部のコミュニティーだけで固まってしまうのではなくて、いろいろな立場の人がつながりながら、こういう現状なんだというのもそこで分かることもあるでしょうし、今、答弁もありましたけれども、ネットワークをつくっていくというのが非常に大事になってくると思います。
いろいろなやり方があると思うんです。
今、実際にいろんなことをやられている方、県内にもいらっしゃったりすると思うので、そこをきちんと結びつけて、広くネットワークをつくれるように、県で頑張っていただければと思います。
終わります。

ご意見・ご感想など
あなたの声を聞かせてください。










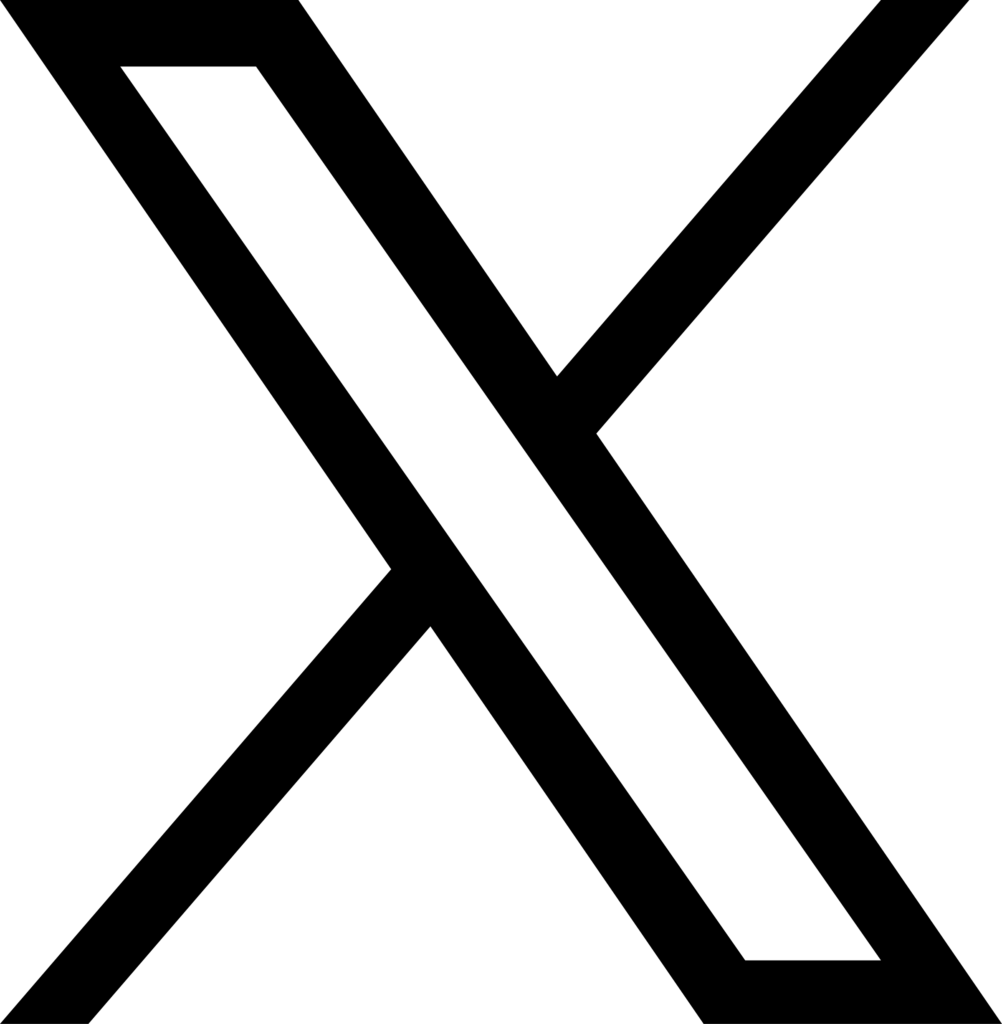
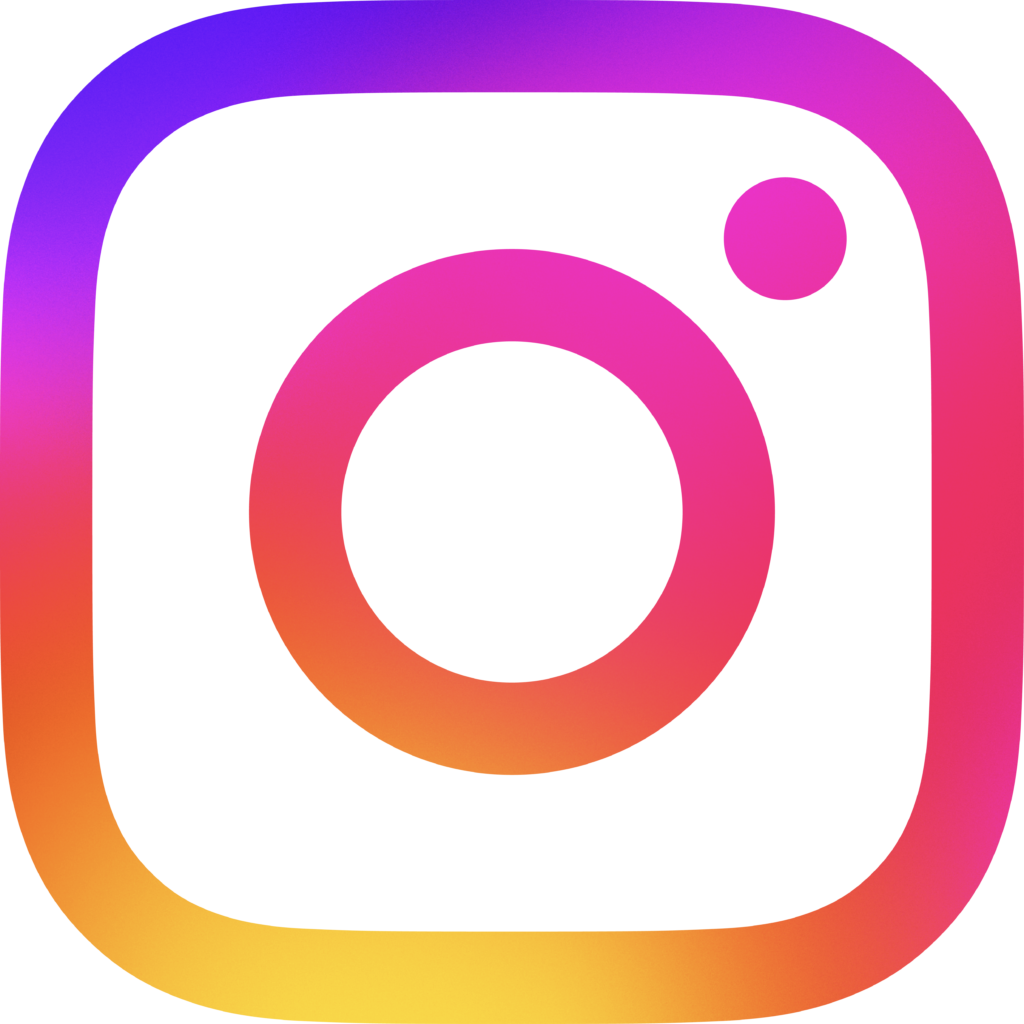

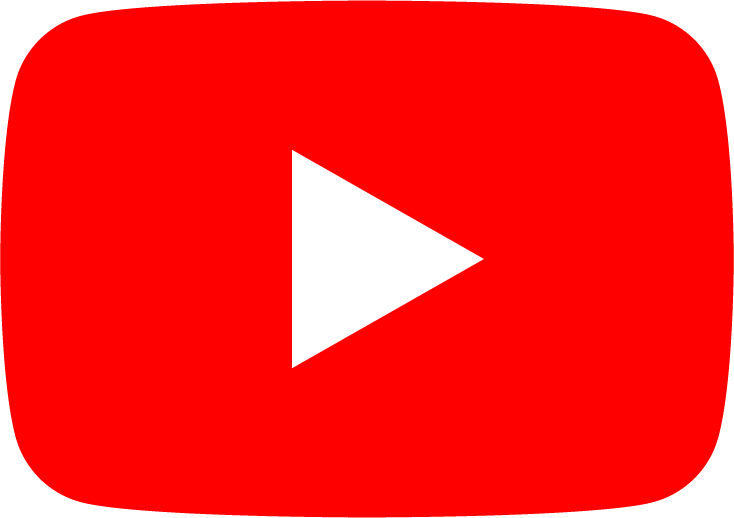

 青森県庁ホームページ
青森県庁ホームページ 青森市ホームページ
青森市ホームページ