
議案第32号青森県児童福祉法施行条例の一部を改正する条例案一時保護等についての質問
目次
議案第32号青森県児童福祉法施行条例の一部を改正する条例案一時保護について

新政未来の小笠原です。
総務政策こども委員会の今年度最後の常任委員会となります。どうぞよろしくお願いいたします。
【質問①】県内の児童相談所が行った一時保護について、令和元年度以降の件数の推移を伺いたい。
私は付託案件に関して、議案第32号「青森県児童福祉法施行条例の一部を改正する条例案」の一時保護について、少し詳しく聞いていきたいと思います。
まず、青森県内で児童相談所が行った一時保護に関して、令和元年度以降の件数の推移というのはどうなっているのか伺いたいと思います。
回答:和田こどもみらい課長
- 県内の児童相談所が行った一時保護の件数は、令和元年度が324件、令和2年度が308件、令和3年度が328件、令和4年度が327件、令和5年度が474件となっており、児童虐待相談対応件数が増加していることもあり、一時保護の件数も増加しています。
- このうち、一時保護所を含む児童相談所内で行った一時保護の件数は、令和元年度が125件、令和2年度が108件、令和3年度が117件、令和4年度が82件、令和5年度が106件となっております。
令和5年度が474件で、前年よりも150件近く増えているということでした。そして、一時保護所では100件ちょっとということですけれども、それ以外は、いわゆる保護委託されているところで一時保護されているという認識でよろしいのでしょうか。
回答:和田こどもみらい課長
- 474件から児童相談所内で行った106件を差し引きますと368件となります。こちらについては、児童養護施設や里親への委託一時保護となります。
【質問②】一時保護を解除されたこどもの状況について、令和5年度の実績を伺いたい。
相当な件数があるということでした。
次に、一時保護されたけれども、大丈夫だろうと判断された、解除された子供の状況に関して、令和5年度の実績を伺いたいと思います。
回答:和田こどもみらい課長
- 一時保護の解除は、児童相談所による一時保護の期間中に、保護者や子供との面接、関係機関等への調査を行った上で、一時保護解除後の家庭引取りや児童養護施設等への入所措置などを含め、決定しています。
- 令和5年度に行った一時保護は474件であり、解除後の対応は、家庭引取りが230件、児童養護施設等への入所措置が78件、里親委託が22件、他の児童相談所への移送が15件、家庭裁判所送致が1件、その他が128件となっています。
その他が128件とあったんですが、その他というのはどういった事例なのでしょうか、答えられる範囲でお聞きしたいと思います。
回答:和田こどもみらい課長
- 例えば、里親等への委託一時保護から中央児童相談所の一時保護所への移送がありますけれども、様々ありまして、これが多いというようなことはなかなかお答えできない状況でございます。
【質問③】児童虐待を受けたこどもの一時保護に至るまでの児童相談所の対応の流れについて伺いたい。
様々なケースがあるということでした。
児童虐待を受けた子供が一時保護に至るまでの児童相談所の対応の流れを確認したいと思います。
回答:和田こどもみらい課長
- 児童相談所では、児童虐待通告を受理した後、原則として48時間以内に子供の安全確認を行うとともに、子供や家庭環境等に関する調査を行います。
- その後、所内の会議において、一時保護決定に向けてのアセスメントシートを活用してリスクを客観的に把握し、リスクが高いと判断される場合に、児童相談所長の判断で一時保護を行います。
最終的には児童相談所の所長が決定するという認識でよろしいのでしょうか。
回答:和田こどもみらい課長
- 児童福祉法では、児童相談所長が必要があると認めるときは児童の一時保護を行うこととされておりますので、児童相談所長の判断で一時保護が行われています。
【質問④】児童相談所が一時保護を行う際の基準について伺いたい。
最終的な判断は所長ということで、誠に重い判断、本当に的確な判断が求められると思います。
もちろん、勝手に判断するわけではなく、周りの職員の方であったり、状況を見たりしながら判断することではありますけれども。
次に、児童相談所が一時保護を行う際の基準、何をもってこれは一時保護しなければならない、そういった基準をどういうふうに設定しているのか、その基準について確認したいと思います。
回答:和田こどもみらい課長
- 一時保護は、児童相談所長が必要と認める場合に行うことができるとされており、その必要性の判断においては、できる限り客観的かつ合理的な判断をしなければならないとされています。
- そのため、児童相談所では、子供の一時保護の必要性をできるだけ客観的に判断するために、一時保護決定に向けてのアセスメントシートを活用しています。
- 本シートは、リスク度判定のための客観的な尺度であり、当事者が保護を求めているか、既に虐待により重大な結果が生じているか、次に何か起これば重大な結果が生ずる可能性が高いか、虐待が繰り返される可能性が高いかなどの8項目について情報を整理し、所内の会議において総合的に検討し、一時保護の要否を判断しています。
アセスメントシートなどを使いながら客観的に判断されているということですね。
年々、特に令和5年度は増えており、令和6年度はこれから発表になると思うんですけれども、やっぱり相談件数なども増えていくと思うんです。
そして、委託保護をするケースも今後増えていく可能性もある。
あまり劇的に下がるということはないのかなとも思います。
一時保護が必要とされている子供が保護に至るように、そして保護された後も十分にケアしていただければと思います。
所管事項ではこれに関連して八戸市の案件などもお話ししたいと思いますけれども、子供たちの命を守るのは、やっぱり大人たちの責務だと思います。
自分たちではどうしようもならない、子供というのは本当に限られた力しかなくて、大人の言うことを聞くしかないというのもあって、なかなか逃れられないんですよ。
自分たちではなかなか逃れることができない。そうなったときにどう助けてあげるのか、本当に考えていかないといけない問題だと思います。
今後も一時保護施設の整備なども含めて対応していただければと思います。
私からは以上です。
固定的性別役割分担意識の解消に向けた男性の家事参画の促進について
それでは、所管事項に関して質問していこうと思います。
まず、1つ目、固定的性別役割分担意識の解消に向けた男性の家事参画の促進についての質問です。
3月8日は国際女性デーです。
女性の地位向上、女性差別を払拭していこうと、それを世界で確認して、女性の権利を高めていこう、差別をなくしていこう、そういった日であるんです。
この日にとある講演があって、私も講師の方の話をいろいろ聞きながら、昔に比べればよくはなったのかもしれないですけれども、まだまだ男女の差というのはあると思うんです。
例えば政治の分野においても、青森県内、女性の議員がいない市町村が40市町村のうち12ですか。
それでどうやって女性の声を反映させていくのか。
職員やもろもろの委員で女性が増えているというのはあったりすると思うんですけれども、議員で女性がいないとなると、女性の声がなかなか届きづらいですよね。
男性はこうだ、女性はこうだという意識が根強い。
それが仕事と結びついているわけです。
その根強さというのが、男性もしくは夫は外で働いて、女性もしくは妻は家庭を守るべきだと。
これがいわゆる固定的性別役割分担意識になってしまうんです。
呼び方に関してもそうですよね。
例えば女性であれば、嫁、家内、奥さん。男性だと主人、主というので、ずっとそういうのが続いてきた。
そうした中で、男性がより家事をしていかないといけないのに、結局、男性は外で働いて、女性にばっかり家事を任せる。
最近は意識が高まっていると思うんですけれども、それでも、男性側が「やってあげているんだよ」とかではなくて、それが当たり前になってくるように。
男だろうが、女だろうが関係なく、普通に外の仕事は外の仕事、家の仕事は家の仕事、やるべきことはやるべきことというので当たり前にやっていくようにならないといけないと思うんです。
【質問①】今年度の取組状況について伺いたい。
そうした中で、青森県でも男性が家事に参画していくようにいろいろ取り組んでいらっしゃると思うんですけれども、今年度はどういった取組をされていたのか伺いたいと思います。
回答:沼田県民活躍推進課長
- 県では、今年度、家事等に対する家庭内での性別役割分担意識の解消に向け、日常生活に必要不可欠な掃除や洗濯、買物といった家事を男性がすることについて抵抗感をなくすことを目的に、仕事と家庭のジェンダーギャップ解消事業を実施しました。
- 具体的には、県内のスーパーなど124店舗で、掃除用品等のコーナーに12月から3か月間、男性が家事をする日を意味する「カジダンデー」と表記したポスターやのぼりなどを掲示する意識啓発を行いました。
- また、大手日用品メーカーとタイアップし、県内2地域のショッピングセンターで、1月と2月に毎日の家事を簡単にする家事用品体験ブースを設置する啓発イベントを実施し、家族連れの方など約330名の来場がありました。
今、ご説明の中で男性が家事をする日というのがありましたけれども、家事をする日、しない日というのがよく分からないです。
忙しくてできないとかであれば、まだ分かるんですけれども、する日、しない日というのが何かよく分からないわけです。
啓発するために、あえて「カジダン」という言葉を使っていらっしゃると思うんですけれども、本来であれば、「カジダン」という言葉もなくなっていく、イクメンとかいろいろあったりしますけれども、そういった男性を強調しなくても当たり前になっていくというのが望ましいと思っています。
【質問②】今後の取組内容について伺いたい。
今、そういったことに取り組まれているということですけれども、来年度以降、より男性が家事参画していくように、どういったことに取り組んでいくのか、今後の取組内容を確認したいと思います。
回答:沼田県民活躍推進課長
- 性別にかかわらず、個性と能力を発揮できる男女共同参画を実現するためには、固定的性別役割分担意識の解消が重要であると考えています。
- そのため、来年度は、引き続き固定的性別役割分担の解消に向けて、男性の家事参画についての意識を高めるための啓発イベントを開催します。
- 加えまして、家事を効率化し、家事時間そのものを減らす取組も必要であることから、家事代行サービスを利用した家事のアウトソーシングを普及啓発するための冊子を作成しまして、周知を図っていきたいと考えております。
普及啓発はぜひ頑張って続けていってほしいと思うんです。
若い人の間だと、抵抗がなくというか、割と当たり前になってきているのかなと思うんですけれども。
年齢が上がっていくにつれて、いわゆる亭主関白的な考えというのがまだあるんです。
私は今、30代ですけれども、30代でも若干いたりします。
今、若い人はいろいろ啓発されていたり、学習されていたりしていると思います。
より年配の方とか、配偶者がある方にどうやって啓発していくのか、そこが重要になってくると思います。
女性が抑圧され我慢させられてきたということがずっと続いてきて、だんだんよくなってきている。
家事に関しても自分たち家族だけでやるのではなくて、社会に任せられることは任せていいじゃないか、そういった意識を生んでいくことが必要だと思うんです。
例えば、子供が生まれたりすると、仕事があって、家事、育児、本当にいろいろ大変になってくる。
そういった中で、子供もそうですし、家事、家庭のこととかも社会に任せられることは任せていいんだと。
それが野放図にやったり、ないがしろにしたりしたら駄目ですけれども。
安心して任せてもいいんだという社会を目指していくためにも、今、アウトソーシングの話がありましたが、こういうのがあるんだと、ちゅうちょせずに県民の方がすぐ使えるように周知などもしていっていただければと。
業者の方といろいろ話をしながら、アウトソーシング、家事を代行してもらうということを進めていただければと思います。
八戸市における児童虐待死亡事例検証報告書について
次の質問に移りたいと思います。
【質問①】検証報告書では、八戸児童相談所の対応にどのような問題点・課題があるとされたのか伺いたい。
先ほど菊池副委員長からもお話がありましたけれども、私も八戸市における児童虐待死亡事例の検証報告書について質問しようと思います。
私もこの検証報告書を見ました。
結構赤裸々というか細かく書いてあって、本当に心が締めつけられるような内容も書いてあったりするんですけれども・・・
改めて、検証報告書では、八戸児童相談所の対応について、どのような問題点、課題があるとされたのか伺いたいと思います。
回答:和田こどもみらい課長
- 検証報告書では、八戸児童相談所の対応に関する問題点、課題として、
- 1回目の虐待通告では、内夫の父母から女児が元気に生活しているという情報により、2回目の虐待通告では、警察が女児に傷、あざがないことを目視確認していたことにより、児童相談所が女児を直接目視確認していなかったこと。
- また、本世帯が令和5年10月にアパートに転居したことによるリスクを考慮し、本世帯への対応方針や指導終結の判断を慎重に行う必要があったこと。
- また、令和5年11月30日の指導終結の前に、母が本当に育児に困っていないか、指導したことが守られているかを面接により確認すべきであったこと。
- また、母の養育能力に関する評価を適切に行い、具体的な支援を行う必要があったほか、
- 指導を終結する際に八戸市への連絡を確実に行うべきであったことなどが指摘されています。
改めて課題として見えてきたことがあると思うんです。
先ほど一時保護に関する質問を付託でしましたけれども、本来であれば、アセスメントシートも使って評価していくということであったんですが、今回の件は、アセスメントシートも使われていなかった。
これがあれば大丈夫とか防げるとかではないと思うんですけれども、細かいところから客観的に評価するためにシートがあるわけで、こういうところなんだと思っております。
【質問②】検証報告書では、本事例の再発防止に向けてどのような提言がされているのか伺いたい。
次に、検証報告書は、本事例の再発防止に向けてどのような提言がされているのでしょうか。
回答:和田こどもみらい課長
- 検証報告書では、本事例の再発防止に向けた対応として、
- 子供に会えなかった場合の対応について、児童虐待防止法に基づく出頭要求、立入調査、臨検捜索の活用も含め、子供の安全確認のための対応を最優先かつ速やかに行うこと。
- 虐待のリスク判断は、虐待通告時の状況、情報のみで判断することなく、事例の経過や状況の変化に応じて、その都度、必要な調査を行い、アセスメントを行った上で対応方針を検討すること。
- 虐待相談対応の終結は、虐待に至るリスクが低下し、児童相談所が関与する必要性がなくなったことを組織で確認した上で終結する必要があり、不足している指導や支援がないか、児童相談所の関わりがなくなることで懸念される状況がないかを多角的に協議した上で終結の判断を行うこと。
- 児童相談所の指導終結に当たり、市町村との情報共有や市町村の支援が適当と判断する場合は、市町村に対して、支援が適当と判断した理由と支援を求める内容を確実に伝達し、市町村の了承を得ることなどがありました。
- また、県への要望として、児童福祉司と児童心理司の適正配置、児童福祉司スーパーバイザーの専門性の向上、児童相談所の業務効率化、児童虐待に関する周知啓発などが提言されております。
【質問③】県では、検証報告書の内容を踏まえ、児童虐待の防止に向けてどのように取り組んでいくのか伺いたい。
様々、具体的な提言がされているということですが、県では検証報告書の内容、提言を踏まえて、児童虐待の防止に向けてどのように取り組んでいくのでしょうか。
回答:和田こどもみらい課長
- 県では、児童虐待による死亡事例が二度と発生しないよう、児童虐待相談体制の強化に取り組むこととしています。
- 具体的には、児童相談所の業務効率化を進めるため、児童の一時保護に係る移送業務の外部委託やタブレットアプリを活用した相談記録の迅速な情報共有、
- 児童相談所職員の専門性向上を図るため、相談対応の実例の振り返り等によるケースマネジメント研修や職員の指導、教育を行うスーパーバイザー等を対象とした継続的な研修の実施、
- 児童相談所業務の質の向上を図るため、児童相談所第三者評価の受審と児童相談所運営指導の実施、
- 児童相談所職員を確保するため、学生向け児童相談所業務紹介リーフレットの作成や就職イベントへのブース出展、
- 市町村の相談体制を強化するため、こども家庭センターの設置促進や機能強化に向けた市町村への支援、児童虐待に関する通告義務や体罰によらない子育てに関する県民への周知啓発などを行います。
- また、児童虐待事案への対応に当たっては、県民から子育て世帯等において、ふだんの生活とは違う異変や違和感などを感じた場合、ちゅうちょなく、積極的に児童相談所、警察、市町村に連絡していただくことが重要であると考えており、県民からの情報提供の呼びかけを行っていきます。
【質問④】令和6年4月1日時点における児童相談所職員の配置数について伺いたい。
職員の質の向上もそうですし、児相の環境とか、もろもろのことを整えていかないといけない。
整えていくための今後の取組ということであると思います。
相談件数も年々増えていく中で、人員、マンパワーはどうしても必要になってくるんです。
人間一人でできることは限界があります。
どれだけ効率化しようと思ったって、環境をよくしようと思ったって、対応しないといけないものが増えるのであれば、どうしても限界がある。
そういった観点から質問していこうと思います。
令和6年4月1日時点における児童相談所職員の配置数に関して確認したいと思います。
回答:和田こどもみらい課長
- 県内の児童相談所には、所長、次長及び庶務担当職員を除き、令和6年4月1日時点で計101名の職員が配置されています。
- 内訳としては、児童福祉司が63名、児童心理司が28名、警察からの出向職員3名を含む相談員が10名となっています。
【質問⑤】令和7年度における児童相談所職員の配置基準について伺いたい。
昨年4月1日時点で101名ということで、ここからまた新しく採用される方々や辞めてしまう方々もいらっしゃるとは思うんですけれども、本来、どれぐらいいなければいけないのか。
いろいろ配置基準があると思うんですけれども、令和7年度における児童相談所職員の配置基準に関して伺いたいと思います。
令和6年4月1日時点の配置数から比較すると、どちらも20名ほど多くなければいけないということですけれども。
先日、人事なども公表されましたが、この配置基準というのは満たされる状況になるのでしょうか。
児相の職員の方がきちんと増員されたということになるのか、改めて確認したいと思います。
回答:和田こどもみらい課長
- 令和7年4月1日時点で、県内の児童相談所に配置される職員の数は、所長、次長及び庶務担当職員を除き109名となっており、令和6年4月1日時点の101名と比較して8名の増員となります。
- なお、現時点では、児童福祉司及び児童心理司として配置される職員の数が決まっていないため、それぞれについて、令和7年度の配置基準と直接比較することはできませんが、児童福祉司及び児童心理司の配置基準の合計125名に対しては、少なくとも16名不足することになります。
16名不足するということでしたが、その不足分に関してはどのように対応していくお考えなのか伺いたいと思います。
回答:和田こどもみらい課長
- 県では、児童福祉司と児童心理司を確保するため、令和6年度からリクルート関連企業と連携し、学生向け児童相談所業務紹介リーフレットの作成配布、リクルート専門サイトに本県の採用試験や職員の経験談等を掲載、リクルート関連会社が主催する就活イベントへのブース出展の取組を行ったほか、令和6年度中に児童相談所に任期付職員5名を採用するなど、職員の確保に努めています。
- 令和7年度においても、これらの活動等を通じて、引き続き児童相談所職員の確保に努めます。
101名から109名と少し増えましたが、本来なら足りていない状況ということ。専門性が求められるので、おいそれと集めることは難しいと思うんです。
人が足りなくて、対応し切れなくなってしまうことがあるんですよね。
子供たちの命に関わることですから、足りていない部分を何とか頑張って集めていただければと思うんです。
前に委員会で質問させていただいた意見表明等支援員のことです。
こちらは検討するというお話であったと思うんです。
子供の声をきちんと聞かないといけない、その中で意見表明等支援員というのが必要になってくると思うんですが、こちらの検討状況はいかがでしょうか。
回答:和田こどもみらい課長
- 意見表明等支援員については、現在、外部委託する方向で令和7年度当初予算案に必要な予算を計上しているところです。
本当に痛ましい事件だと思います。
防げたのではないか、本当にいろいろ思うことは多いんですけれども、二度とこういうことがないように、市と警察とも連携しながら防いでいっていただければと思います。
虐待される子供たち、児相に相談される子供たち、少しでもその件数を少なくしていかないといけないですし、様々な福祉の分野とも連携しながら、痛めつけられてしまう子供たちを減らしていっていただければなと思います。
以上で質問を終わります。

ご意見・ご感想など
あなたの声を聞かせてください。










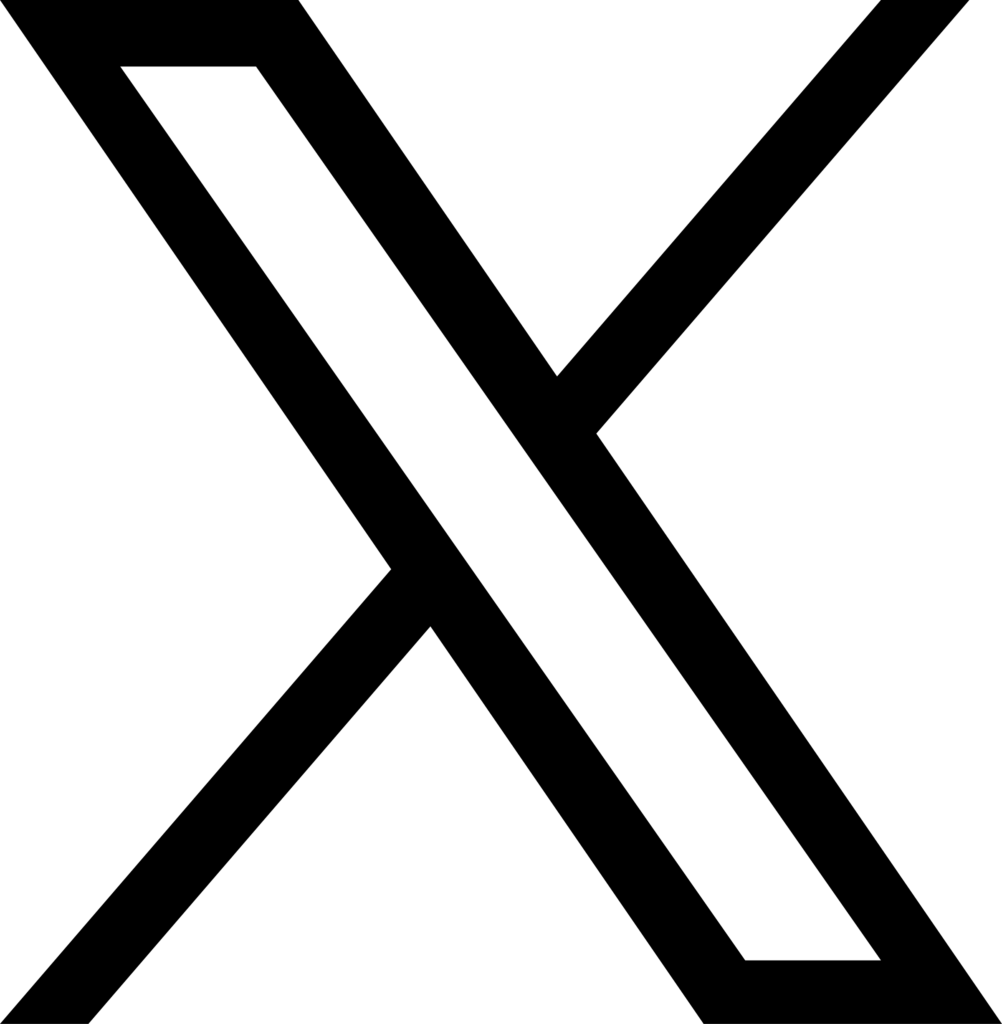
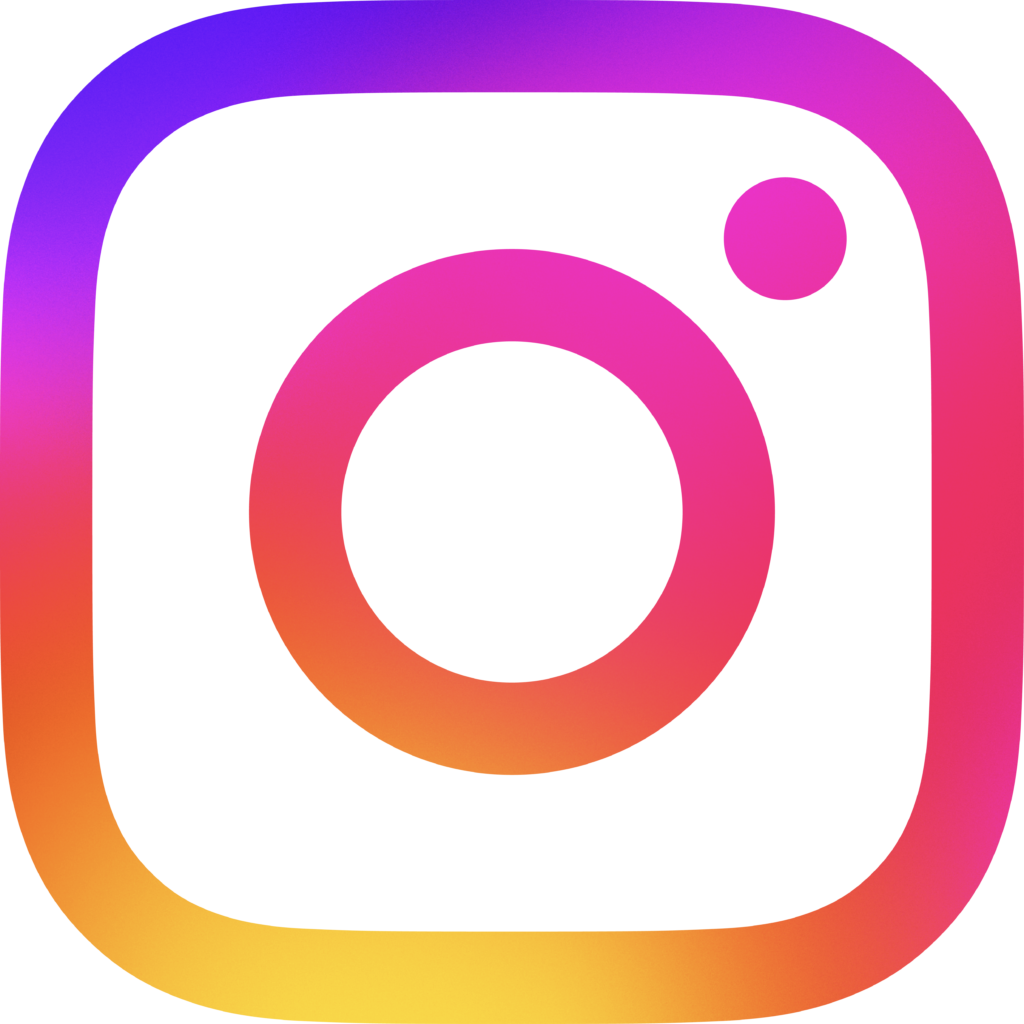

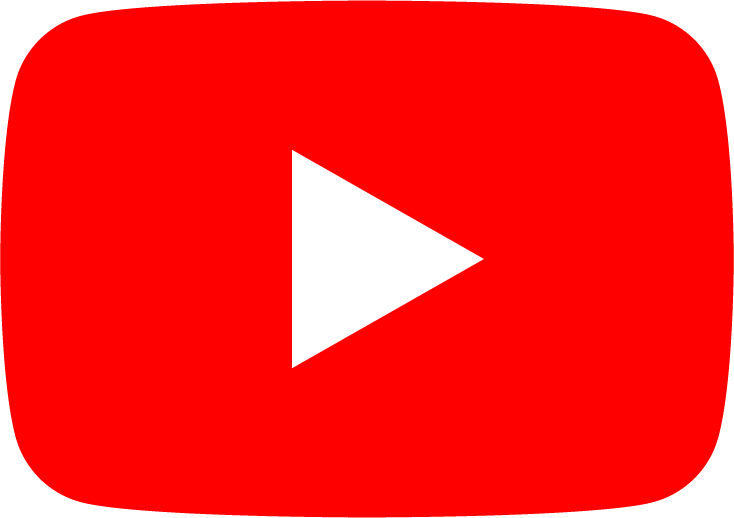

 青森県庁ホームページ
青森県庁ホームページ 青森市ホームページ
青森市ホームページ