
伝統工芸産業の振興に関する取組についての質問
目次
伝統工芸産業の振興に関する取組について

新政未来の小笠原です。
私からは、伝統工芸産業の振興に関する取組について質問したいと思います。
【質問①】本県の伝統工芸産業の振興に向けた県のこれまでの取組状況について伺いたい。
地域の産業のことを考えたときに、伝統工芸産業というのは本当に大切なものになってくると思うんです。
地域を表しているというか、青森ならでは、青森だからこそ、この産業があるんだというものを表すものとして、伝統工芸産業というのがあると思うんです。
南部裂織とかもそうですし、こぎん刺しであったり、本当にいろいろなものがあったりしますけれども、そうした中で、今、本県において、伝統工芸産業の振興に向けた県の今までの取組の状況というのはどうなっていますでしょうか。
回答:田澤地域企業支援課長
- 本県には歴史と風土に培われ、県民の生活の中で受け継がれてきた伝統的な工芸品が数多くあります。これらの優れた工芸品の技術を後世に継承し、伝統工芸産業の振興を図るためには、伝統工芸品の価値を高めるとともに、その魅力を発信していくことが重要であると認識しています。
- そのため、県では、伝統工芸品の中で一定の要件を満たすものを青森県伝統工芸品に指定する制度、及び高度な技術・技法を有する製造者を青森県伝統工芸士に認定する制度を設け、作り手の意識高揚と次世代への技術継承の促進を図るとともに、指定等の状況を県ホームページやパンフレットなどを通じて広く県内外に情報発信してきました。
- また、伝統工芸品を含めた本県工芸品の作り手の確保・育成や新たな購買層の獲得に向けて、商品開発や魅力向上の支援にも取り組んでいるところです。
今、一定の要件を満たせば青森県伝統工芸品に指定するということだったんですけれども、一定の要件というのはどういった要件でしょうか。
回答:田澤地域企業支援課長
- 青森県伝統工芸品の指定要件でございますが、5つございます。
- 1つとして、主として日常生活の用に供される工芸品であること、
- 1つとして、その製造過程の主要部分が手工業的であること、
- 1つとして、伝統的な技術または技法により製造されるものであること、
- 1つとして、伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられるものであること、
- 1つとして、伝統工芸品がおおむね50年以上の歴史を有するものであること、以上でございます。
【質問②】伝統工芸については後継者不足が懸念されるが、県が指定する伝統工芸品の製造者数の推移について伺いたい。
この伝統工芸も、ほかの産業や企業等々と同じで、例えば、人手不足や後継者不足があり、どうやって継いでいくのかというのが本当に問題になっていると思います。
この伝統工芸の後継者不足に関して、県が指定する伝統工芸品の製造者数の推移はどのようになっているのかを伺いたいと思います。
回答:田澤地域企業支援課長
- 県が指定する伝統工芸品の製造者数の直近3か年の推移については、
- 令和4年度は年度内の追加が3者、解除が3者あり、年度末時点の製造者数は74者、
- 令和5年度は解除が1者あり、年度末時点で73者、
- 令和6年度は追加が1者、解除が2者あり、年度末時点で72者となっております。
- この3年間で指定解除となった6者の指定解除の理由は、製造停止によるものが多くなっております。
- 一方で、この3年間で県が追加指定した製造者数は4者で、地元市町村の積極的な調査等により増加したものでございます。
新たに指定された製造者もあったりするみたいですけれども、製造中止になってしまったところもあるということですが、製造中止になった理由は分かりますか。
回答:田澤地域企業支援課長
- 全てについて承知しているというところではございませんが、個別の理由のほか、死亡により製造停止となった方もいらっしゃいます。
今の話ですと、結局、製造されていた方が亡くなってしまったということもあったりするみたいですけれども、事前に技術を受け継いでいければ、後継者がいれば続いていけたんでしょうが、製造中止になってしまったということだと思うんです。
そうした中で、本当に青森の伝統工芸を守るためにも、後継者不足を、県としても市町村とも連携しながら考えていって欲しいと思うんです。
【質問③】本県の伝統工芸品の魅力発信に関する県の取組状況について伺いたい。
そして、本県において、青森の伝統工芸品の魅力を発信していくため、どういった取組がなされているのか伺いたいと思います。
回答:田澤地域企業支援課長
- 県では、本県の伝統工芸品を含めた工芸品の販路拡大による産業振興を図るため、これまで首都圏ライフスタイルショップと連携し、多様化する消費者ニーズに対応した商品開発を支援するとともに、効果的な情報発信に取り組んできました。
- 具体的には、首都圏や海外で日本各地の魅力ある商品を発信している株式会社ビームスのバイヤーから助言を受けながら、新商品の開発や既存商品のブラッシュアップを行い、完成した商品は、東京都内にある同社の店舗と公式オンラインショップにおいてテスト販売を実施しました。
- 令和6年度は、新たにインバウンド向けに商品開発の取組を行い、同社におけるテスト販売や、県ホームページ及びSNS等ウェブでの情報発信などを行うとともに、県内バイヤー向けの商品説明会を実施するなど、積極的に本県伝統工芸品の魅力発信を展開したところでございます。
県外向けであったりとか、インバウンド向けのものに対して、そういった策はなされているということなんですけれども、先ほど、伝統工芸品に指定するのに5つの要件があるとおっしゃいました。
その中で、日常生活で使えるものというのがあったと思うんですけれども、青森県民が伝統工芸により親しみやすくなるように扱っていなければいけないことが大事だと思うんですね。
実際、伝統工芸品はどんなものがあるんだろうというのが、やっぱり若い人とかだと特に分からないということもあったりするでしょうし。
手間暇がかかっているので、価格も高いと思うんですけれども、県外やインバウンドではなく、青森県内において、県民の人たちに対して、魅力を発信していくとか、周知をしていく、親しんでもらうようにといった中で、本県において取組されていることはありますでしょうか。
回答:田澤地域企業支援課長
- 県の伝統工芸品に指定された場合は、県伝統工芸品パンフレットやホームページによるPRなどを行っております。
また、伝統工芸士に認定された場合は、同じような形でPRを行っているところでございます。 - 併せて、この伝統工芸品の認定、あるいは伝統工芸士に認定された場合は、報道機関に公表し、報道していただくことで、県内の消費者の方々にも周知を図るような形の取組をいたしております。
報道機関にも、積極的に、例えばリリースなどをして報道してもらうということもなさっているとは思うんですけれども、実際、手に取ってもらうとか、使ってもらうとなったときに、青森でいろんなイベントとかがあるときに、伝統工芸品を作っている方々が出店とかをされたりしてPRしていくということも重要だと思います。
そういった点においても検討してもらって、ぜひPRしたいんだという伝統工芸士の方々を支援していただきたいと思うんです。
【更問】後継者不足解消のため、市町村と連携して、支援策を講じるべきと考えるが、県の認識を伺いたい。
そして、後継者不足を解消していくために、基本的にはこういう伝統工芸は、市町村でいろいろ青森県においては支援されていることというのは多いと思うんですけれども、青森県以外で、伝統工芸を県として支援されているということも結構多いんです。
本県においても、市町村にある意味任せるというのではなくて、市町村と連携した上で支援策を講じていくべきだと思うんですけれども、県の認識を伺いたいと思います。
回答:田澤地域企業支援課長
- 県では、市町村と連携して、伝統工芸産業の振興を図るため、例年、市町村を含めた関係機関による担当者会議を実施し、伝統工芸の状況や支援策の内容等について情報共有しています
- また、青森県伝統工芸品及び青森県伝統工芸士認定制度では、その申請を市町村経由で行うことで、伝統工芸産業に関する状況を相互に把握する仕組みとしているほか、申請手続に関する相談対応等、工芸品製造者へのフォローを市町村と連携して実施しております。
- さらに、県が製作する伝統工芸品パンフレットを各市町村や関係機関に配布することにより、県内の伝統工芸品の内容及び伝統工芸士の活動について広く情報発信しているところです。
- 県としては、こうした取組を引き続き市町村と連携して実施することにより、後継者不足の解消と伝統工芸産業の振興を図ってまいります。
分かりました。
基本的には、よりPRしていく、そして申請などもフォローアップしていくということであると思うんですけれども。
実際に問題になってくるのが、継続していくためにいろいろお金がかかったり、いろいろ周知してPRしていくとなったときに、なかなか手段が分からないとか、そういったときもお金がかかってしまうということもあったりすると思うので。
PRする、周知していく、知ってもらうというのが本当に現代だと重要だと思うんです。
SNSなどでの積極的な発信とかも求められると思いますし、若い人が知らなければ、伝統のあるものというのは廃れていってしまいます。
特に、本当に若い人がそういった伝統工芸、青森にこういうがあるんだよ、こういうところで手に入るんだよといったことを知れるように、県としても積極的に後押ししていただきたいと思います。
以上で質問を終わります。

ご意見・ご感想など
あなたの声を聞かせてください。





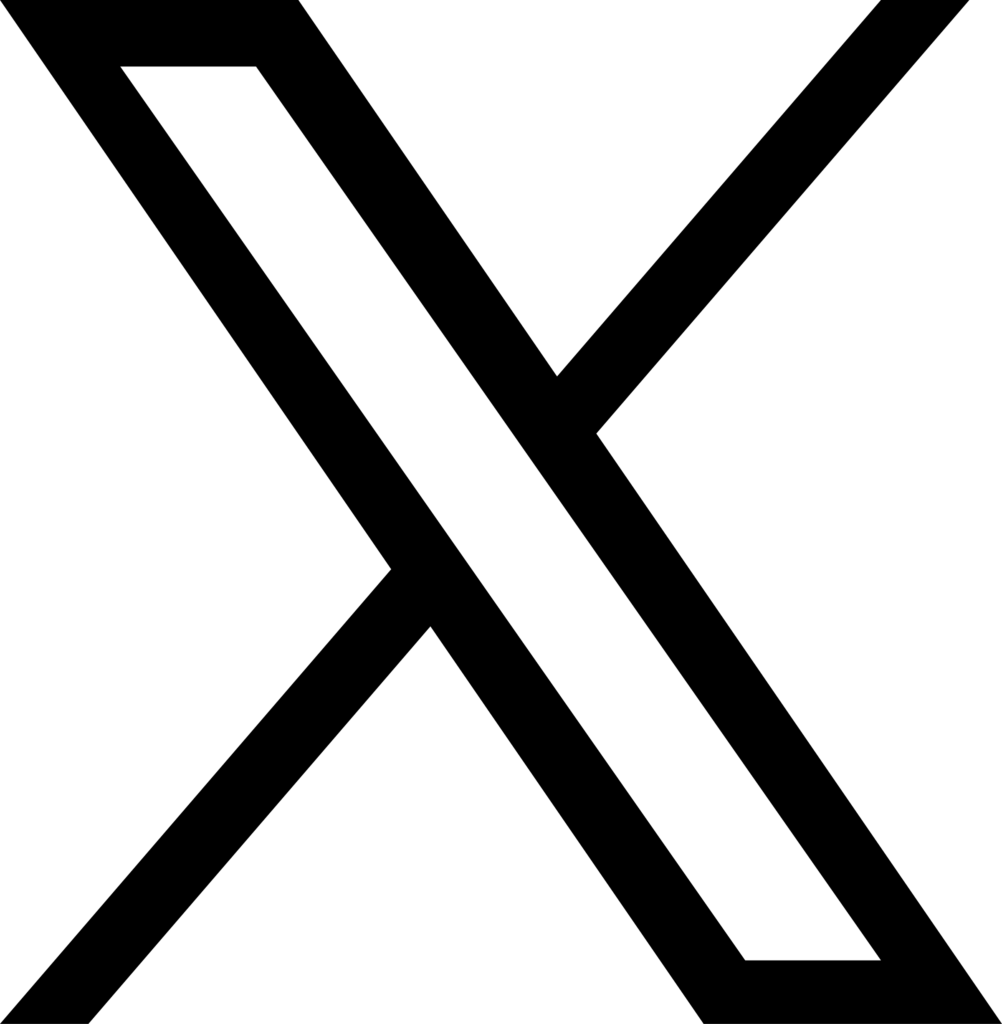
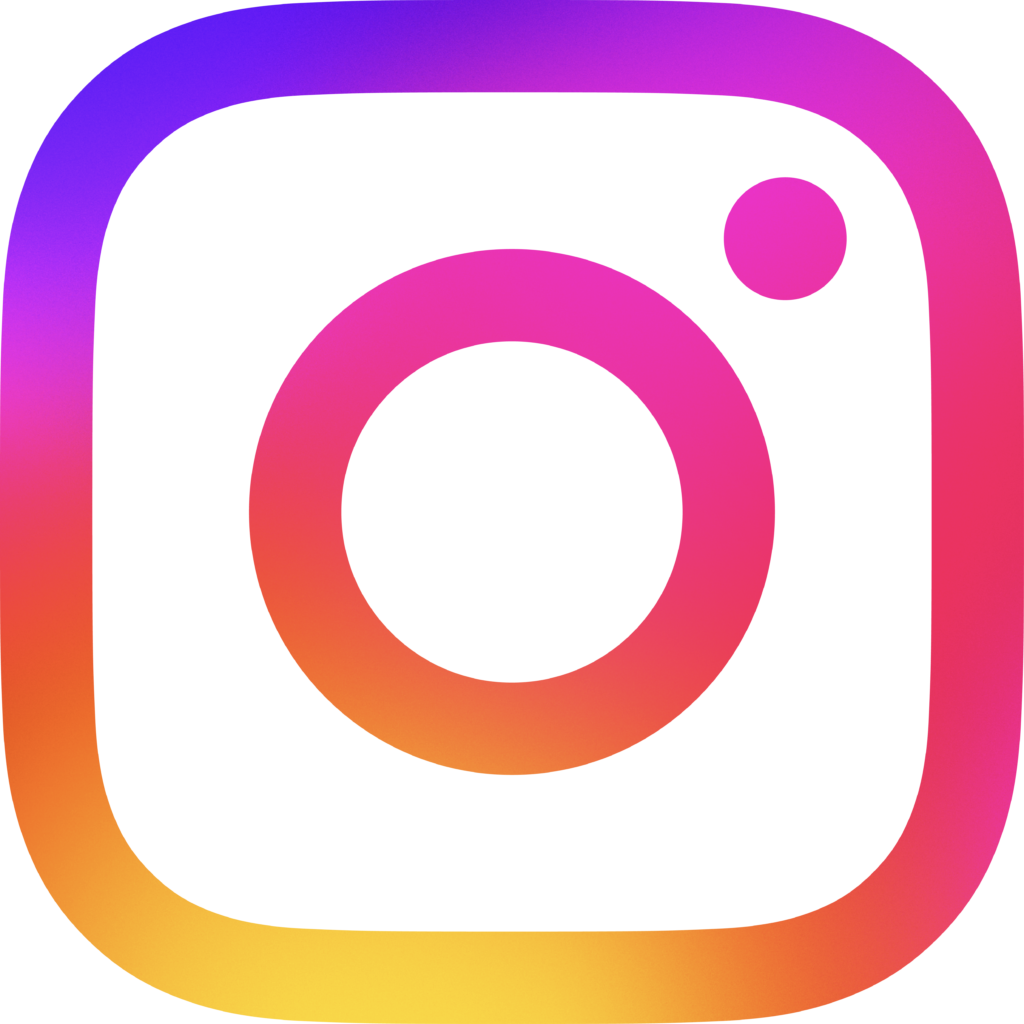

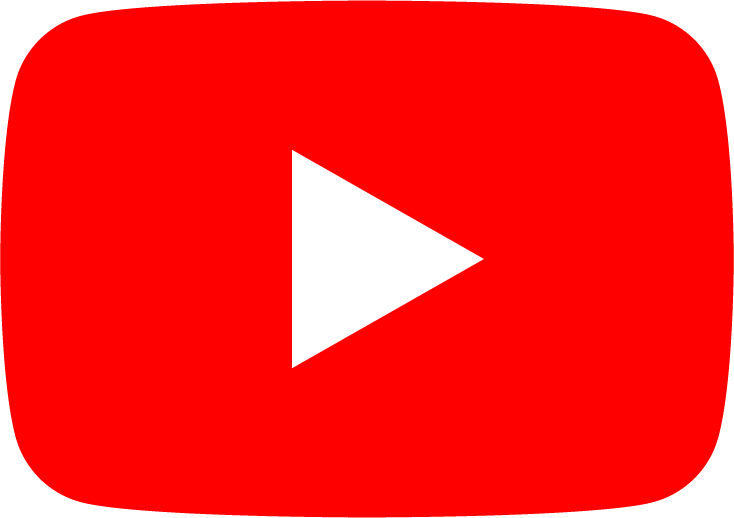

 青森県庁ホームページ
青森県庁ホームページ 青森市ホームページ
青森市ホームページ