
県のスタートアップ支援の取組についての質問
目次
県のスタートアップ支援の取組について

小笠原です。私は、県のスタートアップ支援の取組に関して質問しようと思います。
先ほど安藤委員からもありましたけれども、先月26日に、この委員会で県内調査に行ったときに弘前大学の研究・イノベーション推進機構に伺いました。
弘前大学にこういう施設があったのを全然知りませんでした。
東京都ならともかく、県内、青森県でもそういった学生からの起業の相談が増えていって、支援をしているというのが本当にいいことだなと思っています。
起業支援も若手の人たちがどんどん利用している。
200人以上起業していたり、20代、30代の方も100名以上は起業しているということで、どんどん県内でも利用が増えていると思うんですけれども、県での起業、スタートアップ支援に関して伺っていきたいと思います。
【質問①】県内スタートアップ企業等に向けた技術開発に係る取組について伺いたい。
スタートアップを支援するに当たって、まず、技術をいろいろ研究したり、技術を開発していくという部分。
そうした部分の支援の取組、本県で県内スタートアップ企業などに向けた技術開発に係る取組に関して伺いたいと思います。
回答:原産業イノベーション推進課長
- 県では、青森県産業技術センター工業部門と連携し、製造業を中心とした、スタートアップを含む県内企業等の技術開発支援に取り組んでいます。
- 具体的には、企業等が抱える課題にきめ細かく対応するため、工業部門3研究所において所管する技術分野別に、技術的な相談への助言指導や共同研究を行うほか、製品の品質や耐久性向上のための依頼試験や分析調査の実施、さらには、センターが保有する設備機器の貸出し等を行っているところです。
ちなみに、産業技術センターで、企業が自分たちの設備を置いたり、研究の機器を置いたりであったりとか、長期、短期も含めてレンタルオフィスのような空間もあったりもするのでしょうか。
回答:原産業イノベーション推進課長
- 企業との共同研究や依頼試験、技術相談の際に、企業が施設内で機器の使用をするということはできますけれども、レンタルオフィスのような形での貸出しは行っておりません。
承知しました。
【質問②】あおもりスタートアップ推進事業の取組について伺いたい。
今、技術研究や技術開発に関しての取組を伺いましたけれども、次に、スタートアップそのものに関しての取組を伺いたいと思います。
もともとアイデアを持っているような人もいるでしょうし、そのアイデアをどう実現していくのか、アイデアは差し当たって持っていないけれども、起業に興味があるとか、本当にいろんな立場の人がいらっしゃると思うんですけれども。
そうしたスタートアップに関心がある人、そして進めていきたいという方々に向けて、県としてあおもりスタートアップ推進事業をされているのですが、この取組に関して、詳しく伺えたらと思います。
回答:栗島企業立地・創出課長
- 県では、革新的なビジネスモデルで創業し、短期間での急成長を目指すスタートアップの創出に向けた取組を、令和6年から本格的に実施しています。
- 本事業の具体的な取組内容は、
- 1つとして、県内外の起業家、投資家、支援機関等が参画し、連携して支援するオンラインプラットフォームの運営、
- 2つとして、スタートアップ支援のノウハウを習得する官民協働ワークショップの実施、
- 3つとして、創業時に加えて、創業初期の事業拡大にも活用可能な補助制度の創設などとなっているところでございます。
- それに加え、中高生や大学生などの学生を対象として、創業者の成功体験、スタートアップの魅力や知識、起業家マインドなどを学ぶ人材育成にも積極的に取り組んでいるところでございまして、本県発のスタートアップの創出を強力にサポートしているところでございます。
今、中高生に対してもという話があって、高校生とか大学生とかであれば分からなくもないのですけども、中学生に対してもあるんだと思って。
中学生に対して、中学・高校以上という形だったのか、中学生は中学生としてやっているのか分からないのですけれども、その中学生向けにはどういった取組をされているのか、詳しく聞けたらと思います。
回答:栗島企業立地・創出課長
- 昨年度までは高校生・大学生を中心とした人材育成を行っていたところでありまして、中学生も含めた事業を行うのはこれからでございますので、今検討中の案でございますけれども。
その内容でお答え申し上げますと、スタートアップを創出するためには、新たな価値やアイデアを創造する思考力ですとか、自分のビジョンを実現するための情熱、あるいはリスクを受け入れて挑戦し続ける起業家マインドなどを持った人材の育成が必要であると考えています。 - それに基づきまして、昨年度、高校生や大学生に対する起業家教育を行ってきたところでございますけれども、今年からは、中学生も対象にしまして、自ら課題を発見し、自分ごととして捉えて解決する能力や姿勢が養われるような起業体験プログラムにも取り組んでいきたいと考えています。
結果的に起業するかどうかはともかくとして、中学生の時から何かいろいろ経験したり学べるというのは、本当にすばらしいことだと思うので、ぜひいろいろ検討されて、どういう中身にしていくかというのは考えていらっしゃるところだと思うんですけれども、広く周知して、いろんな若い方が参加していけるようにしていただければと思います。
【質問③】県内のスタートアップが利用できる研究開発の場の整備が必要であると考えるが、県の見解を伺いたい。
そして、先月の委員会県内調査で行ったときに、いろいろ話を伺った中で、起業支援の課題、どういったものがあるのかと話になったときに、いろいろ起業支援の課題があるということですが、やっぱり気になったのが、研究開発の場というのがないなという、そこに関しての課題があるというお話をされていたんです。
まず、法人登記に関して、県外出身の学生が起業するとなったときに、学生アパートに住んでいる、でも学生アパートだと登記ができない、だから県外の実家の住所での登記になってしまうという話であったりとか、職員でも賃貸に住んでいる方は、事業活動の場所としては使えない。
弘前大学でも、シェアオフィスというのを設置して、登記の場所であったり、活動の場にもしてはいるんですけれども、規模が大きくなっていったときに、次のステップに進みづらい。
24時間シェアオフィスもなかなか使えるわけではない。週末にも使えない。
物理とか化学実験を行う研究室という、ウェットラボというらしいんですけれども、そういったものもなかなか県内にないし、そうした課題があるというお話をされていたんです。
その中で、例として挙げられていたのが、岩手県では県として岩手県工業技術センターに委託をして、そして研究開発拠点ヘルステック・イノベーション・ハブというのを設置しています。
なかなか新しく研究開発の拠点を設置するというのは難しいかもしれません。
でも、既存の施設を活用したりとか集積したりして、そして研究開発の場をつくる、整備していくというのを県として考えていかなければいけないと思うんです。
そして、県内のスタートアップが利用できる研究開発の場、拠点を県として整備することが必要ではないかとやっぱり思います。見解を伺いたいと思います。
回答:栗島企業立地・創出課長
- 県では、県内大学や金融機関等の支援機関から構成されるあおもりスタートアップ推進ワーキンググループを立ち上げ、スタートアップ支援の方向性について幅広い関係者と意見交換を行ってきました。
- 昨年度、委員御指摘のありました研究開発の場の整備、いわゆるウェットラボについての議論もありまして、そのときには、現段階では具体的なニーズが生じていないことや、大都市にある民間施設でも必ずしも運営が安定しているわけではないことなど、様々な意見も上げられたところでございます。
- 県としては、これらの意見を踏まえ、まずは研究開発拠点への入居費用を補助対象に含めた支援制度を実施しているところでありまして、まず、そういうところの資金面の支援を行っているところでございます。
- 研究開発の場の整備については、具体的なニーズが顕在化した場合に、改めてワーキンググループにおいて意見交換を行った上で必要な政策を検討したいと考えてございます。
- なお、本年3月に弘前大学に竣工されましたグローバルWell-being総合研究棟というものがございますけれども、そこにはいわゆるウェットラボ、研究開発の場も整備される予定と聞いておりまして、大学発スタートアップの社会実装に向けた支援がなされるものと認識しております。県としては、当該施設の活用も促すなど、様々やっていきたいと考えております。
今のところ、そういったニーズがないということで、弘前大学でもそうした施設が整備されていくという話があったんですけれども、やはり場があって生まれていくということもあるでしょうし、何の分野なのかというのでも全然違ってくると思います。
研究機関や商工団体などと密に連携しながら、本当に様々なニーズというのをくみ取って、そうした研究開発の場の整備に向けて取り組んでいただき、青森県でスタートアップがより活性化していってほしい。
県で生まれた技術であったり、会社が、場がないから県外の施設に移転してしまうという可能性もあるのではないかと指摘されていました。
やっぱり移転してしまうと、税金などもそっちに行ってしまうし、せっかくこの青森で研究され、生まれた技術なのに、すごくもったいないことだと思うので、ぜひ、今後とも研究開発の場の整備であったり、スタートアップ支援に力を入れていただければと思います。

ご意見・ご感想など
あなたの声を聞かせてください。





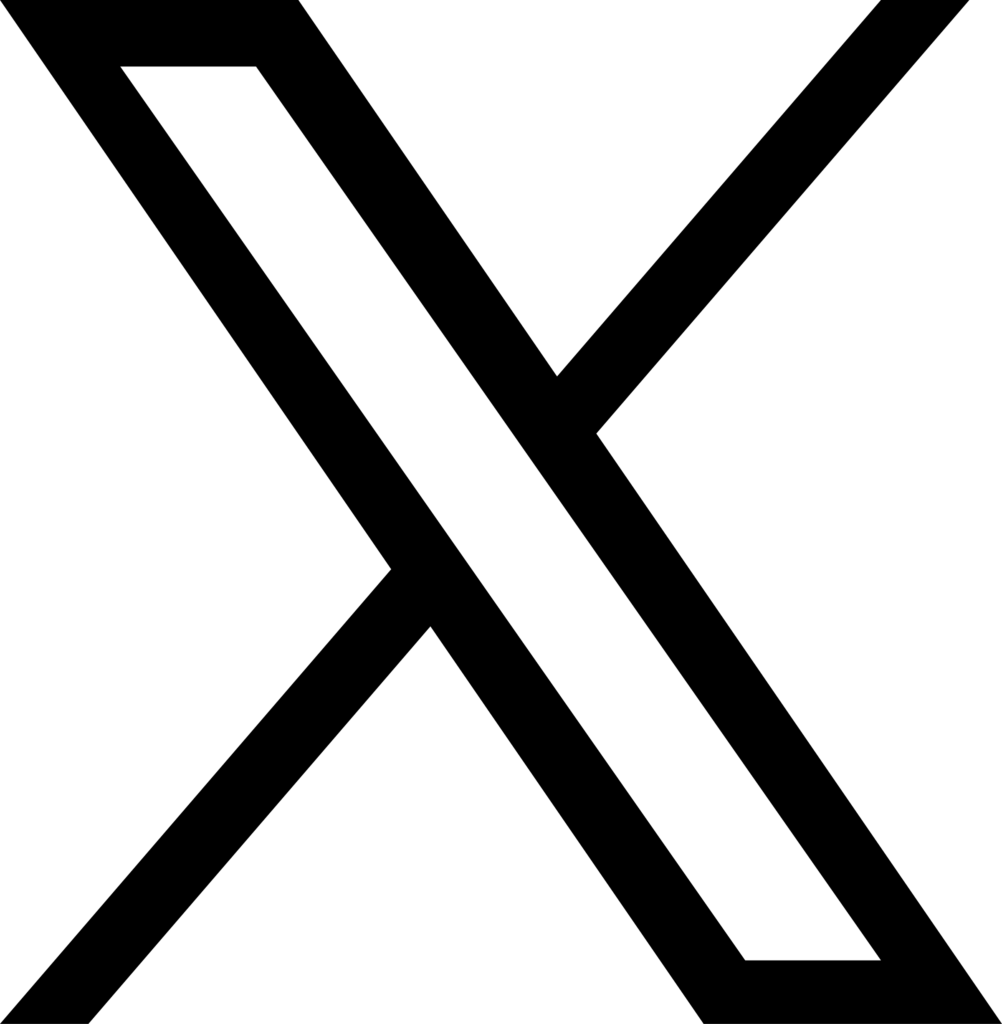
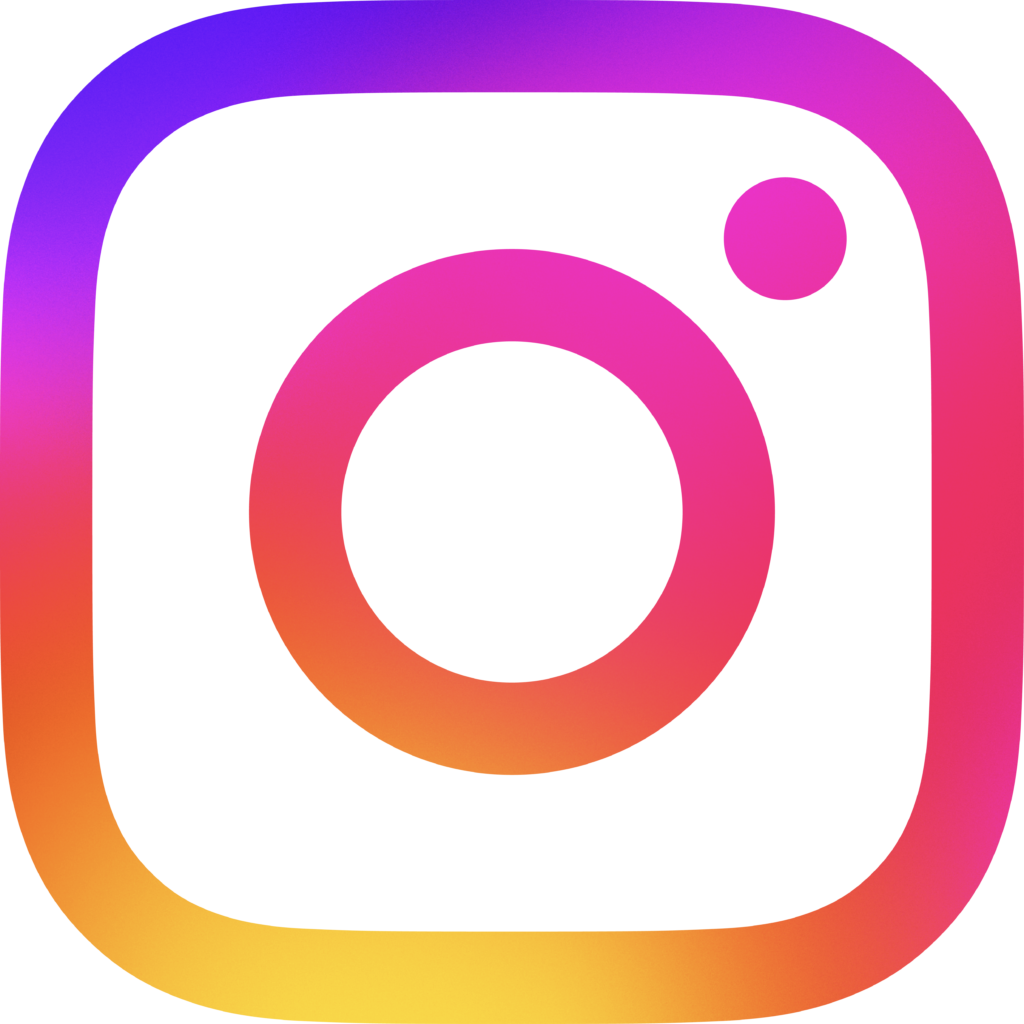

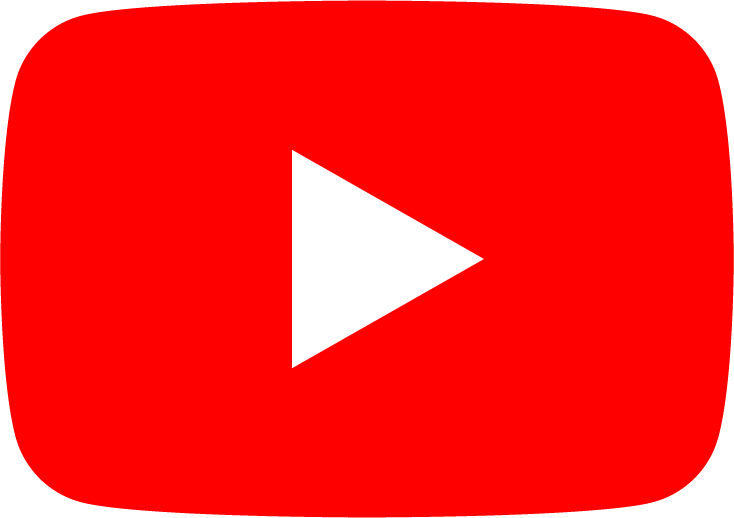

 青森県庁ホームページ
青森県庁ホームページ 青森市ホームページ
青森市ホームページ