
一般質問【令和7年6月第322回定例会】
目次
再生可能エネルギーの導入拡大について

新政未来の小笠原です。
毎年6月に一般質問しているような気がします。
本当に早いもので2年がたって、川村議員、花田議員からもありましたけれども、知事は2023年の6月29日に就任されて──ちなみに、6月29日は私の誕生日でございます。33歳で出馬しましたが、今月で36歳となります。
よろしくお願いいたします。
質問項目が多いので、早速質問していきます。
【質問①】 県内の電力需要に対する再生可能エネルギーの発電実績の割合と今後の導入の見通しについて伺いたい。
まず、再生可能エネルギーの導入拡大に関しての質問をします。
7月より自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例が青森県でも施行されていきますが、知事は、再生可能エネルギーに関して、自然環境との共生を前提に、県内の電力需要相当量の全てを再生可能エネルギーによる発電で賄うことが可能な規模の導入を目指していくということをおっしゃっています。
そうした中で、本当にその目標に向けて割合というのをどんどん増やしていく必要があると思うんですけれども、その割合は今現在どうなっているのか。
この点から、今、県内の電力需要に対する再生可能エネルギーの発電実績の割合と、今後の導入の見通しについて伺いたいと思います。
回答:環境エネルギー部長(豊島信幸)
- 資源エネルギー庁の令和4年度電力調査統計にある県内における電力需要に対する再生可能エネルギーの発電実績は、約42.6%となっております。
- また、未稼働分のFIT認定済みの再生可能エネルギーなどを単純に加えました県内の再生可能エネルギーの年間発電量は、先ほど申し上げた令和4年度の県内の電力需要を上回ります。
【質問②】 カーボンニュートラルの達成に向け、さらなる再生可能エネルギーの導入を図る必要があると考えるが、県の見解を伺いたい。
本県では、これまで、主に太陽光発電や風力発電を中心に再エネ導入が進められてきましたが、いろいろと課題があるわけです。
課題がある中でいろいろ条例も定められているわけですけれども、太陽光発電であったりは、設置面積が大きく必要である。そして、青森は雪が降るので、積雪時の発電量の低下とか、そうした問題もある。
環境の問題もあります。風力発電も同様に、騒音や景観への懸念から地域との調整が必要となる。
立地可能な場所にも制約があるわけですが、こうした課題を解決してくれそうなものとして、次世代型の再エネ技術の導入が鍵となるのではないかと私は思っています。
近年では、同じ太陽光電池でもペロブスカイト太陽電池は、黒いシートを貼るんですけれども、軽量で柔軟性があって、建物の壁面や窓にも設置ができることから、豪雪地域でも通年で安定した発電が期待されています。
また、次世代型の地熱発電は、既存の温泉地への影響を抑えつつ、24時間安定供給が可能な点で有望であります。
いろいろ開発するのにコストはかかりますが、本県には豊富な地熱資源があると思っていますし、ポテンシャルなどもあるとは思っています。
こうした観点から、カーボンニュートラルの達成に向けて、さらなる再生可能エネルギーの導入を図る必要があると考えますが、県の見解を伺います。
回答:環境エネルギー部長(豊島信幸)
- 再生可能エネルギーの円滑な導入を図るため、青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例を本年3月に制定し、7月には運用が開始されることから、この適切な運用を図ってまいります。
- 次世代型太陽光電池や次世代型地熱につきましては、これからの進展に注視しながら考えていきたいと考えております。
【質問③】 今後の再生可能エネルギーの導入拡大に当たっては、地域資源を活用した地域振興の視点が重要であると考えるが、県の取組について伺いたい。
そして、再生可能エネルギーの導入拡大に当たっては、単に発電量を増やすことだけではなくて、地域経済であったり、地域の課題を解決していくことが重要だと思っています。
近年では、発電した電力の多くが域外に送られるだけで、地域に利益が十分還元されていないのではないかといった課題も指摘されるわけです。
そして、今後の再エネ拡大に当たっては、発電設備の設置だけでなく、地元企業の参入の促進であったり、人材育成、部品製造、メンテナンスなどの産業の創出にまでつなげていく視点が不可欠だと思います。
本県には、ものづくり産業の基盤、自然エネルギー資源、地域に根差した事業者のネットワークがあります。
こうした地域の強みを生かし、再エネを新たな地場産業として育成していくことであったり、また、再生可能エネルギーを導入していくことで地域の課題を解決していく、それが地域振興になっていくと思っています。
いろんな可能性が本当に無限大だと思うのが再生可能エネルギーだと私は思っています。
そこで、今後の再生可能エネルギーの導入拡大に当たっては、地域資源を活用した地域振興の視点が重要であると考えますが、県の取組について伺います。
回答:知事(宮下宗一郎)
- 再生可能エネルギーの導入拡大に当たっては、地域が主体となって地域資源を活用することで、新たな産業や雇用の創出、エネルギーコストの削減などのメリットが還元されるなど、地域が抱える課題の解決につながる仕組みづくりが重要と考えております。
- 例えば、脱炭素先行地域に選定された佐井村では、海洋漂着プラスチックごみを燃料として加工し、漁協の水産加工場のボイラーで利用する取組が進められております。
- 県では、このように地域が主体的に挑戦する取組について、国による各種支援制度を活用するための助言や情報提供を行うなど、社会実装に向けた伴走支援をしっかりと行ってまいります。
水道事業の広域化について
次に、水道事業の広域化について質問いたします。
人口減少と施設の老朽化が進行する中で、水道事業の持続可能性をどう確保するかは県民の生活に直結する重要な課題です。
こうした状況を受けて、県では、令和5年3月に青森県水道広域化推進プランを策定し、県内を地区に分けて広域化の協議を進めてきました。
しかしながら、各地区の関係自治体との間で合意形成に至らなかった事実が明らかとなっています。
こうした背景には、コスト負担の公平性であったり、設備の更新の時期をどうするか、水源管理の権限であったり、職員体制の変化であったり、様々な問題があると思います。
水道広域化に当たっては、施設更新の平準化や技術職員の安定確保、経営基盤の強化といったメリットもあるでしょうが、中山間地、小規模自治体においては、広域化によって自前の水道が失われるのではないか、運営が大規模自治体の中心になってしまうのではないか、そういった疑念もあるわけです。
課題をいろいろと整理しながら、丁寧に議論を進めていくことが必要だと思います。
では、青森県水道広域化推進プランに基づく広域化の検討状況について。
また、水道事業の広域化に向けて、県はどのように取り組んでいくのか。
この2点について伺います。
【質問①】 青森県水道広域化推進プランに基づく広域化の検討状況について伺いたい。
回答:財務部長(千葉雄文)
- 本県の水道事業を取り巻く経営環境は、人口減少に伴う料金収入の減少に加え、施設の老朽化に伴う更新費用の増大などにより厳しさを増しておりますことから、県では、国からの要請などに基づき、令和5年3月に青森県水道広域化推進プランを策定したところであります。
- 同プランでは、県内の市町村等を6地区に分け、市町村の区域を越えた広域的な連携等による経営基盤の強化に向けた検討を進めてまいりましたが、令和6年度末時点では、経営部門を集約化します経営の一体化、料金も含め、事業そのものを統合いたします事業統合に着手することは困難であり、当面は見送るという結論になっております。
- 一方で、いずれの地区も、これまでの検討を踏まえまして、令和7年度以降も事務の広域的処理や施設の共同設置・共同利用など、段階的な連携を端緒としながら、引き続き検討や取組を進めていくという方向性を示しておりまして、将来的な広域化の必要性は各市町村等で共有されているものと認識しております。
【質問②】 水道事業の広域化に向けて、県はどのように取り組んでいくのか伺いたい。
回答:知事(宮下宗一郎)
- 水道事業は、地域住民の生活を支える重要なライフラインであります。
経営の一体化や事業統合といった広域化の実現に向けては、各市町村等の料金水準や経営規模、施設の管理状況など、中長期的な視点でその格差の解消に取り組む必要があります。 - 広域化の実現に当たっては、各地区それぞれの課題があるものと認識していますが、コストの抑制はもちろんのこと、災害発生時における対応の強化にも資する取組となることから、県としては、各市町村等の協議に基づく判断を最大限尊重しつつ、県民の安全・安心を支える水道事業の広域化が推進されるよう助言してまいります。
若者の社会参画について
次に、若者の社会参画についての質問に移ります。
本県では、若者世代の県外流出・転出が依然として深刻な課題です。
進学や就職を機に若者の多くが県外に出ていき、その多くがなかなか戻ってこないという現実があります。また、令和六年度の青森県の合計特殊出生率は1.14と過去最低の水準となり、将来的な地域の縮小、消滅のリスクというのが現実味を帯びているわけです。
こうした県外流出・転出、人口減少の要因には、経済的な要因というのはもちろんあるんですが、気持ちの問題、若者のマインドの問題がやっぱり大きいのではないかなと私は思うんですね。
青森に住み続けても、なかなか将来に希望が持てないであったりとか、若者の声が、私たちの声がなかなか届かない、といった諦め、無力感が根底にあるのではないかと思います。
若い人と関わっていく中で、高齢者や子供には支援制度があるのに、自分たちは何の対象にもなっていないといった声を聞くんですね。
実際に、社会保障費の配分や制度の多くが高齢者や児童生徒に向けられていて、若い世代、18歳以降30代前半くらいまでの子供でもない、高齢者でもない現役の若者世代というのが公的支援の谷間に取り残されているのではないか。
また、不登校経験やひきこもり、経済的困窮、家庭内問題など、多様な困難が複雑に絡んでいるケースも多くて、支援につながるには時間と関係性の構築、若い人の支援には本当にいろいろ構築していかないといけないと思っています。
そういった背景を踏まえて、2つの観点から質問したいと思います。
【質問①】若者の声を聴く機会について
まず、若者の声をどう聞いていくのか、若者の声を聞く機会をいかにつくるのかということです。
若者の声を政策に反映させることは、単に施策の多様化を図るという目的にとどまりません。
若者にとって自分たちの声が社会に届いたと感じられることは、社会への信頼を築き、地元に残ることや戻ってくることへの動機づけにもなると思っています。
コミュニティーの問題であったり、ここにいられるんだ、ここに行けば自分の声が届くんだ、そういった感覚がやっぱり必要ではないかなと思っています。
そこで、若者のニーズや提案を政策形成に生かすために若者の声を聞くことが重要と考えられますが、県の考えを伺います。
若者のニーズや提案を政策形成に生かすため、若者の声を聴くことが重要と考えるが、県の考えを伺いたい。 回答:知事(宮下宗一郎)
- 若者が、未来を自由に描き、実現できる社会を実現するためには、当事者である若者の意見にしっかりと耳を傾け、対話を通じて進むべき方向性を見いだしていくことが重要と考えております。
- そこで、県民対話集会「#あおばな」では、小、中、高校生や大学生、若手社会人と青森県の未来について対話を重ねてきたほか、これ以外でも様々な機会を通じて若者と対話し、政策のヒントを得てきたところであります。
今後も、若者の声をしっかりと受け止め、若者のニーズや提案を政策形成に生かしてまいります。
【再質問】あおばなは行政が主体であるが、若者が主体となり提言をする「あおもりユース会議のような場を設置し、若者の意見反映、社会参画を促し、県の若者政策に活かしていくべきと考えるが、見解は
「#あおばな」は、これからもぜひ続けて、多くの県民の声を聞いていただきたいと思います。
何度も応募しても抽せんに漏れている団体もあるようですが、もちろんそういった方々も今後対話の機会を設けられるようにして、多様な声を聞いてほしいと思います。
ただ、私が思うのは、未来の青森を担うのはやはり若者たちで、人口流出、若者の定着・還流、まちづくりなどにも様々な思いを持っていますし、アイデアもあるはずです。
そうした若者の声をより一層生かす場があればよいのではないかと考えます。
「#あおばな」は、ある意味、行政が主体となるんですけれども、若者が主体となって提言する、例えば青森ユース会議のような場を設置して、若者の意見反映、社会参画を促して、県の若者政策に生かしていくべきと考えますが、いかがでしょうか。
回答:知事(宮下宗一郎)
- 若い人たちにはぜひ主体的にそういう場を設置して、提言いただきたいと思います。
【質問②】 多様な若者への支援について
そして、多様な若者への支援について。
青森県にも、若くてもなかなか職が得られていない方もたくさんいらっしゃいますし、不登校であったり、ひきこもりの方、精神疾患を抱えている方、経済的に困窮している方、家庭内の問題を抱えている方、本当にいろんな問題を抱えている方がいらっしゃいます。
こうした若者たちは、1つの問題ではなくて、複数の問題が絡み合っていたりします。支援につながるまでに時間を要することがあるわけです。
こうしたいろんな問題、困難な問題を抱えている若者への支援について、県ではどのように取り組んでいるのか伺います。
(ア)困難を抱える若者への支援について、県ではどのように取り組んでいるのか伺いたい。 回答:こども家庭部長(若松伸一)
- 若者のうち、特にニート、ひきこもり、不登校、発達障がいなど、社会生活を円滑に営む上で困難を抱える若者は、その要因や課題が複雑化かつ複合化しております。
- このため、県では、津軽、県南、下北の3地域に、教育、保健、福祉、雇用、非行防止などの各分野の関係機関で構成する地域ネットワーク会議を設置し、各地域においてそれぞれが連携し、切れ目のない総合的かつ継続的な支援を行う体制づくりに取り組んでおります。
- また、困難を抱える子供、若者やその家族が必要とする支援を必要なときに得られるよう、県内三地域で各地域ネットワーク会議構成機関による合同相談会を開催するとともに、SNS広告配信による相談機関の周知を行っております。
また、若者の支援においては、困難を抱える若者だけではなくて、特に大きな問題を抱えていない人たちというのも、本当にいろんな若者がいらっしゃるわけです。
仲間と交流したり、自己実現や社会参画の場を求めているアクティブな若者ももちろんいらっしゃいます。
困難な事情を抱えている若者、アクティブな若者、こうした幅広いニーズを持つ多様な若者に対して、教育、福祉、医療、地域団体、企業など、いろんな関係機関が連携して、包括的で切れ目のない支援、支え合いの環境を整備することが重要だと思います。
多様な若者の声を幅広く、どう受け止めていくのか。
ここで、質問として、若者を支援する機関相互の連携を深めていくことが重要と考えますが、県の考えを伺います。
(イ)若者を支援する機関相互の連携を深めることが重要と考えるが、県の考えを伺いたい。 回答:知事(宮下宗一郎)
- 私は、1人でも多くの若者が青森県で人生を送ることに多様な可能性を見いだし、自分の夢が青森県でかなえられる環境づくりに向け、行政、教育、企業、産業、NPO、ボランティア、地域活動、相談対応といった若者を支援する各種機関が、引き続きしっかりと連携しながら、様々な取組を進めていくことが重要であると考えております。
【再質問】多様な若者が集い、活動する若者の居場所「ユースセンター」を、本県での設置の検討、また設置の支援を行うべきと考えるが、見解は
先ほどの質問では、既存の機関や団体が相互の連携を深めて若者のケア、支援によりつなげていくという話でしたけれども、こちらももう一歩進んで、多様な若者が集って活動する若者の居場所、ユースセンター──このユースセンターは、青森県以外でも設置されているところがあったりするんですけれども。
これを例えば本県で設置する検討をしたり、また、設置する支援を行うべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
回答:こども家庭部長(若松伸一)
- ユースセンターにつきましては、若者の日常圏にあるオープンアクセスの施設、また、主に若者の利用を想定していることなどが関係団体から示されており、例えば勤労青少年ホームや児童館、自立支援や就労支援施設、NPO法人などがこのユースセンターに当たるのではないかと認識しております。
また、ユースセンターにつきましては、明確な定義は確立されていないものと認識しております。 - 今年度、こども家庭庁では、子供、若者の居場所づくりに関する取組として、若者世代の居場所づくりに関する検討を進めることとしております。
県としては、まずはこども家庭庁での検討を注視していきたいと考えております。
このユースセンターというのは、本当に定義がいろいろ曖昧な部分がありますけれども、例えば海外だとスウェーデンなどでも、今ユースセンターは結構盛んになっているという話も聞きます。
国内でもそうですし、国外の例も含めて、青森県でもぜひ何かいろいろ考えていただければと思います。
多様な学びの場の確保について
次に、多様な学びの場の確保についてです。
【質問①】青森市が公立夜間中学の設置を表明したことについて、県教育委員会の受け止めと今後の対応について伺いたい。
先月、青森市が令和7年度の開校を目指して、公立夜間中学校の設置を表明しました。
学びの多様性を広げ、学校に通えなかった方々の学び直しの場を確保する重要な動きと評価したいと思います。
特に青森市は、今、青森市外からもそういった生徒を受け入れる意向を示しています。
全県規模での学びの受皿としての役割を期待されていることには注目に値します。
ただ、一方で、設置主体が市であるために、県全体の教育施策としての整合性や支援体制をどう構築していくのかは大きな課題だと思っています。
これまで、県と市の間で夜間中学の設置に関する役割分担であったり、設置主体の決定がなかなか進まなかった中で、青森市が設置の方向で動き出したという経緯もあります。
このため、今後、県教育委員会と青森市教育委員会が密接に連携しながら、学びの場としての夜間中学の機能を全県的に支えるための体制づくりが不可欠と考えます。
そこで、青森市が公立夜間中学の設置を表明したことについて、県教育委員会の受け止めと今後の対応について伺います。
回答:教育長(風張知子)
- 昨年度、県教育委員会が設置した公立夜間中学設置検討委員会において、夜間中学について、令和9年4月の開校を目指すことが望ましいとされたところです。
このような中、青森市における夜間中学の設置は、本県初となるだけでなく、他市町村からの生徒の受入れについても検討するとの意向であり、本県における様々な背景を持つ生徒の就学機会の充実に寄与する取組になるものと受け止めています。
今後は、設置主体となる青森市において、具体の事項について検討することとなりますが、県教育委員会では、その検討状況を踏まえて、青森市以外の市町村の通学対象者等に関する調査を行うなど、夜間中学の設置に向けて、青森市教育委員会と協議を進めていきます。 - また、6月2日に青森市から県に対して、新設準備に係る経費への財政支援を求める要望書が提出されたところであり、他市町村からの生徒の受入れなど、夜間中学の設置に係る青森市の取組を確認しながら、対応について検討していきます。
【質問②】不登校児童生徒の多様な学びの場の確保について、県教育委員会としてどのように捉えているか伺いたい。
そして、近年、学校に通うことが難しい児童生徒の数は増加傾向にあるわけです。
例えば家庭の事情であったり、心身の不調、対人関係の悩みであったり、本当にいろいろな理由で学校に通えなくなる子供がいる。
こうした子供たちが学び続けるために、学校以外の多様な学びの場というのもあるわけです。
フリースクールであったり、ボランティアの活動などもあるわけですけれども、多様な選択肢が今でもあったりはするんですが、その数や質というのが地域によって差があって、まだまだ十分ではないのではないかと思います。
こうした状況を踏まえて、県教育委員会としては、児童生徒の学びの権利を保障するために、学校現場だけではなくて、多様な学びの場の整備や支援に県として主体的に取り組んでいくべきではないかと思います。
不登校児童生徒の多様な学びの場の確保について、県教育委員会としてどのように捉えているのか伺います。
回答:教育長(風張知子)
- 県教育委員会では、児童生徒が不登校になった場合でも学びたいと思った際に多様な学びにつながることができるよう、児童生徒1人1人の状況に応じた学習支援や相談支援として、校内教育支援センターや市町村が設置する教育支援センターでの支援のほか、そうした支援につながっていない児童生徒に対しては、ICTの活用や支援員等による訪問支援が必要だと考えています。
- また、児童生徒が社会とつながりを保ち続け、将来を見据えた社会的自立ができるよう、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと学校、教育委員会、関係機関等が連携して支援することが大切だと考えています。
性の多様なあり方への理解促進について

次に、性の多様な在り方への理解促進についてです。
来週の28日の土曜日、青森県において、レインボーパレードが開催されます。
今までは青森市で行われていましたが、今回は八戸市で初開催されます。
ちなみに、私がつけているこのレインボーのこぎん刺しも、昨年のレインボーパレードで手に入れたものです。
レインボーパレードは、LGBTQ+などの性的マイノリティーの方々が、誰もがありのままに自分らしく生きられる社会を目指して、町を歩き、可視化し、理解を求める場です。
レインボーの色には、赤は命、オレンジは癒やし、黄色は太陽、緑は自然、青は調和、紫は精神を意味するなど、多様性と調和を象徴する意味が込められています。
このレインボーパレードは、単なるカラフルな行進ではなく、いまだ社会の中でいないことにされがちな人々が、ここにいるんだ、ここで生きているんだと手を挙げる、そんな静かで力強い意思表示だと思います。
そして、今、こうしたパレードが青森県でも開かれるようになったということが変化の兆しであり、私たちが耳を傾けるべき声がこの青森県にもあるということを示していると思います。
性の多様性をめぐる課題は、決して特別な誰かのものではなく、地域で共に生きる一人一人の尊厳に関わる問題です。
そして、性的マイノリティーの方が互いを人生のパートナーとして共に生きていくというパートナーシップ制度、本県でもパートナーシップ宣誓制度が創設されて3年余りが経過しましたが、現在の青森県パートナーシップ宣誓制度の実施状況について、また、性の多様な在り方に関する理解の促進に向けた県の取組についても伺いたいと思います。
【質問①】青森県パートナーシップ宣誓制度の実施状況について伺いたい。
回答:こども家庭部長(若松伸一)
- 令和4年2月の制度創設から、これまでに16組が宣誓を行っており、うち3組は利便性向上のために導入したオンラインでの本人確認により、来庁せずに手続を行いました。
- また、県では、宣誓書受領証の提示により利用できるサービスの拡充に向けて、市町村や医療機関、民間事業者などに働きかけを行ってきました。
その結果、利用できる行政サービスは、昨年4月からこれまでに、1つとして、パートナーの治療や検査行為の同意等の際に利用できる医療機関が22か所から30か所に増加、県営住宅のほか、公営住宅への入居申込みの際に利用できる市町村が8か所から12か所に増加、また、住民票や税証明の交付等の際に利用できる市町村が7か所から13か所に増加などとなっております。
民間サービスは、保険商品を取り扱う生命・損害保険会社が17社、賃貸住宅への入居をあっせんする不動産会社が4社などとなっております。
【質問②】性の多様なあり方に関する理解の促進に向けた県の取組について伺いたい。
回答:こども家庭部長(若松伸一)
- 県では、第五次あおもり男女共同参画プランに基づき、性的マイノリティーであることを理由とする困難の解消に向けて、性の多様な在り方に対する理解の促進に取り組んでおります。
具体的には、性の多様性に関する当事者団体の協力を得てパンフレットを作成し、県内企業や県内の各大学、短期大学、専門学校等に配布しているほか、企業や県及び市町村職員等を対象とした研修会の開催などに取り組んでおります。 - また、青森県パートナーシップ宣誓制度について、パートナーシップの関係にあるカップルに加えて、生計を一にする未成年の子を家族として届け出ることができる内容に改正するなど、当事者団体等の声やニーズに応えるとともに、性の多様な在り方や、それに伴う多様な家族の在り方について、理解の促進を図っております。
【質問③】性の多様性に配慮した取組を行う県内企業の登録制度の導入について、県の考え方を伺いたい。
そして、性の多様な在り方への理解促進を社会全体で進めていくためには、行政だけではなくて、地域の企業や職場の取組も不可欠だと思っています。
社内でのハラスメントの防止であったり、性別を限定しない服装規定、同性パートナーを対象にした福利厚生の見直しなど、企業の姿勢が当事者の働きやすさや暮らしやすさに直結すると思います。
こうした企業の取組を見える化し、県として積極的に後押しすることは、当事者が安心して働ける環境を広げるだけでなく、地域全体のダイバーシティー推進、そして企業の魅力向上にもつながると思っています。
埼玉県でもアライチャレンジ企業登録制度というのを設けていたりして、性の多様性に配慮した取組を行う企業を登録、公表しています。青森県においても、こうした先行事例を参考にしながら、企業や事務所が性の多様性に配慮した取組を行っていることを認定、公表する制度を導入してはいかがでしょうか。
そこで、性の多様性に配慮した取組を行う県内企業の登録制度の導入について、県の考え方を伺います。
回答:こども家庭部長(若松伸一)
- 性の多様性に配慮した取組を行う企業の登録制度については、制度の呼称や登録要件などが自治体によって異なりますが、東京都や埼玉県などに導入事例がございます。
県としましては、国の動向や他の自治体の実施状況を踏まえつつ、県内企業や当事者団体等のニーズを参考にしながら、対応について検討していきたいと考えております。
本県における外国人患者への医療提供について
次は、本県における外国人患者への医療提供についてです。
全国的にインバウンドが増えています。
先ほどの花田議員の答弁にもありましたけれども、宿泊者数も過去最高ということで、でも、今注目すべきはインバウンドの問題、観光だけの問題ではありません。
県内で働き、暮らし、地域の一員として生活する外国人住民、いわゆる在留外国人の存在です。
今、青森県の在留外国人の数は、令和6年末時点で8,045人(※令和6年6月時点での最新、現在は8,603人)とされています。恐らく今後も増えていくことだと思います。
彼らは一時的な労働力や観光資源ではありません。
同じ社会に共に生きる存在です。
その前提として、在留外国人の方々も、誰もが安心して医療を受けられる体制の整備が必要ではないかと思います。
ただ、その整備に当たって、言語の壁などの対応がどうなっているのか。
厚労省のホームページでも、外国人対応ができる医療機関を公表していますが、そのウェブページでは青森県はまだ少ないんですね。
5つくらいしか公表されていなくて、ほかの同じく在留外国人が青森県より少ないところでも対応できる機関がもっと多く登録されていたりするわけです。
共に生きる外国人の方々が医療にきちんとアクセスができるようにしないといけない。
しっかりと支援体制を整えなければいけません。
【質問】外国人患者に関する県内医療機関の対応状況及び県の取組内容について伺いたい。
では、質問です。
外国人患者に関する県内医療機関の対応状況及び県の取組内容について伺います。
回答:健康医療福祉部長(守川義信)
- 医療機関では、外国人患者の受入れに当たり、医療通訳者の配置、電話通訳及びスマートフォンを介した翻訳サービスなどの活用等を行っており、全国の医療機関情報を検索できる国の医療情報ネット「ナビイ」によると、令和7年6月現在で県内の病院、診療所の237施設が外国語に対応しています。
- 県では、外国人患者の円滑な受入れに向けて、対応可能な医療機関などをホームページで公開しています。
また、県内医療機関に対し、外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアルの周知を図るとともに、外国人患者の対応状況について、医療情報ネット等による情報提供を促しています。
【再質問】外国人患者受け入れ体制をより整備していくため、本県でも、医療通訳者や外国人患者受け入れ医療コーディネーターの養成をより促していく必要があると考えるが、見解は
本県における外国人患者への医療提供についてですが、ナビイというホームページでは237機関が対象になっているとはいえ、これは翻訳アプリとか、そういったサービスとかも使いながら外国人も対応できるよということだと認識しています。
実際、それがあっても十分に使いこなすことができるのかという問題もあると思いますし、そして、そもそもそういった病院がある、機関があるというのを在留外国人の方々がきちんと把握していくというのも必要だと思いますので、そういった周知の状況を、まず国際交流グループ、外国人相談窓口などとも連携しながら周知を図っていただきたいと思っています。
そして、厚生労働省の外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリストの中で、やっぱり医療通訳者がいる機関が2つとか、3つくらいだったと思うんですけれども、医療通訳者や外国人患者受入れ医療コーディネーターというのが重要な役割を担うと思うんです。
普通の日常会話と違って、医療機関でのやり取りというのは本当に専門的な知識も必要になると思うんです。
外国人患者受入れ体制をより整備していくために、本県でも医療通訳者や外国人患者受入れ医療コーディネーターの養成をより促していく必要があると考えますが、見解を伺います。
回答:健康医療福祉部長(守川義信)
- 県としましては、外国人患者の円滑な受入れに向けて、県内医療機関に対し、国が実施している外国人患者受入れ医療コーディネーター養成研修の周知や、医療通訳の技能に関する資格等の情報提供を行っていきたいと考えています。
今後も積極的に外国人患者への医療提供を整備していただければと思います。
動物取扱業に対する動物愛護管理対策について

次に、動物取扱業に対する動物愛護管理対策についてです。
皆さんはペットの移動販売というのを御存じでしょうか。
トラックに犬、猫たちをたくさん乗せて、広いイベント会場でまとめて並べて販売します。
会場には100頭とか、たくさんの犬、猫たちがいらっしゃいます。
いろんな種類の犬、猫たちが集まって、イベントへの来場者もたくさんいるわけです。
しかし、一方で、こうしたペットの移動販売の在り方には多くの問題点が指摘されています。
例えば関東圏の動物取扱業者がトラックに犬、猫などを乗せて、青森に長距離、長時間をかけて移動してくる。
青森だと片道で10時間近くかかるわけです。
人間でもすごく負担がかかります。
ものすごく動物に負担がかかっている。
先月末も青森市内の産業会館で開催されていましたし、あの豪雪の1月にもテレビで同様の開催告知のCMが流れていました。
もちろん、動物取扱業者は、国の基準にのっとった上で移動販売を行ってはいます。
ただ、それが本当にいいのか、動物にとってよいことなのか、本当に根本から問い直す必要があると思います。
そうした点でも私は問題提起をしたいと思います。
そして、なぜ移動販売が行われるかというと、時間やコストをかけて青森に来ても、それだけ来場者がいて、ペットが購入されて利益になるから業者も来るわけです。
動物たちにとって、移動販売は身体的にも精神的にも大きな負担となり、健康状態に深刻な影響を及ぼすことも少なくありません。
さらに、販売会場となるイベント会場は、人混みであったり、騒音であったり、動物にとって過酷な環境であることも多いと聞きます。体調を崩す原因にもなります。
また、移動販売では、短期間の販売と引渡しが主であるため、購入者に対する丁寧な説明やアフターフォローが不十分となりがちです。
買ったばかりの動物が体調を崩してしまった、どこに相談すればいいんだろうといったトラブルや相談も各地で報告されています。
こうした状況を踏まえて、中央環境審議会動物愛護部会においても、動物の移動販売に関する課題について指摘されています。
今後の議論や規制の在り方が問われています。
動物は物ではなくて、命ある存在です。
その命がどう扱われ、どう売買されているのか、私たち一人一人が関心を持って考えていくことが大切だと考えます。
では、質問いたします。
動物取扱業者が臨時の施設でペットを販売するための基準及び本県における直近3年間の施設の登録件数について。
また、臨時の施設でのペットの販売の状況や購入に関して、直近3年間で県に寄せられた相談の内容と県の対応について伺います。
【質問①】動物取扱業者が臨時の施設でペットを販売するための基準及び本県における直近3年間の施設の登録件数を伺いたい。
回答:健康医療福祉部長(守川義信)
- 臨時の施設で犬や猫などのペットを販売するためには、営業者は、一般の動物取扱施設と同様に、動物の愛護及び管理に関する法律に基づく第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。
同法では、第一種動物取扱業については、職員の配置や飼養施設の規模及び構造等に関する基準並びに事業者が遵守しなければならない動物の管理の方法等に関する基準を定めています。 - 県では、登録に当たっては、現地調査により、これらの基準に適合していることを確認しており、臨時の施設においては、特に入念に動物の健康状態を観察しています。
- なお、直近3年間のペットの販売に係る臨時の施設の登録件数は、令和4年度2事業者5件、令和5年度2事業者7件、令和6年度2事業者5件となっています。※注:2つの事業者が年間にペットの移動販売イベントを行った件数
【質問②】臨時の施設でのペットの販売の状況や購入に関して、直近3年間で県に寄せられた相談の内容と県の対応について伺いたい。
回答:健康医療福祉部長(守川義信)
- 直近3年間で県に寄せられた臨時の施設でのペット販売の状況や購入に関する相談件数は、令和4年度、令和5年度及び令和6年度の毎年度1件ずつで、いずれも購入したペットの体調不良に関するものでした。
- 県では、このような相談を受けた際には、必要に応じて事業者に対する調査を行い、ペットの適正な取扱いについて指導しています。
加えて、当該事業者による次回の販売施設の登録申請に係る立入調査時には、特に入念な健康観察を行うなど、販売されるペットの健康確保に努めています。
公立小・中学校等の教員の確保に向けた取組について
次の質問は、公立小・中学校などの教員の確保に向けた取組についてです。
現在、県内の学校現場では、深刻な教員不足が現実のものとなっています。
新しい年度が始まって子供たちが新しい学年で学びをスタートさせているこの時期に、担任として配置されていなくて、担任として配置されるべき教員がそもそも足りていない状況もあるわけです。
本来であれば、教員の数そのものを全国的に増やして教職の魅力を高めるなどして、持続的かつ根本的な改善を図っていく必要があります。
そのためには、国がもっと責任を持って制度的な対応を講じていく必要がありますが、しかし、国の対応を待っているだけでは目の前の子供たちの学びの機会を保障することはできません。
【質問】公立小・中学校及び義務教育学校における教員の未配置を解消するため、臨時講師を確保すべきと考えるが、県教育委員会ではどのような取組を行っているのか伺いたい。
日々の教育に直接影響する切実な問題、それが教員不足です。
ただ、当面の対応としては、臨時講師を確保して、その臨時講師の方々を未配置のところに少しでも配置して、解消していくことが必要だと思います。
その観点から、まず、公立小・中学校、義務教育学校における教員の未配置を解消するために、臨時講師を確保すべきと考えますが、県教育委員会ではどのような取組を行っているのか伺います。
回答:教育長(風張知子)
- 県教育委員会では、教員採用候補者選考試験受験者へ臨時講師等の募集案内を送付することに加え、通年にわたり、ハローワークを通じての募集や退職教員等に対する働きかけを行っています。
- また、新規学卒者の他県への流出を防ぐため、教員採用候補者選考試験において採用に至らなかった方に対し、試験の結果を通知した後、可能な限り早い時期から臨時講師としての勤務依頼を行っています。
- さらに、教員免許を持ちながら長らく教職を離れている方や教職未経験者等への働きかけとしての各教育事務所における説明会の開催、小学校教諭免許状所持者の増加に向けた認定講習の開催、小学校教員の魅力を発信するためのPR動画やリーフレットの作成と、SNS等を活用した情報発信等により、臨時講師を含めた教員の確保に取り組んでいます。
教職員の負担軽減に向けた取組について
そして、次は、教職員の負担軽減に向けた取組についてです。
先ほどの質問でも触れたように、今、学校現場では深刻な教員不足が続いていて、教員の負担というのは本当に増えている状況ですが、この教員の業務負担というのを軽減していかないといけない。
これは、教員の数を増やすだけではなくて、その業務をほかに、どのような手段で軽減していくのか。
教員のこういった過重労働は、教育の質の低下を招くだけではなくて、教職を目指す若者が減少する大きな要因にもなっています。
これ以上、教職を、やりがいはあるが、続かない仕事にしてしまっては、教育現場はもちません。
負担軽減には主に二つの側面からのアプローチがあると思います。一つは、人的支援の充実です。
【質問①】公立学校におけるスクールサポートスタッフの配置について
書類の整理や教材の準備、事務手続など、子供たちと直接関係のない業務をスクールサポートスタッフが担うことによって、教員が本来の教育活動に集中できる環境を整えることができます。
スクールサポートスタッフの配置は、限られた教職員体制の中でも教育の質を保つ上で非常に重要です。
では、公立学校におけるスクールサポートスタッフの配置について、令和7年度当初のスクールサポートスタッフの配置状況と、スクールサポートスタッフを確保するために、県教育委員会ではどのように取り組むのか伺います。
(ア)令和7年度当初のスクールサポートスタッフの配置状況について伺いたい。 回答:教育長(風張知子)
- 県教育委員会では、教員の業務支援を図り、教員がより児童生徒への指導や教材研究等に注力できる体制を整備することを目的に、外部人材を活用したスクールサポートスタッフ配置事業を実施しています。
- 令和7年5月1日現在の配置状況は、小・中学校及び義務教育学校が386校中304校、高等学校が46校中29校、特別支援学校が20校中19校となっています。
(イ)スクールサポートスタッフを確保するため、県教育委員会ではどのように取り組むのか伺いたい。 回答:教育長(風張知子)
- 県教育委員会では、県内の全ての公立学校でスクールサポートスタッフを活用できるよう、ハローワークを通じた幅広い募集、学校や市町村教育委員会と連携したPTAや地域ボランティア、卒業生の保護者等、学校運営に関心の高い人材への働きかけなどを進めており、引き続き、これらの取組を通じてスクールサポートスタッフの確保に努めていきます。
【質問②】デジタル技術の活用による校務の負担軽減について
そして、こうした人的な支援と併せて、教職員の負担軽減のために不可欠なのがデジタル技術の活用による校務の負担軽減です。
これまで、学校では、出席簿の管理であったり、採点、成績処理など、膨大な事務作業が教員にのしかかってきました。
授業の準備時間も減る、生徒と向き合う時間も奪われる、ひいては教育の質そのものにも影響してくる。
そうした中で、近年は校務のデジタル化が進むことで、事務作業の自動化、業務の効率化が実現されつつあり、教員からも負担が減った、業務が楽になったとの声が聞かれます。
まず、県立学校におけるデジタル技術を活用した校務の負担軽減のための県教育委員会の取組は今どうなっているのか確認したいと思います。
(ア)県立学校におけるデジタル技術を活用した校務の負担軽減のための県教育委員会の取組について伺いたい。 回答:教育長(風張知子)
- 統合型校務支援システムについては、令和4年度から全ての県立学校において運用しており、生徒指導要録、出席簿等の帳票様式が統一され、教職員が学校を異動した際も同じシステムで作業を進めることができるなど、負担軽減につながっています。
- また、令和6年度から全ての県立高等学校及び県立中学校にデジタル採点システムを導入し、この活用によって、採点、集計、得点転記作業の効率化が図られ、採点業務が大幅に軽減されています。
- さらに、全ての県立学校にクラウド型の連絡ツールを導入したことにより、配布資料や行事案内等のペーパーレスによる情報共有や、保護者からのデジタルツールによる欠席連絡等が推進され、校務の時間的な負担が軽減し、児童生徒と向き合う時間の確保につながっているものと認識しています。
ただ、この校務支援システムなんですが、知人の教員から伺った話なんですけれども、青森市から弘前市の学校に異動になったら校務支援システムが変わってしまって、大変戸惑ってしまったと。
これは、東青であったり、西北、三八など、各地域ごとに異なる校務支援システムを導入していたので、教員が地域をまたいで異動した際に、使用するシステムが変わってしまった。
それで新しく覚えないといけない。
その結果、せっかく慣れたシステムが使えなくなってしまって、操作方法をまた新たに覚えないといけない、慣れないといけない。そうした負担がかかってしまっていたわけです。
今、県教育委員会では、様々な声を受けて、これを統一するという方向に向かっているという話を聞きます。
校務支援システムが各地域で違う状況から、県域で統一させることで異動時の混乱を避けることができるほか、学校間、自治体間での情報共有やサポート体制の一元化も可能になり、より効果的な運用、負担軽減となると思っています。
そこで、市町村立小・中学校及び義務教育学校における統合型校務支援システムの県域での統一に向けた取組について伺います。
(イ)市町村立小・中学校及び義務教育学校における統合型校務支援システムの県域での統一に向けた取組について伺いたい。 回答:教育長(風張知子)
- 市町村立小・中学校及び義務教育学校の統合型校務支援システムについては、各市町村の判断により整備することとなっておりますが、令和5年度に県教育委員会と県内全ての市町村教育委員会とで設置した青森県GIGAスクール推進協議会において、教職員の負担軽減の一助として、統合型校務支援システムの県域での統一に向けた意見交換を行ってまいりました。
- その結果、令和7年2月にプロポーザルを実施し、青森県GIGAスクール推進協議会として推奨する統合型校務支援システムを決定しました。
- 今後、各市町村の実情に合わせて決定した統合型校務支援システムを導入していくことになりますが、市町村の導入経費削減や事務負担軽減の観点から、県教育委員会が主導して共同調達の準備を進めているところです。
県立高等学校における校則について
次は、県立高等学校における校則についての質問です。
ブラック校則という言葉が生まれて久しくなりましたが、過度に厳しいとか、合理性に欠ける校則が生徒の人権や自己決定権を侵害しているのではないかという声があるわけです。
ツーブロック禁止、下着の色指定、地毛が茶色でも黒に染めさせる、 そういった内容の校則はさすがに少なくなったかなと思いますが。
私が現在公開されている県内高校の校則を見たんですけれども、ヘアゴムの色は黒、紺、茶色、トランプの持ち込み禁止──これはなぜでしょうか。
男女の交際は、相互の人格を尊重し、明朗健全でなければいけない──明朗健全とは何でしょうか。
これは校則に入れる必要があるのか。
また、高校生らしい清楚な着装で、高校生らしい髪型──何々らしいというのは誰かが決めることではないのではないでしょうか。
文科省でも、校則の見直しに当たっては、生徒や保護者の意見を聞き、必要に応じて定期的に見直すことや、その内容や趣旨を丁寧に説明することを求めています。
青森県内でも生徒自身が校則の見直しを求めて学校と対話して、より現実に即した内容に変更された事例があるとは伺っています。
ただ、一方で、いまだに校則が学校外、外部から確認できない状況にある高校も存在しているわけです。
校則は、学校に通う生徒やその保護者にとって重要な生活上のルールであり、公開されていないことで外部からのチェックや意見表明の機会を失ってしまうという問題もあります。
では、ここで質問です。
1点目、県立高等学校における校則の公開状況と、公開を促すための県教育委員会の対応について。
2点目として、県立高等学校における合理性に欠ける校則に関し、県教育委員会の把握状況と、それに対する見解を伺います。
【質問①】県立高等学校における校則の公開状況と、公開を促すための県教育委員会の対応について伺いたい。
回答:教育長(風張知子)
- 県教育委員会では、令和3年3月に各県立学校に対し、校則の積極的な見直しと公開に向けた検討を進めるよう通知しており、その後も県立学校長会議や生徒指導関係会議等において、繰り返し検討を依頼しています。
- なお、校則を学校のホームページに掲載している県立高等学校は、令和7年1月時点で30校あり、前年度より13校増加しています。
【質問②】県立高等学校における合理性に欠ける校則について、県教育委員会の把握状況と、それに対する見解を伺いたい。
回答:教育長(風張知子)
- 県教育委員会では、学校への訪問指導等の機会を捉えて校則の確認を行っており、把握している範囲では、著しく合理性に欠ける校則はないと認識しています。
- 校則は、人権に配慮しつつ、社会通念上、合理的と認められる範囲において、教育目標の実現という観点から校長が定めるものとされていますが、県教育委員会としましては、今後も必要に応じて、各学校に対し、指導や助言を行うなど、適切に対応してまいります。
【質問③】各校が校則改正の手続きについて明文化するべきと考えるが、県教育委員会の見解を伺いたい。
そして、さらに重要な視点は、校則の改正に係る手続が不透明であることです。
実際には、生徒が校則の見直しを求めても、どのような手順で変更がなされるのか、あるいは誰が決定権を持っているのかが明確でない学校が多く存在します。
おかしいなと思っても、そもそもそれをどう変えていいのか分からない。
こうした不透明さは生徒の参画意欲をそぎ、学校と生徒との信頼関係の構築にも支障を来しかねません。
改正手続を明文化することによって、生徒や保護者が自らの意見を表明する機会を得るだけでなく、学校側にとっても変更プロセスが整理されて、対話のルールが明確になると思います。
また、手続が明文化されることで、学校が一方的にルールを決めるのではなくて、民主的な意思決定のプロセスを生徒が経験する、身近なところから自分たちで声を上げてルールを変えていく、非常に大切なことだと思います。
では、3点目として、各校が校則改正の手続について明文化するべきと考えますが、県教育委員会の見解を伺います。
回答:教育長(風張知子)
- 文部科学省が令和4年に改訂した生徒指導提要では、校則を策定したり、見直したりする場合にどのような手続を踏むことになるのか、その過程についても示しておくことが望ましいとされています。
- 県教育委員会としましても同様に考えており、各学校において校則改正の手続の明文化を含め、生徒指導提要の趣旨を踏まえた適切な対応がなされるよう働きかけてまいります。
【再質問】校則の改正手続きの明文化の状況も、校則の公開状況と合わせ県教育委員会として把握し、促して行くべきと考えるが、見解は
校則の公開状況は、今30校と把握していらっしゃると思いますけれども、校則改正の手続が明文化されているかというのは把握していらっしゃるのか。
もし把握していないのであれば、こうした校則改正手続の明文化の状況も校則の公開状況と併せて県教育委員会として把握して、そして、より積極的に促していくべきだと思います。
きちんと把握することも必要だと思います。見解を伺います。
回答:教育長(風張知子)
- 県教育委員会では、学校への訪問指導等の機会を捉えて校則の確認を行っており、校則の改正手続の明文化についても、必要に応じて、各学校に対し助言を行うなど、適切に対応してまいります。
公益財団法人青森県育英奨学会が運営する青森県学生寮について
では、最後の質問です。公益財団法人青森県育英奨学会が運営する青森県学生寮についてです。
東京都小平市にある青森県の学生寮に関して、私は何度も取り上げていますが、家賃、食費などの生活費が年間60万円ほどと破格で住める。
東京に住めば、普通ならこの倍以上はかかります。経済的負担が全然違うわけです。
何とか有効に活用されてほしいという願いがあります。
【質問①】直近3年間の入寮者の推移について伺いたい。
現在、県のホームページでも、今、議場でタブレットをお持ちの方は、この学生寮に関してちょっと検索していただければと思います。
まだ定員を満たしていないので、年度途中の入寮者希望を受け付けていますとあります。
100名の定員ですが、最近は半分どころか、40名すら切っている状況で、運営費の赤字分は基金から補填、その基金の残りも、このままではあと数年で尽きてしまう。
入寮者の確保をどうしていくのか。
まず、今年度の入寮者を含めた直近3年間の入寮者の推移について確認します。
回答:教育長(風張知子)
- 学生寮の定員は、男子100名となっており、直近3年間の入寮者数については、令和5年度は33名、令和6年度は31名、令和7年度は36名となっています。
【質問②】入寮者の確保に向けて、保護者に対する一層の周知が必要であると考えるが、県教育委員会の見解を伺いたい。
また、入寮者を確保するために、ともかく存在を知ってもらわないといけないわけです。
広報誌であったり、インスタなどのSNSなどでも確かに発信はしていらっしゃいます。
しかし、誰によりアプローチすればよいのかというと、生徒以上にその保護者の方々であって、保護者により直接的なアプローチが必要なのではないか。
例えば熊本県の学生寮では、入寮を希望する保護者の方へ説明会を開催しています。
このように、保護者の説明会の場を設けたり、また、進路指導を通じたり、手段はいろいろ考えられますが、入寮者の確保に向けて、保護者に対する一層の周知が必要ではないか、県教育委員会の見解を伺います。
回答:教育長(風張知子)
- 青森県育英奨学会では、これまで高等学校に学生寮のパンフレットを送付するとともに、第三学年の全ての男子生徒に対し、学校を通じて入寮生募集要項を配付しています。
また、高等学校長やPTAの会議で周知、教育広報、県広報紙、県ホームページ及び県教育委員会公式インスタグラムへの入寮生募集案内掲載などにより、入寮生の確保に取り組んでいます。 - 県教育委員会では、生徒及び保護者に対しての周知が重要であると考えていることから、青森県育英奨学会と連携し、他県の事例を含め、周知方法について検討していきます。
【再質問】女子学生が入寮できない不平等な状況が続いているが、県教育委員会としてはこの状況をどのように認識し、解消していくのか
私が確認したところだと、昭和63年(昭和62年度決算特別委員会)の議事録に女子学生が入寮できない問題が取り上げられていました。
そのときは、施設の構造などから見て難しいが、育英奨学会の理事長にも話して検討させたいといった答弁だったんですね。
37年前からこうやって言われていて、全く同じ状況ではないのかと思います。
議事録では、建部議員だったり、渡辺議員であったり、今この議場にいる議員だと伊吹議員であったり、菊池議員、阿部議員だったり、党派を超えていろんな議員が今まで指摘しているんですね。
でも、ずっと変わっていない。
現在の学生寮に女子学生も入れるようにするとか、新設するとか、アパート、マンションなどを借り上げて、女子学生が入れるような学生寮を設けるとか、学生寮がない代わりに住宅費の支援をする、いろんな手段はあると思います。
この不平等な状況への対応策というのはいろいろ考えられるとは思いますが、女子学生が入寮できない不平等な状況が続いているというのを県教育委員会としてはどのように認識しているのか、そして、どのように解消していくつもりなのか質問します。
回答:教育長(風張知子)
- 学生寮の運営につきましては、公益財団法人青森県育英奨学金(後刻「青森県育英奨学会」に訂正)が決定するものですが、青森県育英奨学金(後刻「青森県育英奨学会」に訂正)を所管する県教育委員会としましては、女子の入寮のみならず、立地、学生のライフスタイルなどの変化及び改修費用等を総合的に考慮し、検討する必要があると考えております。
- 失礼しました。青森県育英奨学会でございます。訂正させていただきます。
私の元に届いた1通のメールを紹介したいと思いますので、聞いてほしいと思います。
ほぼそのまましゃべります。
『我が家は、妻と娘三名の至って普通の家庭です。
娘たちには成人以降、子育てなどで生活に拠点を置く必要が生じるまでは、一度きりの人生だから、親元を離れていろんな経験をしてほしいと思い、東京での生活を勧めてきました。
しかし、学費と親元を離れた生活が娘に奨学金受給やバイト掛け持ちを強いることとなり、本来の目的がかすんでしまう状況となっています。
これらの理由により、長女は合格した美大への進学を断念しました。
次女は、新聞奨学生として2年間、朝晩配達をしながら専門学校に通っています。
三女は、この春、都内の専門学校に進学が決まり、運よく近隣に居住する親族に間借りできそうですが、気遣いからのストレスも心配しています。
親として満足な生活環境を与えることができないことを申し訳なく思います。
青森県学生寮に女子学生の受入れが可能となれば、私たちと同じ悩みを抱える親娘の一度きりの人生を強力にバックアップする施策になることは間違いありません』と。
教育長、いかがでしょうか。実際にこうした声があるんです。
1人の女子学生が進学を諦めてしまった。
ほかにも進学を諦めたり、進学しても経済的理由で苦しんでいる女子学生はいることでしょう。
私自身もネット上でアンケートを実施しました。
そのアンケートは241人の方が答えてくれたんですけれども、そのうち8割以上は女子学生が入れないこの不平等な状況を是正すべきとの答えだったんですね。
運営しているのが育英奨学会だからといって逃げないでほしいんですね。
これは女子差別撤廃条約にも明確に反していますし、県人寮で過ごした学生、若者たちは、必ず未来の青森にも関わって貢献してくれると思っています。
それを踏まえて、この解消に向けて、育英奨学会とより話していくであるとか、そういったことを37年前からずっと言われているんです。
もっときちんと検討すべきだと思うんです。
きちんと話し合っていくべきだと思うんです。
いかがでしょうか。
回答:教育長(風張知子)
- 先ほど男性、女性の不平等というお話がございましたけれども、当初は昭和66年(後刻「昭和56年」に訂正)に建設されておりまして、その頃は男子が東京の学校へ行く率が高いということからこういった制度を設けてやってきたと思うんですが、現在におきましては──昭和56年ですね──男性と女性だけに限らず、なぜ東京の子供たちだけなんだということもあり、様々なこととか、あと奨学金の在り方のお話が議員からもございましたけれども、そういったこととかを総合的に考えて、どういった形で支援することができるのかということを検討する必要があると考えているところでございます。
分かりました。
なぜ東京だけなのかというのはあります。
ただ、今現に東京の小平市に学生寮があるので、それを活用できるなら活用できたほうがいいですし、首都圏はやっぱりお金がかかってしまうというのもあるんですね。
今まできちんと育英奨学会ともこうすべきというのを話しているのか。
ほかの県の学生寮などでは、不平等な状況が続いているから女子も入れるようにしたとか、新設したというのもきちんとあるんですね。
今までそもそも話しているのか。
そして、今後どうしていくのかというのをきちんと考えてほしい。
繰り返しになりますけれども、37年前からずっと変わっていない。
同じことをずっと言われていて、令和7年の今も全く同じ答弁になってしまっているのかなと思います。
先ほど1通のメールを紹介しました。やっぱり女子学生がどうも不平等な状況に置かれている。
今の時代はライフスタイルが本当にいろいろあると思いますけれども、真剣に考えていただきたいと思います。
若者の未来を潰さないようにしていただきたいと思います。

ご意見・ご感想など
あなたの声を聞かせてください。





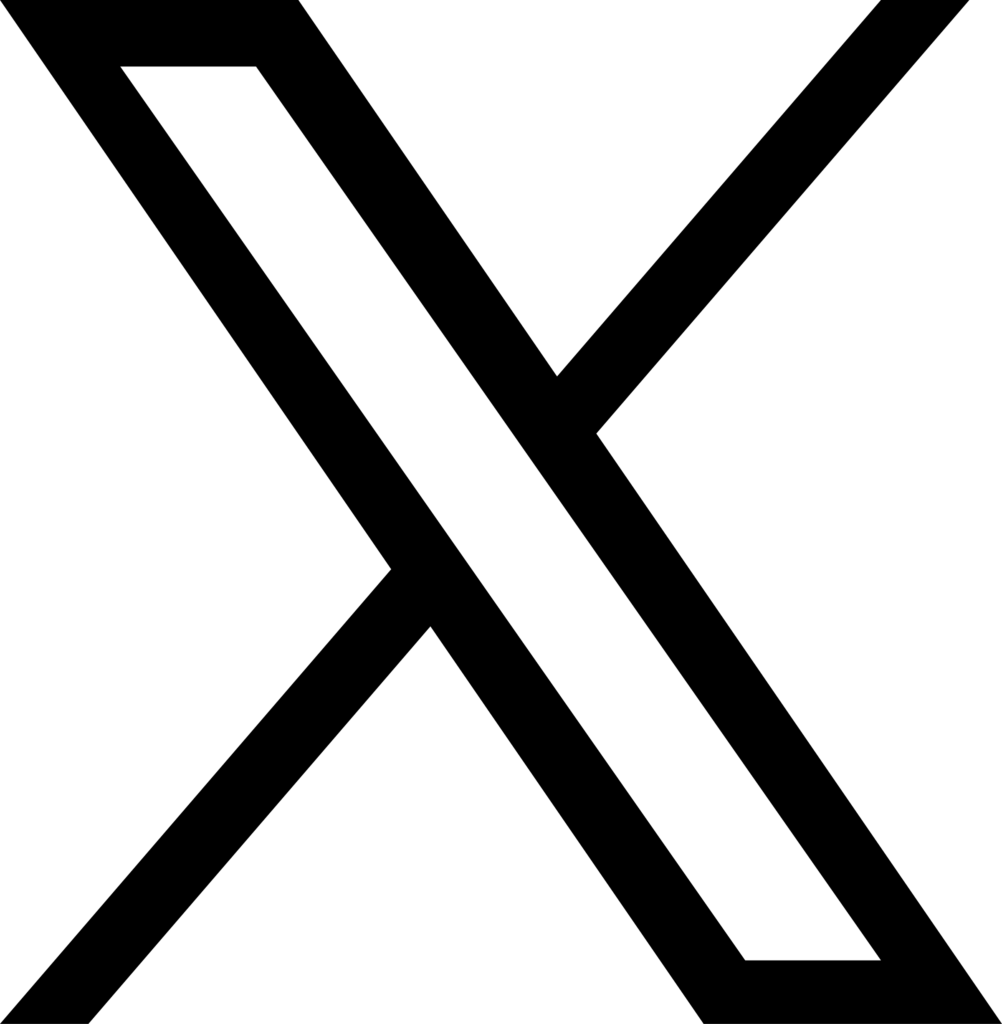
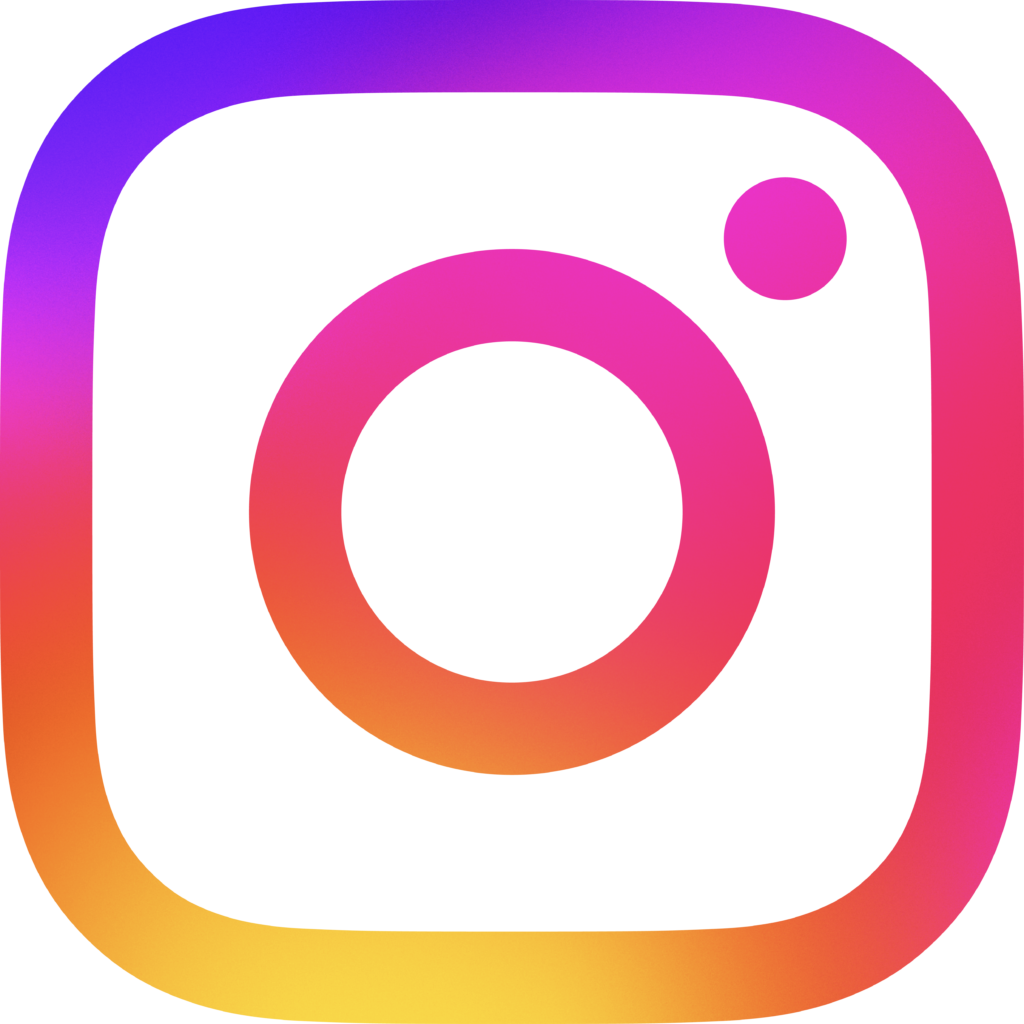

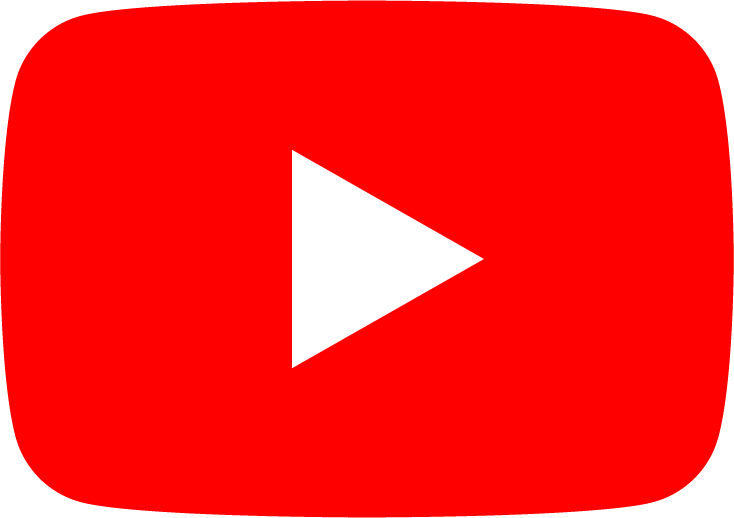

 青森県庁ホームページ
青森県庁ホームページ 青森市ホームページ
青森市ホームページ