
近隣道県からの誘客促進等についての質問
目次
近隣道県からの誘客促進について

8月に入り、青森ねぶた祭りが開催されるほか、県内各地で祭りが予定されています。現在は選挙期間中ですが、インバウンド観光客が著しく増えている状況にあります。
近年、クルーズ船の寄港数は増加しており、青森市でも今年41隻の寄港予定があるほか、今後は100隻まで増やす計画が示されています。
インバウンド観光客の実数や冬の宿泊客数も増加傾向にあります。こうした状況を踏まえ、本県はインバウンド対策には力を入れていると認識しております。
【質問①】令和5年の本県の観光入込客数について、県内と県外の割合及び県外のうち北海道、岩手県、秋田県からの割合について伺いたい。
一方でマイクロツーリズムに関してはどのように取り組んでいるのか、近隣道県からの誘客促進について質問していきたいと思います。
遠隔地からの観光客誘致に頼らず、県内または近隣県からの移動圏内にいる観光客、すなわち近場への旅行を重視した戦略というのは、例えば、コロナもそうでしたが、災害、感染症といった外的要因により、観光が大きく制約される状況になったとしても、一定の需要を維持して、観光産業のダメージを緩和するための鍵となります。
やはり、近隣の観光客が土台となるので、インバウンドや県内外の観光促進という中でも、特に近隣道県、マイクロツーリズムの重要性をより意識していかなければならないと私は思っています。
いろいろなデータを見ると、岩手県や秋田県など近隣県からの来訪者が多いことがよく見受けられます。
車での訪問が中心であり、リピーターも多い傾向であるというのも明らかになっています。
このような実態を踏まえて、改めて近隣道県をターゲットにした戦略的な観光施策が必要であると思っています。
それでは、質問させていただきます。まず一つ目は、令和5年の本県の観光入込客数について、県内と県外の割合及び県外のうち北海道、岩手県、秋田県からの割合についてお聞きします。
回答:佐藤観光政策課長
- 青森県観光入込客統計によると、令和5年の本県の観光客のうち、県内の割合は31.8%、県外の割合は68.2%となっており、県外のうち、北海道は5.5%、岩手県は9.9%、秋田県は5.5%で、隣接道県の合計は20.9%となっております。
この割合は、ここ数年大きな変化はないという認識でよろしいでしょうか。
回答:佐藤観光政策課長
- 今、お答えしたものは令和5年の観光客ですが、コロナ禍前の令和元年では、県内客の割合が38.4%となっており、令和5年度が38%ですから、若干、県内の割合が下がっていることとなっております。
やはり県外からの観光客が増えていると思います。
もちろん、年によっていろんな要因はあると思います。
【質問②】県民による県内旅行や近隣道県からの誘客の促進について、県の認識と取組を伺いたい。
次に、県民による県内旅行や近隣道県からの誘客の促進について、県の認識と取組を伺いたいと思います。
回答:佐藤観光政策課長
- 本県や近隣道県からは、年間を通じて安定した入込があることから、県としては、本県観光を下支えする重要な地域であると考えています。
また、県民や、近隣道県の観光客は、県内各地を何度も訪れ、本県の魅力を再発見し発信していただくことが期待されるため、本県観光の振興にとって、県民による県内旅行や近隣道県からの誘客は重要な取組であると認識しています。 - このため、青森県観光戦略に「近隣道県からの誘客促進」を掲げ、閑散期である冬季の県民向け宿泊キャンペーンや北海道からの教育旅行の誘致、NEXCO東日本等と連携した東北地方の周遊促進企画などに取り組んでいるところです。
キャンペーンもされているということでしたが、PRや情報発信について、近隣道県や県民向けの旅行、いわゆるマイクロツーリズムに関して、現在取り組んでいることや実施している施策はありますでしょうか。
SNSでの発信も継続していただきたいと思います。
また、テレビなど既存のメディアの影響力も、依然として大きいと思っています。
北海道や北東北の民放テレビの企画に対して、行政として関与や提案を行うことは有意義だと思います。
メディアを通じた情報発信は非常に重要であるため、引き続きいろいろな取組を進めていただきたいと思っています。
県の観光危機管理体制について
そして、県の観光危機管理体制について伺います。
【質問】県は観光危機管理体制をどのように整備しているのか伺いたい。
さきほど、近隣道県の観光の話、マイクロツーリズムの話をしましたが、観光危機管理も非常に大事になると思います。
コロナもありましたが、地震、豪雪、風水害、感染症など、予期せぬ事態による観光への打撃を最小限に抑えるため、観光危機管理の視点というのは欠かせないと思っています。
地域の大事な観光資源を守り、観光事業者、観光客を受け入れる地域の生活や経済の影響を緩和するとともに、観光危機からの迅速な回復を図る体制の整備も必要だと思っています。
むつ地域でも土砂災害が発生しており、今後も大きな災害がいつ起こるか分かりません。
感染症についても同様です。
今後、いろいろな予期せぬ事態が起こる可能性がある中で、県としての観光危機管理の体制はどのように整備しているのか伺います。
回答:佐藤観光政策課長
- 県では、災害発生時においては、当部の各課が災害対応に応じた組織体制に移行し、観光施設等の被害状況や観光客の状況についての情報収集、旅行者に対するSNS等を活用した情報発信などに取り組むこととしています。
また、災害時における的確かつ迅速な対応を講じるための業務手順の方法等についてマニュアルを整備し、県庁内では定期的に図上訓練等も実施しております。 - 県内市町村に対しては、災害発生時に観光客の避難等の対応方針を事前に関係者間で情報共有しておくことや、観光施設などの被害状況等を県へ情報提供することについて周知しているところです。
定期的に情報を交換し、共有しているということでした。
やはり定期的にきちんとやっていくことが重要であり、マンネリ化しないようにする必要があります。
特に、最近のコロナで多くの気づきを得る機会がありました。
直近で県内に大きな出来事がなかったとしても、県外で大きな出来事が起こった際に、それらを踏まえて、能登の状況も含めた情報を確認し、何が必要かをより深く検討していくべきだと思います。
マイクロツーリズムに加え、今後さらに増加が見込まれるインバウンド観光客に対応するため、観光における危機管理体制の強化が非常に重要となります。引き続き取り組んでいただきたいと思います。
※以下は先の安藤委員のボールパークの整備に関する質問を受け、小笠原が関連として質問。
関連してお伺いしたいのですが、先ほど安藤委員のご質問にあったボールパークの整備についてです。
検討対象地がいくつかあったとのことですが、具体的にどのような場所が候補地となっていたのか教えていただけますでしょうか。
セントラルパークも候補地の一つとのことですが、ほかにどのような場所があったのか、差し支えなければ、具体的にお聞きしたいと思います。
回答:金沢地域交通・連携課長
- ボールパーク整備の候補地となり得る場所については、例えば青い森セントラルパーク、現県立中央病院・商業高校跡地、新青森県総合運動公園、合浦公園等が考えられたところでございます。
ありがとうございます。
新統合病院の際にも複数の候補地があり、その中から選定が行われましたが、ボールパークについては、安田の運動公園が現在最有力の検討対象地となっています。
十分に検討を重ねた上で、最適な場所を選定し、事業を進めていただければと思います。

ご意見・ご感想など
あなたの声を聞かせてください。




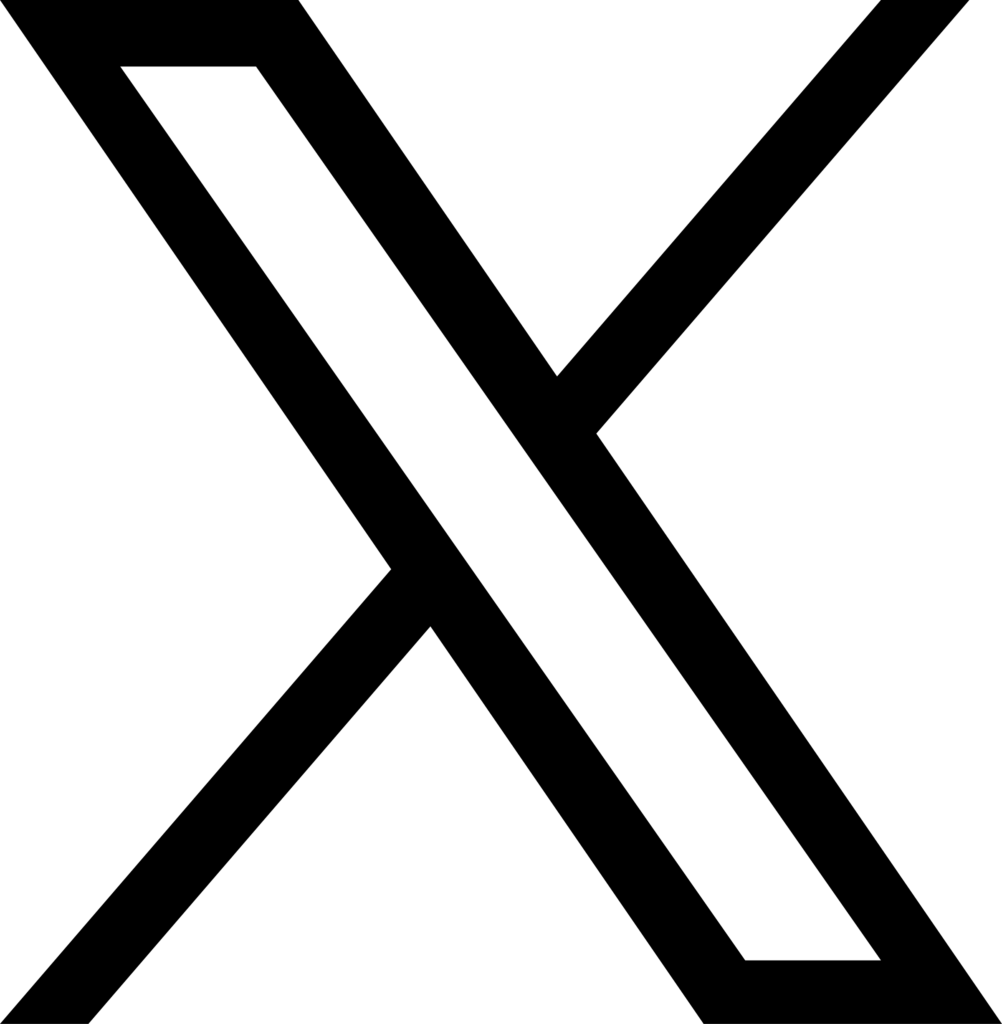
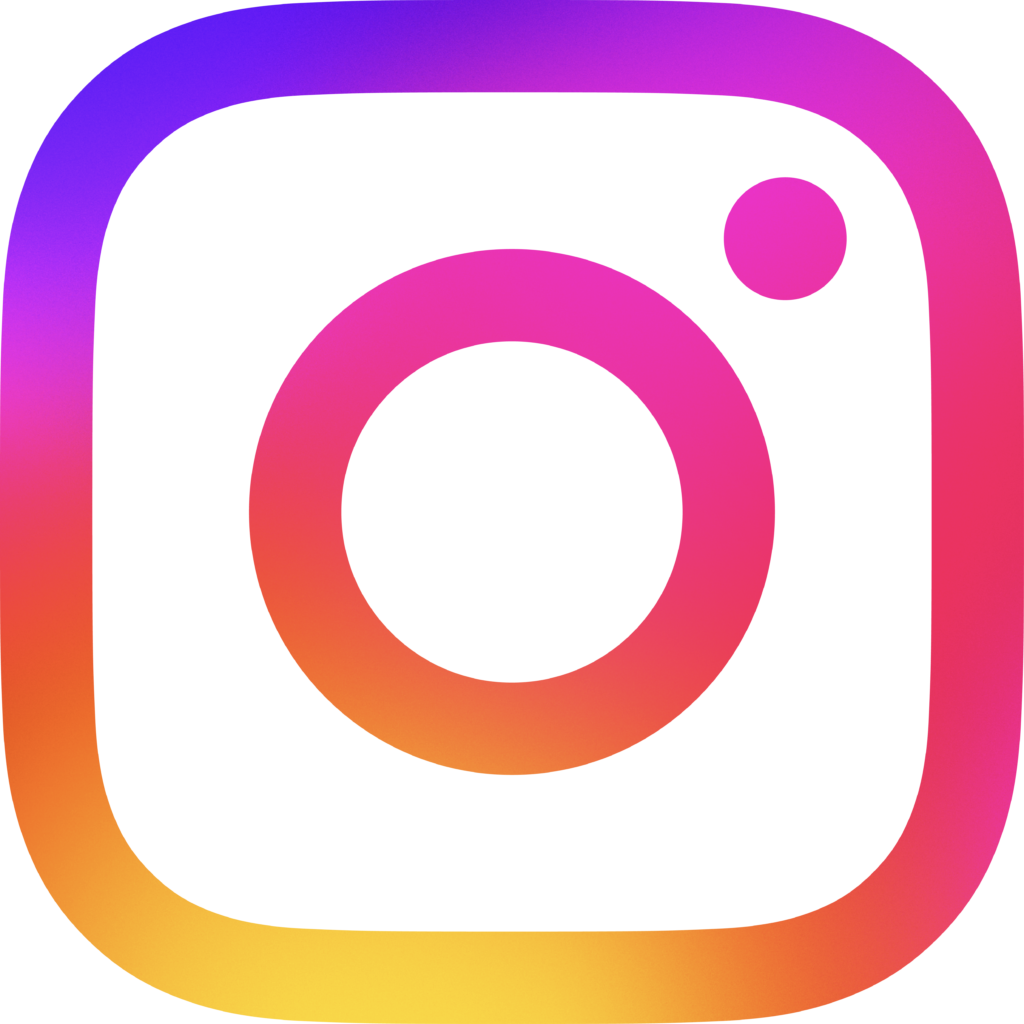

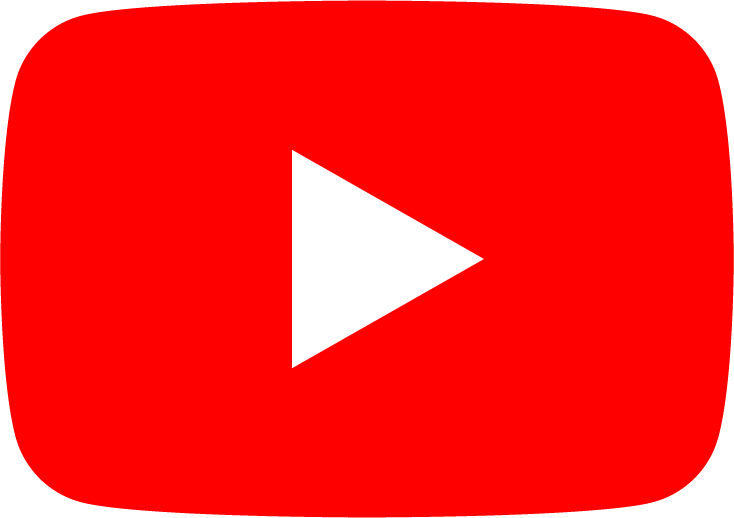

 青森県庁ホームページ
青森県庁ホームページ 青森市ホームページ
青森市ホームページ