
全員協議会での質問【令和7年2月 議員全員協議会】
目次
共同経営・統合新病院に係る基本計画(案)について

新政未来の小笠原です。私から質問していきたいと思います。
【質問①】統合新病院の経営形態について
まず、共同経営・統合新病院に係る基本計画案の中で、統合新病院の経営形態に関して質問しようと思います。
午前中の谷川議員の質問でもありましたが、開院時点では企業団で始めていく。
そして、後に経営状況などを見ながら、地方独立行政法人、いわゆる独法への移行も検討していくというお話でありました。
これに関して、まず、そもそもこの経営形態の決定に当たって、青森県立中央病院、そして青森市民病院、この両病院の職員の意向はどのように把握したのか、そして、その把握した結果というのはどうであったのか伺いたいと思います。
(ア)経営形態の決定にあたり、両病院の職員の意向をどのように把握したのか、またその結果について伺いたい。 回答:荒関病院局長
- 統合新病院の経営形態の検討に当たっては、これまで企業団や地方独立行政法人の制度について、職員団体との勉強会を開催するなど、相互の理解を深めてきたところであります。
- また、職員に対しては、経営形態に関する情報を院内情報サイトに掲載して周知を図るとともに、全職員を対象としたアンケートを実施いたしました。
- 職員アンケートでは、県の病院局職員と青森市の病院職員の合計で、企業団が約35%、地方独立行政法人が約17%、どちらでもよいが約22%、よく分からないが約26%となっています。
- 企業団を希望する理由としては、公務員の身分が維持されるが約83%となっており、地方独立行政法人を希望する理由としては、『人事管理が柔軟』が35%、『自律的・弾力的な経営』が約32%などとなっております。
勉強会なども実施して、アンケートも実施されたということでした。
そして、開院後、企業団で開始した後に、経営環境が安定して、中期的な展望を見通すことが可能となった段階で、国の医療政策の動向であったり、地域の医療機関等との関係であったり、医療従事者の需給動向、また、労働環境などの職員の意向なども確認しつつ移行をということであるのですけれども。
ちょっとまだ私、この文言というのが具体的に分からないんです。
改めて、地方独立行政法人への移行を検討するタイミングの考え方というのはどういったものなのか、もう少し詳しく説明していただければと思います。
(イ)地方独立行政法人への移行を検討するタイミングの考え方について伺いたい。 回答:小谷副知事
- 統合新病院の開院時点においては、これまで同様、議会の関与の下、県と青森市の支援により、安定した経営の確保が期待できる企業団といたしたいと考えているところであります。一方で、経営環境が安定し、中期的な展望を見通すことが可能となった段階で、地方独立行政法人への移行について検討することといたしております。
- 現時点では、そのタイミングについて具体的に申し上げられる状況にはございませんが、まずは経営環境が安定し、中期的な展望を見通すことができるようにすることが重要であろうと考えているところでございます。
現段階では具体的に言うことはできない。
難しいとは思うのですけれども、ただ、そこというのはとても重要な話であるので、きちんとこういう基準であるとか、そういったものをいろいろ示していくというのが重要だと思っています。
最初の質問に戻りますけれども、職員にアンケートを行ったと。
そして、アンケートの結果、県の職員も市の職員も、どちらも企業団での経営を望んでいる方が多いということでした。
どちらでもよい、よく分からないの二つを合わせると22%、26%でほぼ半分、50%ぐらいということで、勉強会などを開いていてもまだ十分に伝わっていない部分もあったりするのかなと思います。
さらに、企業団であるべきなのか、独法であるべきなのかという部分、やはり勉強会であったりとか対話というのは重ねていただきたいと思うのです。
その上で、私としては企業団で行くべきだと思うのですけれども、結局、職員のアンケートでは、統合新病院の経営形態として、企業団がよいと考えている職員のほうが多数であるのにもかかわらず、地方独立行政法人への移行も検討している。こちらは職員の意向に反するのではないかと考えるのですが、県の見解としてはいかがでしょうか。
(ウ)職員のアンケートでは、統合新病院の経営形態として企業団がよいと考えている職員の方が多数であるのに、地方独立行政法人への移行も検討するのは、職員の意向に反すると考えるが、県の見解を伺いたい。 回答:宮下知事
- 我々としても企業団で行くべきだという発想の中で、今回判断をしております。地方独立行政法人については、現時点で検討を進めるわけではありません。これは明言させていただきます。
中長期的に統合した結果として、経営環境が安定し、その展望を見通すことができた時点で移行について検討するということですので、誤解のないようにご理解いただきたいと存じます。
あくまで現段階で考えているわけではない、展望が見えた時点でそういったこともあるだろうという話でありました。
私としては、展望が見えた中でも、なるべく企業団で行くべき、臨んでほしい。
もちろん、そのときも状況によって職員へのアンケートなども行うとは思いますが、企業団での経営を望みたいと思っております。
【質問②】人員計画について
次に、基本計画に書かれている人員計画に関して質問したいと思います。
基本計画案の88ページに書かれていますけれども、県立中央病院の職員数が令和6年4月の時点で1,596人、うち医師数が184人とあって、そして青森市民病院のほうが令和6年4月の時点で725人、うち医師数が65人とあって、1,596人と725人を合わせると2,321人となります。
しかし、84ページの統合新病院の収支シミュレーションでは、職員数、約1,850人となっている。
現県立中央病院と青森市民病院の職員数を合わせると2,300以上で、約500人の減となるシミュレーションとなっているんですね。
これは単純に職員数を削減するという認識でよいのか、そして削減するのであればなぜ削減するのか、そちらの理由について伺いたいと思います。
(ア)統合新病院の収支シミュレーションでは、職員数を約1,850人としており、現県立中央病院と市民病院の職員数を合わせた2,321人より約500人の減となっているが、職員数を削減する理由について伺いたい。 回答:荒関病院局長
- 今回の基本計画案において参考としてお示しした収支シミュレーションでは、職員数について、他病院の病床当たりの職員数を基に機械的に試算したものでございます。
- 統合新病院の人員計画については、今後、具体的な病院機能等に応じて、現場の意見等も踏まえながら対応していきたいと考えているものでございます。
機械的に計算したということですが、午前中の答弁でも、より機能を充実していく、そして医療従事者の職場環境も整えていく方針であると言ったにもかかわらず、500人も職員を削減して、果たしてこれで働きやすく魅力ある職場環境整備ができるのかと思うのですけれども、その認識について伺いたいと思います。
(イ)医師、看護師、技術者等の職員数の内訳はどのようなシミュレーションなのか伺いたい。 回答:荒関病院局長
- ただいま答弁したことに加えて申し上げるとすれば、今回のシミュレーションは、統合新病院開院後20年間の平均として見込んだものでございまして、今後、28年先までという長いスパンになってございまして、そこまで適切に現時点で見込むことは極めて困難だと考えております。
- そういった中で、あくまでも今回のシミュレーションでは、他病院の病床当たりの職員数を参考に、それに基づきまして機械的に試算させていただきました。
実際の病院の人員計画については、本日冒頭に知事からこれから医療従事者の確保もかなり厳しくなるという話もございましたが、そういった様々な状況なり、病院としての機能をどう発揮させていくのかという点も踏まえまして、当然、現場の意見等も踏まえていきたいと思います。
そういったことに基づきまして人員計画を改めて作成していくというのは非常に重要なことだと認識しております。
開院が令和14年で、確かにまだ先の話ではありますし、状況というのは刻々変化していきますけれども。
病院としても医師であったり医療従事者、広く環境を維持できるように、決してきつきつではなく、ちゃんとためがあるような状態で保っていっていただきたいと思うんです。
そして、またちょっと戻りますけれども、約1,850人のもろもろの内訳というのが機械的とはいえ、全く分からないんです。
この約1,850人の内訳、医師であったり、看護師であったり、技術者などの職員数の内訳というのはどのようなシミュレーションであったりするのでしょうか。
回答:荒関病院局長
- シミュレーション上の職員の内訳につきましては、あくまでも正職員ベースでお答えいたしたいと思いますが、医師で約220人、看護師は約800人、医療技術者は約270人として積算しております。
- 例えば、医師220人については、現状、両病院合わせまして214人となっておりますので、ほぼ同程度ということでのシミュレーションでございます。
そういった数字があるというわけですが、なぜこの基本計画案にはそういった内訳が記載されなかったのかなと思うのですけど。
記載されなかった理由というのはなぜなんでしょうか。
回答:荒関病院局長
- 申し訳ございませんが、特段意図はございません。今、ご質問に応じてお答えしたとおりでございます。
私たちも頂いた資料などを見ながら、こういった議論をしていくというものですので、なるべく必要な数字というのは記載していただければと思っております。
この数字は機械的だとおっしゃっていますが、必要な数字というのはなるべく細かいものも書いていただければと思っております。
【質問③】交通渋滞対策について
次に、交通渋滞対策について、先ほど福士議員のほうからも質問があった項目です。
特に今年、青森市は非常に雪が多くて、除排雪も大変な状況で、浜田周辺というのもこういった状況が続くと、すごく混むわけです。
現に、シーナシーナ青森、前はイトーヨーカドーですけれども、本当に混むわけですね。
そういった中で、緊急の中で交通渋滞対策というのは本当に対策していかないといけないと思うのですけれども。
そして、渋滞対策を考える中で、基本計画案の敷地利用計画、以前からこういった地図みたいなものが出ているんですけれども。
サンドームの東側、一番狭くなっている部分、都市計画道路3・4・23号浜田豊田線、道路拡幅の計画ありと概要版のほうにあります。
こちらはどうやったって拡幅していかないと、普通の渋滞とかを考えても、特にこういった雪の状況とかを考えても、確実にやっていかないと、もうどうしようもならないと思います。
道路を拡幅するということは、市道ではありますが、やっぱりちゃんと計画を立てて整備をしていかないといけない。
交通渋滞対策のためにも、敷地利用計画に記載された統合新病院の東側、浜田豊田線の道路拡幅は確実に必要であって、そのためには用地買収が必要となります。
開院に向けての用地買収の計画はどのようになっているのか伺いたいと思います。
交通渋滞の対策のためにも、敷地利用計画に記載された統合新病院の東側、浜田豊田線の道路拡幅は必要であり、そのためには用地買収が必要となるが、開院に向けての用地買収の計画はどうなっているのか伺いたい。 回答:荒関病院局長
- サンドーム東側の市道浜田54号線については、平成7年8月に都市計画決定した都市計画道路3・4・23号浜田豊田線であり、延長1,210メートルのうち、幅員20メートルの計画となっており、うち410メートルが未着手、残り800メートルは20メートルに拡幅済みとなっております。
- 先般、1月13日に開催した浜田地区住民との懇談におきまして、青森市から都市計画に基づき道路拡幅を想定している旨、説明があったところでございます。
現時点もそういった拡幅が続いているということで、市ともしっかり連携、調整など、いろいろ話をしながら進めていっていただければと思います。
【質問④】周辺環境や景観と調和した施設を計画するとあるが、その具体的な内容について伺いたい。
次に、計画にも書かれていますが、今回、浜田中央公園がほぼ使われないような形になったんですけれども、病院の周辺環境であったり、景観と調和した施設を計画するとありますけれども、こちらの具体的な内容に関して伺いたいと思います。
回答:荒関病院局長
- 基本計画案の施設整備方針においては、地域との共生に配慮した施設整備として、道路交通などの課題に適切に対応するとともに、隣接する浜田中央公園との一体的な機能整備、調和を図るなど、地域の安全・安心を支えるエリア拠点として、県民、市民に愛される施設を目指し、周辺環境や景観と調和した施設としたいと考えております。
- 具体的には、今後、設計の中で検討していくこととなりますが、例えば建築デザインとして、周辺建物と調和する色調や素材を使用すること、建物の高さや規模を周囲と調和させるよう工夫すること、自然環境の保護として、既存の樹木や植生を最大限に生かすこと、新たな緑地やガーデンスペースを設置すること、文化的要素の取り入れとして、地域の歴史や文化を反映したデザインやアートの導入などが考えられるところでございます。
ぜひこういった景観には本当に配慮していただければと思います。
せっかく公園が残っても、そこと全然ちぐはぐな景観であったりすれば、そんなことはないと思いますけれども、そういった病院であってはならないと思います。
病院を利用する方が公園を治療の一環として利用するということもあったりするでしょう。
そういった中で、この一帯の景観などが保たれたような、青森の誇れるような病院としてそういった設計などもしていっていただければと思います。
【質問⑤】整備費・運営費の負担割合について
次に、整備費、運営費の負担割合に関しての質問です。
現時点では、県が5分の3、市が5分の2ということですけれども、この整備費、運営費の負担割合において、基本計画案などを見ると、個別に考慮すべき事項については別に設定するといった記載があるのですけれども、個別に負担割合を検討する事項としてどのようなものが挙げられるのか伺いたいと思います。
(ア)整備費・運営費の負担割合において、個別に考慮すべき事項については別に設定するとあるが、個別に負担割合を検討する事項としてどのようなものが挙げられるのか伺いたい。 回答:荒関病院局長
- 現在の県立中央病院と青森市民病院では、それぞれ県及び青森市の施策として実施している事業があり、そうした項目については、個別に負担割合を決定する必要があると考えています。
- 例えば、県の施策として実施しているものとしては、ドクターヘリや小児在宅支援センター、総合周産期母子医療センターなどがあります。
- なお、これらの項目については、現時点では具体的な面積、運営体制などが決定していないため、今後、設計等が進んだ段階において、負担割合について改めて設定したいと考えております。
一応、そうした個別の部分に関しては、また別であるという具体例も示していただいて了解いたしました。
そして、こちらは午前中の議論でも少しあったんですけれども、赤字のことに関してなんですが、もし赤字が発生した場合の負担の割合というのはどういうふうになるのか伺いたいと思います。
(イ)赤字が発生した場合の負担割合について伺いたい。 回答:荒関病院局長
- 開院後の統合新病院の運営において、資金不足などにより、県、青森市からの補填が必要となった場合の負担割合については、県が5分の3、青森市が5分の2とすることが基本と考えております。
現時点でも負担割合としてはほぼ同様な形ということでありますけれども、赤字が発生した場合に関しても、市ときちんと事前に協議などをしておいていただければと思います。
【質問⑥】統合新病院の診療科について
次に、診療科のことに関して少し質問しようと思います。
今回、39の診療科目ができていくという中で、精神科もより整備していくべきではないかという話が有識者会議のほうで出ておりました。
また過去の有識者会議で、精神科スーパー救急の受入れに関する課題も挙げられていましたけれども、県としてはどのように考えているのか伺いたいと思います。
過去の有識者会議では精神科スーパー救急の受入れに関する課題が挙げられたが、県としてどのように考えているのか伺いたい。 回答:大山病院事業管理者
- ご質問のように、昨年11月12日に開催されました第7回の有識者会議におきまして、構成員の方から、現状では精神科スーパー救急の受入れは市内の民間医療機関が引き受けていることから、速やかに地域医療連携推進法人を立ち上げて、民間医療機関を入れて、きちんとした関係づくりを進めていくべきであるとのご意見をいただいたところでございます。
- 精神的治療と身体的治療の両方が必要な救急患者さんへの対応につきましては、身体的処置をEICU──救急外来の集中治療室などで行った後、精神科のリエゾンチームがございますので、そのチームが対応するなど、現在の県立中央病院での運用を基本としているところでございます。
- 県といたしましては、令和6年度中に地域医療連携推進法人を設立することとしております。
今後、民間医療機関等を含めまして、現状を共有しながら、この法人の取組の中で医療機関の連携、そして機能の集約、分化について整理していきたいと考えております。
精神科にかかる人は、今、本当にどんどん増えていっていますから、これは精神科に限った話ではないんですけれども、地域医療連携推進法人なども活用して、体制というのをきっちり整えていっていただきたいと思います。
【質問⑦】専門センターの設置について
今は精神科スーパー救急などの受入れの話をしましたが、小児科医に関して、こちらも午前中、工藤議員から質問がありまして、増やしていきたいといった話もありました。
そして、小児医療センターの設置を検討していくと基本計画のほうにもあるのですけれども、設置する、ではなく、『設置を検討する』という曖昧な表記になっている理由を伺いたいと思います。
小児医療センターの設置が「今後設置を検討する」となっている理由を伺いたい。 回答:大山病院事業管理者
様々なハードルがあるでしょうから、一口に小児といっても、外科もできる小児科医の方がいらっしゃるのかとか、そういった問題もあると思います。
なかなか困難ではあると思いますけれども、ぜひ開院したときに設置できるように、何とか努力をしていっていただければと思います。
【質問⑧】県立中央病院の跡地の利活用について、青森市東部地区の医療拠点を確保する観点も踏まえ、どのように考えているのか伺いたい。
次に、跡地のことに関して質問しようと思います。
今回移転するに当たって、青森市の東部地区の県立中央病院がなくなるわけです。
ただ、ヘリポートであったり、救命救急センターなどもあったりして、そこは比較的新しかったりするんですけれども。
いずれにせよ、青森市東部地区の医療拠点がなくなるわけなんですが、現時点で県立中央病院の跡地の利活用について、青森市東部地区の医療拠点を確保するという観点も踏まえた上で、どのように考えているのかお聞きしたいと思います。
回答:荒関病院局長
- まず、一般的に県有地の利活用については、県庁内や市町村による公共利用について検討するとともに、サウンディング調査により民間事業者から市場性の有無、アイデア等の収集などを行い、民間による活用についても検討することなどが考えられます。
- 県立中央病院跡地の利活用については、地元住民の意向なども確認しながら、ただいま議員から御指摘のあった東部地区の医療体制も含め、様々な観点から検討を進める必要があるものと認識しております。
- その際、重要な視点ということが幾つかあるんだとは思います。
- まずはまちづくりという観点から申し上げれば、この場所は青森市の立地適正化計画において生活拠点区域となっていること、
- それを踏まえた場合、どういう方向性がいいのか、あるいはここは津波浸水想定区域でもありますので、そういった観点から、制限されるもの、そうではないもの、どういうふうに整理するのかなどいろいろな観点があると思いますので、
- そういう観点も踏まえながら、あとは住民の意向ということも最大限配慮して検討していくことが重要ではないかということで現時点では認識しております。
まちづくりの観点という言葉を久々に聞いた気がしましたけれども、まちづくりが大いに関係してくると思うのですよ。
ただ、今おっしゃられたように、津波であったりとか、そういったこともゼロではないわけです。
だから今回も東部の場所、よくないのではないかみたいな議論がずっと続いてきたわけですけれども。
ずっとここにあった医療拠点がなくなってしまう。
東部地区の住民の方々にとっては本当にゆゆしいことでありますので、もちろん、住民の方々にもきちんとお話を聞いた上で、こちらの利活用を進めていっていただければと思います。
【質問⑨】浜田地区住民からは知事・市長から直接説明を聞きたいといった声も出ているが、知事・市長両名での対話の場を開催する予定はあるのか、県の見解について伺いたい。
最後の質問をしようと思います。
こちらは病院そのものというか、プロセスの話というか、説明の話になるんですけれども、先日の7日、青森市のほうで病院に関する説明会がありました。
市議会のほうで説明会があって、それで西市長は地区住民懇談会に出席する意向だと、こういったお話をされました。
そして、先般の報道でも、そして本日の議場の中でも、知事も3月下旬の「#あおばな」で浜田地区住民で構成する協議会に臨んでいく、対話をしていくといったお話であったんですけれども。
私としては、両名が、青森市長と青森県知事2人でそういった対話の場というのを開く必要があるのかなと思うのです。
今までさんざんお話もされてきました、先般の委員会などでも出席するべきではないかという話はあったと思うのですけれども、単純にプロセス云々だけの話ではなくて、住民の方々のいろいろな感情であったりとか思いというのが乗っかっての話だと思うのです。
そうした中で、きちんと責任ある首長が、もちろん、ふだん出席されている部長、局長の方々に責任がないという話ではないですけれども、やっぱり住民の方に対して説明をするというのはすごく重要なことだと思うのです。
今のところ、両名出席の意向というのはあるのですけれども、できたら、知事、市長両名での対話の場を開催すべきだと思うのです。
こちらの県の見解について伺いたいと思います。
回答:荒関病院局長
- 本日午前中、谷川議員にお答えしたとおり、知事は3月下旬に開催が予定されております県民対話集会「#あおばな」において、統合病院浜田地区協議会の意見を伺う機会を設けているということでございます。
それは分かるんですけれども、市長との両名での対話の場というのは現時点では考えていないということでしょうか。
回答:宮下知事
- 対話集会について、少し経緯を申し上げますと、
- 昨年の12月上旬に全体の申込みがありまして、その中に統合病院浜田地区協議会も入っておりました。
- その後、年内には実施団体を決定していて、1月15日に団体のほうにはやりますということを通知しています。
- そのことは、1月16日にはプレスリリースをしていて、この対話集会に関しては以前から決まっていたということをご理解いただきたいと思いますし、15日には団体の皆様には通知をしています。
- 私としては、説明の機会というものも非常に重要です。
これは懇切丁寧に、次の機会は恐らく基本計画の中身について、今日議論させていただいている内容も含めて、住民の皆様からご意見、ご質問を賜って、それに対して丁寧にご説明させていただく機会だと思っております。
私としては、そういう説明の機会も大事ですが、直接対話、それから広聴の機会として対話集会を設定させていただいております。 - この「#あおばな」という対話集会は、もう既に県内各地で100回行っていて、その中では関係する市町村長に駆けつけていただくということもたくさんありました。そうした中で、青森市長からその意向があれば、当然、私としては承るというようなことで考えております。
※その後、2025年3月17日に、知事と青森市長の両名が参加する広聴会が実施された。

ご意見・ご感想など
あなたの声を聞かせてください。




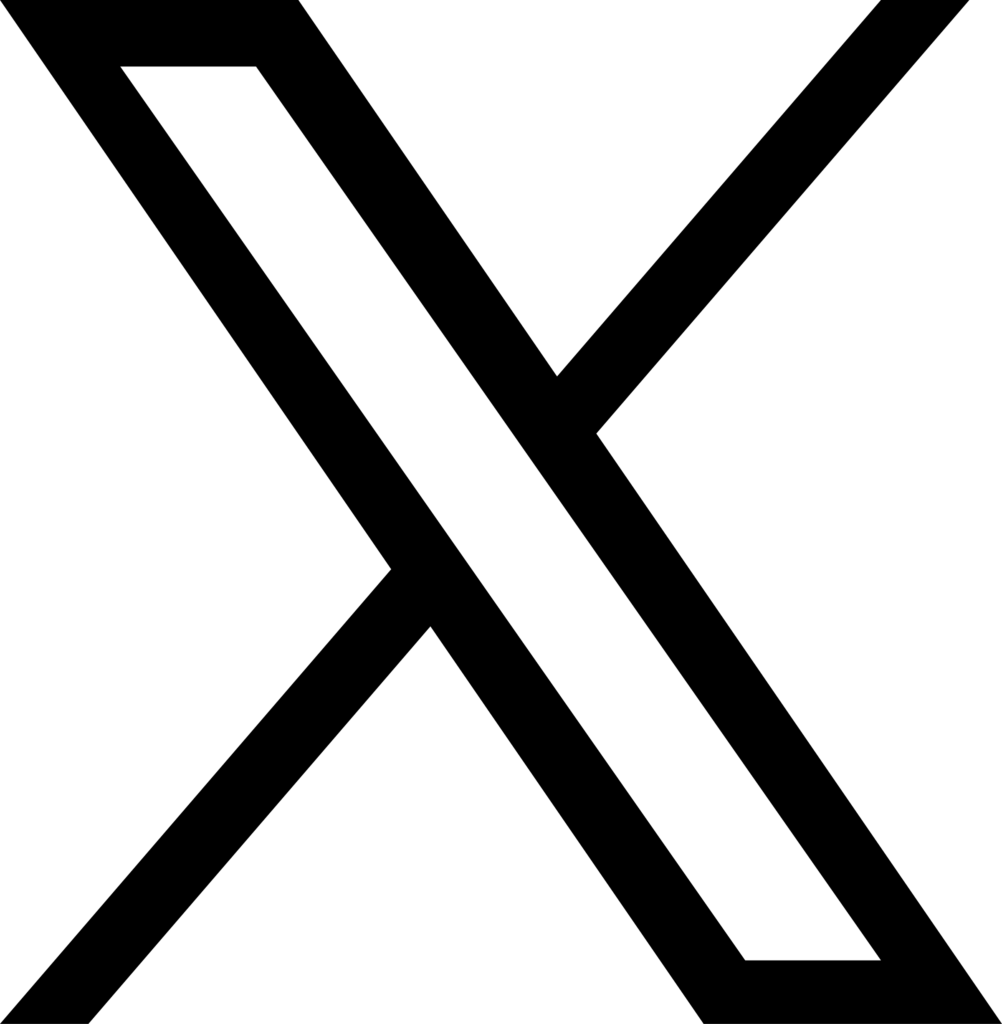
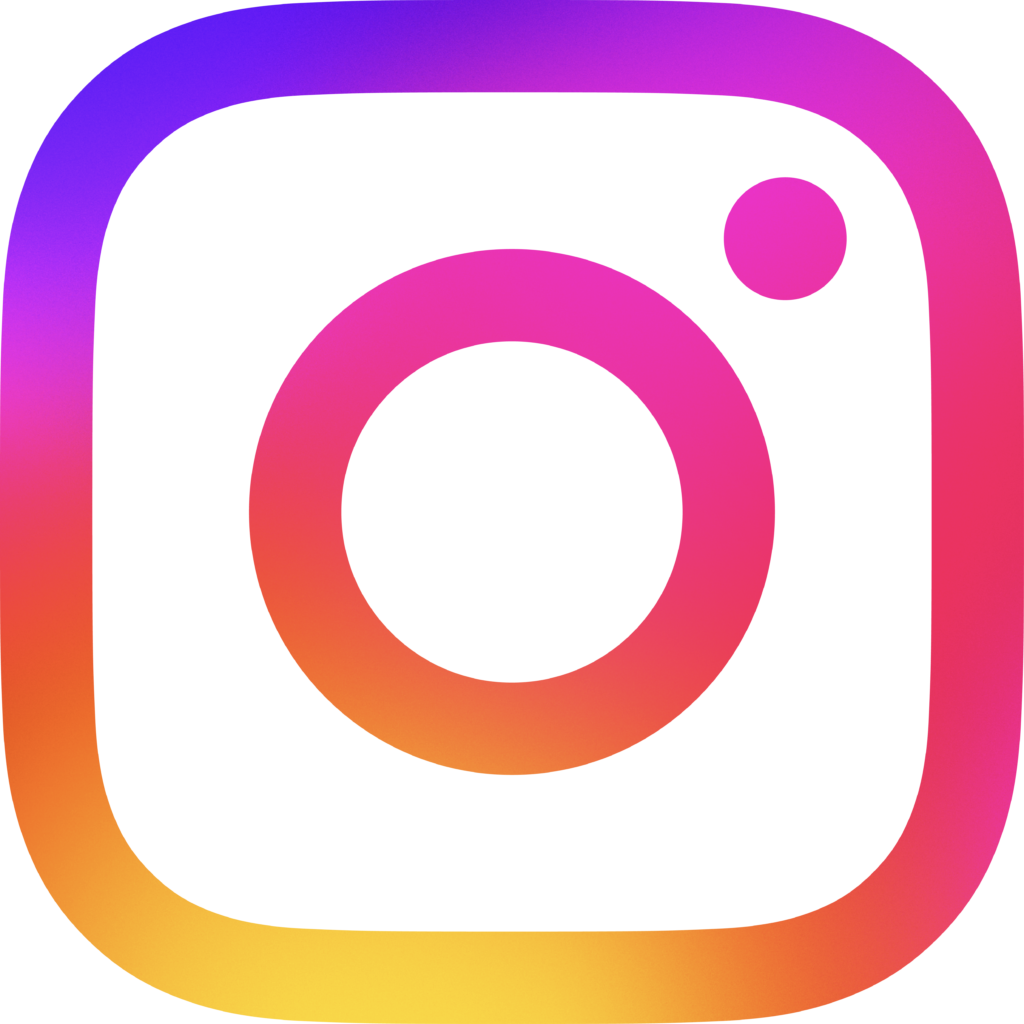

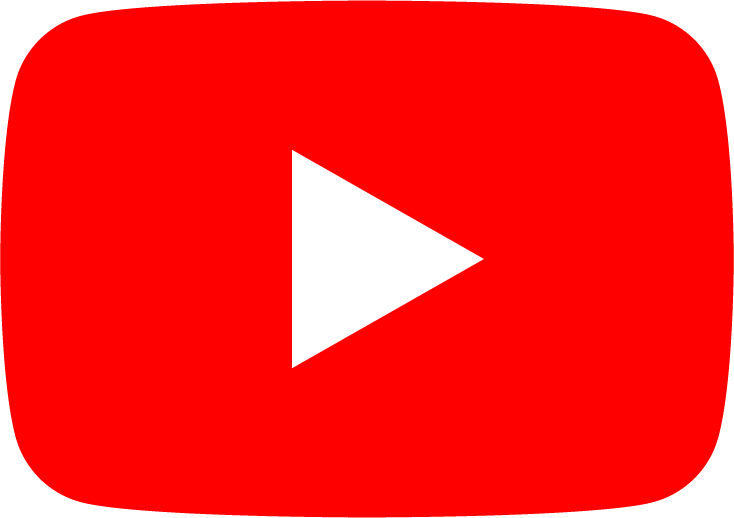

 青森県庁ホームページ
青森県庁ホームページ 青森市ホームページ
青森市ホームページ